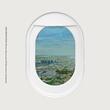蓮沼執太がひさびさのソロアルバム『unpeople』を完成させた。近年は蓮沼執太フィルでの活動をはじめ、アート作品の展示から映画やドラマの劇伴制作、〈東京2020パラリンピック開会式〉における楽曲のプロデュースなどで幅広く活躍していたが、本作は〈純粋に自分のための音楽〉として5年の制作期間を経て完成したもの。ソロ名義でのスタジオアルバムとしては『メロディーズ』(2016年)以来7年ぶり、インストゥルメンタルでは『POP OOGA』(2009年。一部歌唱あり)以来15年ぶりのリリースとなる。
本作に収録された14曲ではアナログシンセを全面的にフィーチャーすることで電子音楽作家としての側面を伝えると同時に、楽器と非楽器、世界各地の様々な場所で録音されたフィールドレコーディングの音源を編集して組み合わせることで、現代音楽作家としての側面も強く表れている。テクノ、アンビエント、エレクトロニカ、ジャズなどを横断し、既存の枠組みを軽やかに飛び越える楽曲からは、〈ポストジャンル〉時代の作家としての資質もはっきりと伝わってくる。
記名性の強いギタープレイを提供しているトータスのジェフ・パーカーやCornelius、ギターのみならずドラムマシンやフルートも演奏している灰野敬二をはじめ、ニューヨーク在住のドラマーであるグレッグ・フォックス、元水曜日のカンパネラのKOM_I、沖縄在住の音楽家・新垣睦美など、多数のゲストが各曲に彩りを加え、蓮沼執太フィルからも石塚周太と音無史哉、エンジニアの葛西敏彦が参加。その顔触れからも蓮沼の足跡が見て取れる。
この5年間で訪れた様々な場所、この5年間で出会った様々な人との記録が集約された『unpeople』は私小説であると同時に旅行記のようでもあり、音楽やアートを通して社会を描いた論文のようでもある。そして、時を奏でる作家としての蓮沼執太が改めて強く感じられる作品であることも間違いない。
※このインタビューは2023年10月10日(火)に発行された「intoxicate vol.166」に掲載された記事の拡大版です

100%蓮沼執太の音楽を
――資料には〈制作期間5年〉とあって、2018年くらいから楽曲を作っていたことになると思いますが、最初から〈ソロアルバムを作ろう〉と思ったのか、それとも〈とりあえず手を動かそう〉みたいな感じだったのか、どちらが近いですか?
「アルバムのために作曲を始めたわけではなく、とりあえず自分のソロとして、何か手を動かしてみようみたいなところが最初ですね。例えば『メロディーズ』のときのように、最初からコンセプトを決めたわけではなく、そのときにある周りの機材や環境で始めた感じでした。
あとフィルも含めていろんな仕事をやってることもあって、自分の音楽作品となかなか向き合えなかったので、そういう時間の中で自分のためだけのことをやるっていう、メディテーション的な感じで始めた部分もありました」
――それを始めたのが2018年だったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
「当時はニューヨークと東京を行き来してたので、最初はニューヨークのプライベートスタジオで作り始めたんですけど……アルバムまでは行かなくても、何か自分の曲を作りたいなっていう、最初はそんな感じだったと思います。
時間軸的にはフィルの『アントロポセン』(2018年)を作り終わった後ぐらいだと思うんですけど、フィルでの創作は各メンバーとのコミュニケーションとも言えます。そうするとどうしても100%の蓮沼執太ではなくなるので、100%蓮沼執太みたいなことをやりたい気持ちがどこかにあったんでしょうね」
――2018年は未発表音源集の『windandwindows』を出したタイミングでもありました。
「この年は展覧会もあって、ずっとハイな状態で、『windandwindows』は過去曲の総集編みたいな雰囲気があったから、気持ち的には次なるフェーズにっていう感じになってたと思うんですよね。ニューヨークの展覧会が終わったのが1月頃だったんですけど、資生堂ギャラリーでやった〈 ~ ing〉が6月まであって、すぐにアルバムを作ろうとは思ってないけど、楽曲的な芽生えとしては、次なる場所へ行こうぜっていう気持ちになってたんだと思います」
――そこから2019年に帰国して、さらにはコロナ禍もあったりという中で、徐々にアルバムとしての構想が見えてきた?
「断片的な素材はすごくたくさんあったんですけど、2019年の段階ではまだアルバムには全然なってないですね。コロナ禍で時間があったから急に素材たちが膨らみを持って楽曲になった認識もあんまりなくて、やっぱりちょこちょこちょこちょこ作って、2年ぐらい前から、いよいよこの子たちを何とかしなきゃいけない、みたいな気持ちになってきたんだと思います。
それで2022年の9月から1曲ずつ配信リリースしていくことを決めて、あわよくばアルバムになってほしいって感じでした」