秩父を拠点に活動するギタリスト・笹久保伸と、彼を中心とするアート運動〈秩父前衛派〉を軸に、同地で巻き起こりつつある新たな潮流に迫る連載〈秩父は燃えているか〉。今年9月、笹久保はロンドン在住の現代音楽家・藤倉大とのコラボレーション・アルバム『マナヤチャナ』をソニーからリリースした。ピエール・ブーレーズのような現代音楽界の巨匠からも高い評価を得る一方、デヴィッド・シルヴィアンをはじめとする異ジャンルのアーティストとのコラボも経験している藤倉と、フォルクローレを主なバックグラウンドとする笹久保という、まったく違った個性を持つ2人の魅力が、アンビエントともエレクトロニカともつかない独特なサウンドに結実した力作だ。
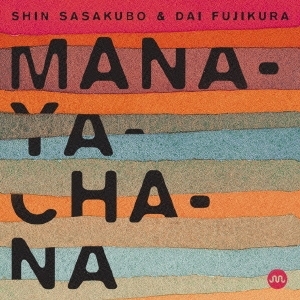
このアルバムを語る際の大きなトピックとなるのが、当事者である2人が一度も顔を合わせずに作品を作り上げてしまったという現代的な制作背景。そんな彼らが実際に出会い、『マナヤチャナ』を語りながら収録曲を演奏するという貴重なイヴェントがタワーレコード渋谷店の7Fにて行われた。当日は『マナヤチャナ』のリリースに関わったソニーの杉田元一が進行および演奏のアシストを務め、会場には笹久保とのアルバム『アヤクーチョの雨』で強烈なヴォーカルを聴かせていたイルマ・オスノの姿もあった。そんな約1時間に及んだ刺激的なイヴェントの模様を徹底レポート!

コラボレーションの経緯
杉田「藤倉さんは作曲家なので、基本的には普段は演奏はされないんですよね?」
藤倉「はい、あまりしませんね」
杉田「でもピアノを弾くというお話をうかがいました。ショパンなんかお好きなのでは?」
藤倉「ときどき弾きますね。ショパンは10代のときに弾いていました」
杉田「一方で笹久保さんは秩父を拠点にギタリストとしてすでに22枚ものアルバムを制作しているということで。まだ30歳だっけ?」
笹久保「はい」
杉田「このご時世になんという……」
笹久保「いまCD売れないですからね(笑)。今年は一年に5枚出しました」
藤倉「自主制作なの?」
笹久保「そうなんです。いつも身を削りながら作っていたんですけど、今回は藤倉さんという大スターと一緒に(笑)」
杉田「藤倉さんといえばバリバリの現代音楽のトップ・コンポーザーなわけですが、畑の違う笹久保さんとのコラボ作である『マナヤチャナ』を作るに至った経緯や発端を教えてください」
藤倉「この作品は僕と笹久保くんの共同作曲なんですが、実は彼とは昨日初めて会ったんです。電話やSkypeで話したこともなくて。Facebookのメッセージ、チャットだけでアルバム全部を作ってしまった」
笹久保「最初、僕が藤倉さんに〈ギターのソロ曲は書いてないんですか?〉とメールをしたんです。藤倉さんの曲を弾いてみたいと思っていたので。そしたら1分の曲(“Sparks”)はあるとのことでしたが、その尺の曲をコンサートのプログラムに取り入れるのは難しくて、〈もっと長い曲はないんですか?〉と聞いてみた。本当は曲を書いてもらいたかったんですが、藤倉さんに依頼するとなると何千万とかかるんでしょ?(笑) でも結果的には〈曲を書くなら一緒にやらない?〉と言っていただいて」
藤倉「僕の作品を弾いてくれる方は世界中にいるんですが、笹久保くんのような不思議なバックグラウンドの人にただ弾いてもらうより、どうせなら一緒に曲を作れないかと思って」
笹久保「それで最初に、10秒から15秒くらいのサンプルを送ってほしいとのことで、そのつもりで秩父で録音していたら3時間くらいの長さになってしまって。何度か藤倉さんに送りながら」
藤倉「まあ、断片だったんですけど。それを僕が一音一音……」
笹久保「3時間の断片ってウザいですよね(笑)」
藤倉「いやいや(笑)。その3時間のなかで〈ピン〉とか〈パン〉とかの一音だけを切り取って、そこから全部の音を加工して、まずはバッキング・トラックを作りました。それを笹久保くんに返して、その上に乗るようにギターを弾いてもらったものを送り返してもらい、それを僕が再編集/再構成して1曲ができるという流れ。ちなみにこのアルバムには2曲だけ歌が入っていて、それはイルマ・オスノさんに歌っていただいたんですが、それ以外の音は笹久保くんのギターのみ。エレクトロニクスに聴こえる音も、全部ギターの演奏を加工して作ったものなんです」
笹久保「でも、藤倉さんから送り返されたときに自分のギターだとは思えなくて、ロンドンで新たに雇われたギタリストの音が返ってきたのかな?と思ったんです」
藤倉「それ先週まで言ってたよね」
笹久保「〈これ俺じゃないでしょ〉って(笑)。バラバラに音を分解して、それを繋いでフレーズにして、あたかも一人のギタリストが弾いているように藤倉さんが作ったという。なのであまり人間的じゃなくて、ライヴでやるのはいやだなあと(笑)」

藤倉「難しいよね。歌は、イルマさんが近くにいるのが分かっていたから、もしスタジオに遊びに来られるならちょっと歌ってもらえないかな?という話になって。その後、ギターの伴奏も付いて完璧にミックスされた、このままでもリリースできるというくらいのクオリティーの歌が送られてきたんです。僕はすごく好きだったんですけど、大変申し訳ないとは思いつつ、それを聴いてなぜか〈分解しよう〉と判断してしまった。それで歌だけを取り外して、笹久保くんが違う日に弾いたまったく関係のない素材に押し込んじゃった。テンポも違うので切り刻んで……ほんと、ごめんなさい。でもあれ、ケチュア語で歌っているんですよね?」
笹久保「ケチュア語は、ペルーとボリビアのアンデス地域に住むケチュア語文化圏で使われる言葉ですね。この日本においては何の普遍性もないし、南米を象徴する言語でもないのに、よくソニーから発売されたなと不思議な感覚です。CDのタイトル/曲目は全部ケチュア語なんですが、僕が〈英語にしましょう〉と提案したところ、藤倉さんがせっかくだからケチュア語にしようということで」
藤倉「この作品って、僕たちにとっては楽しみのためだけに作ったものなんです。誰かの依頼で作ったわけじゃなくて。笹久保くんはソロのアルバムを作っていて、僕は僕でオペラをやっと書き終えたところだった。オペラって契約がすごく面倒くさいことが多いんですが、そういった制約のない、本当にただ純粋に音楽だけが作りたいという想いでした」
笹久保「オペラを作るのに1年半くらいかかったんですよね? そのオアシス的な拠り所として自分の好きなものを……」
藤倉「そうそう。リリースのことなんか全然考えずにほんとに遊びでやり始めた。笹久保くんが送ってくる断片がものすごく面白くて、毎日憑りつかれたかのようにどんどん作っていったんです。彼もフットワークが軽くて、こちらから素材を送ったら次の日には返ってくるので、すぐ1曲ができちゃって。そんな流れで3曲目、4曲目とできていって、そこで〈どうしよう、これアルバムになりそうだけど?〉と」
笹久保「自分たちで出そうか?みたいな」
藤倉「お金がまったくかかっていないからね。自分の寝室で作って、マスタリングまでやっちゃったし。笹久保くんは自分のレーベル(CHICHIBU LABEL)を持っていて、僕もミナベルというレーベルをやっている。じゃあ一緒に出そうかという話になったら、ソニーの杉田さんに興味を持っていただいて、日本ではソニーから出すとおっしゃてくれて。それでいまここに座っているという話です。僕たちだけでリリースしたら、ヘタしたら誰も取材に来てくれなかったんじゃないかな(笑)」
笹久保「藤倉さんがパフォーマーとして登場するというシチュエーションも、あまりないですからね」
杉田「本邦初公開どころか、もしかして世界初公開かな? 今日は『マナヤチャナ』から4曲ほど演奏をしますが、バッキング・トラック、ギター、藤倉さんのサイン波で新しい世界を創ってみるという試みです」
藤倉「ちなみに、初めて一緒に音を出して演奏したのは40分くらい前」
杉田「本当にチャレンジングな企画ですね。ではアルバムの1曲目、〈未知のもの〉という意味を持つ“マナヤチャナ”をどうぞ」
『マナヤチャナ』に隠された秘話
藤倉「この曲、最初から最後まで通したのいまが初めてだよね?」
笹久保「そうですね。初めて弾いた(笑)」
藤倉「『マナヤチャナ』には秘話があって。僕ら、実はネット上でリハーサルしてたんですよね。まず僕が送ったバッキング・トラックを笹久保くんにステレオで流してもらって、その前に彼が座ってギターを弾く。それをiPhoneで撮ってから送り返してもらい、僕はそれを聴かずにインプロするというスタイルで。そうすると理論上、共演で即興してることになるかなと思ったんです。僕たちの場合ロンドンと秩父で時差がありますから、Skypeでやるのもちょっとしんどい部分があって、こういうやり方に落ち着きました。そうすると共演に関しても予算ゼロでできちゃう」
杉田「2人がFacebook上でやりとりしてるのを見ていたんです。それで音源を聴かせてもらって(リリースに繋がった)、という経緯でしたね」
藤倉「そもそもなぜそんな流れになったかというと、お互いの時差がある関係で笹久保くんが家でメールを開いたときに、3つも4つも新しいファイルが追加されている。そのなかのどれを僕が聴いてほしいのか、ファイルの数が多すぎて分かりづらい。だったらということで、まず僕のオフィシャルサイトで掲示板的にパスワードとIDで入れるページを作ったんです。そこに載せたものを聴いてもらおうと思って。さらに、パスワードとIDを音楽業界の人にばらまいて〈覗き見しませんか?〉というところまで拡げたら、杉田さんが……」
杉田「はい、引っかかりました(笑)。というところで、そろそろ2曲目の“ルミ”をやりましょうか。〈ルミ〉ってどういう意味だっけ?」
イルマ「石、です」
杉田「なぜ〈石〉なんですか?」
藤倉「曲の最初の雰囲気が石っぽいというか、コロコロしていて……」
笹久保「(ここで突然)さっきから僕が何もしゃべらず何をやっていたかというと、調弦を一曲ずつ変えて曲を作ってしまったんです。演奏することを考えずに録音して、いざ完成してみたら自分でもよく分からない調弦で弾いていて、すごい大変だったんです」
藤倉「僕はそれ知らなかった。よく弾けるよね」
笹久保「いや、どこを弾いてるのか分からなくなりますよ(笑)」
藤倉「先週くらいまで、〈これ笹久保くんのパートだから聴いて練習しておいてね〉と言っても〈これ、僕は弾いてないです〉とか言って(笑)」
杉田「藤倉さんのFacebookページに行くと、メッセージでのやりとりが残っているじゃないですか? 〈これは調弦が違うから続けて演奏はできない〉とかあって」
藤倉「いまさら言われても!と(笑)」
笹久保「必死で練習してきました」
もっとも怖かったこと
杉田「タイトルの由来について教えてください」
藤倉「杉田さんにソニーから出したいと言われたとき、まだタイトルが付いていなかったんです。笹久保くんからは英語でという提案がきていたけど、僕としては大手であるソニーがどこまで本気なのかなという想いがあって。だったら全部ケチュア語にしてしまって、それでも出したいと言ってくれたらいいかな、と。」
杉田「試されたんだ(笑)」
藤倉「ちなみにケチュア語って何人くらい話す人がいるんですか?」
イルマ「たくさんいると思います。エクアドル、ペルー、ボリビア、あとアルゼンチン(の一部)」
藤倉「じゃあそこで大ヒットするかも(笑)。でも全曲ケチュア語でタイトルを付けたっていうのはすごいよね。タイトル案を教えてもらったとき、僕にとっては〈マナヤチャナ〉が一番よかったので、それをアルバムのタイトルにしました。ちなみにこの作品のデザインをやったのが僕の奥さんの弟(ブルガリア出身/オランダ在住のデザイナー、ミハイル・ミハイロヴ)で、彼はミナベルのデザインもやってくれているのですが、タイポグラファーである彼は綴りを気にするんです。そんな彼が〈マナヤチャナ(MANAYACHANA)〉は〈A〉が多くてすごくいいと。じゃあそれで決まり、みたいな」
笹久保「あと僕の方からも。別のインタヴューで、アルバムの制作上で難しかったり喧嘩になったりというような状況はありましたか?という質問をされたんですが、それは全然なくて。ただ実際に会わずに作る怖さはあって、それは制作上の怖さというよりも、実際会って気が合わなかったらどうしようという部分」
藤倉「そうだよね(笑)。ほんと昨日会ったばかりだもんね。いままで僕も、クラシックや現代音楽以外のジャンルの人と色々コラボレートしてきて、問題がなかったことなんてほとんどないですよ」
笹久保「いつも問題があるんですか(笑)?」
藤倉「ある特定の人なんかは、ものすごく難しい……うちの奥さんにも2度と仕事を引き受けるなと言われた経験もあります。今回に関しては、一回もなかった」
笹久保「意見が食い違ったことがないんですよね」
藤倉「音源を送っても〈いいですね〉〈最高ですね〉ばっかりで、むしろいつも〈いい〉としか言わない人なのかと」
笹久保「そう思われてしまったみたいですが、決してぼくはいつも〈いい〉と言うようなタイプではなくて。けっこう面倒くさいヤツですよ、僕は(笑)」
藤倉「もしくは他のアルバムの作業に没頭してて興味がないのかな、とか」
笹久保「藤倉さんが返してくれる音がすごく洗練されていて。お互いにああしろこうしろみたいなことはなかったですね」
藤倉「あと、このアルバムって統一性があまりないんです。色んな要素があるなかで、最後の方に南米色というものが出てくるんですが……この話は次の曲“プユ”が終わった後にでもしましょうか」
イルマ「ちなみに、〈プユ〉は空の〈雲〉という意味ですね」
リリースのスピード感、音質へのこだわり
藤倉「いまの演奏、アルバムと全然違ったよね?」
笹久保「いや、けっこう同じじゃないですか? あれ、違う曲弾いたかな(笑)?」
藤倉「これはこれでよかった」
笹久保「ここで残念ながら、また僕は調弦を……次の曲けっこう難しいんです」
藤倉「問題のやつだ。じゃあその間に別の話を。そうだ、このアルバムは1か月でさっとできちゃったんですよね」

杉田「話が始まったのが5月くらいでしょ? それで9月17日には出ちゃったから、だいたい4か月くらい」
藤倉「完成が6月1日だとして、3か月でソニーから出ちゃったという」
杉田「ソニーって大きな会社だけあって、ちょっと手間のかかるシステムはあるし、いろんなところを通過しなきゃいけないという部分もあるので、正直に言って僕も〈年内に出せればいいかな〉という感じではあったんです」
藤倉「リリースの話が決まった後、そうは言いつつ1年とか出なかったらいやだなと思う部分もあって。僕らはインディーですから、出そうと思えば明日にも出せるんですよ」
笹久保「作ったらすぐ出ないとイヤなんです!」
杉田「なんせ笹久保さんはこれまでのリリース枚数が22枚ですからね(笑)」
笹久保「出し過ぎですよね。もうすぐ死ぬんじゃないかという(笑)。でもその気持ちは分かりますよ」
藤倉「曲ができて、その後に契約とかあるんだろうけど、なんでそんな時間がかかるの?と」
笹久保「このプロジェクトで一番難しかったのは、ソニーの契約書を英語で読むことだったから」
藤倉「それなぜか僕の役目だったんですけど(笑)。18ページあったものを〈長すぎるので短くしてください〉とお願いして、8ページになった契約書を一所懸命読んで。普通だったら弁護士に頼むような作業だけど、なんせ制作費ゼロなので頼めない」
笹久保「1日1ページずつ読んだとか」
藤倉「ノルマを作ればできるかなと。ちょっとずつ進めるという、僕のそういう性格なんですが。あとこれも不思議なのが、杉田さんは契約書をFacebookで送ってくるんですよ(笑)。3人が見れるFacebooのチャットなので、意見交換などしつつ。でもすぐ話題が脱線しちゃってね」
笹久保「ちょっと気を抜くとこの2人で200回くらいやりとりしてて。見るのが面倒くさいと思いつつ一応はチェックするんですが、全然どうでもいいような……けど、たまにそのなかに重要なことが紛れていたりするので大変でした(笑)」
杉田「かなりの長文でしたよね」
藤倉「メールも使わずに、本当にFacebookだけで作品を作っちゃった。それで、日本ではソニーからCDとハイレゾ配信が決まったわけですが、24bit/96kHzのハイレゾに関しては僕たちが制作していた環境と同じクオリティーで聴けるということになります。このアルバムって、1回目は聴きやすいし〈いい雰囲気だな〉といった印象かもしれないけど、きちんとした環境で聴くと僕が細かくこだわった部分が聴こえてくると思うんです」
杉田「CDもBlu-spec CD2なのでいい音なんですが、でもやっぱりハイレゾは本当に素晴らしいですね」
藤倉「96kHzで作ったエレクトロニクスのサウンドを96kHzで聴くのはいいと思う。あと、世界配信は11月からミナベルでやります」
杉田「ちなみに、藤倉さんはイルカム(IRCAM)というフランスにある現代音楽の研究所の部屋を自由に使えるんですよね」
藤倉「オペラ(“Solaris”)が終わるまでは」
杉田「ということもあって、今回のアルバムではイルカムの素晴らしいソフトも使わせていただいて」
藤倉「僕のイルカムの作品のために開発されたソフトを使って作ったんです」
杉田「イルカムの部屋では常に後ろにプログラマーがいるんでしょ? こういうものを作ってくれと頼むとプログラムを組んでくれるんですよね」
藤倉「毎日9時から6時、月曜から金曜までずっといてくれて。それがだいたい10分の曲だったら制作期間の5週間くらい、オペラだったら2~3か月は付きっきり。そこで作られたソフトが僕のPCにも入っているから、それで音源を作ったり」
杉田「なるほど。ではそろそろ最後なので、お2人から今後の予定などあれば」
笹久保「作ろうと思えば2枚目の作品はできますよね」
藤倉「素材はけっこうあるからね」
笹久保「ぜひ出しましょうよ。またFacebookで会うのが楽しみだな(笑)」
藤倉「あ! そういえば南米色の話をしなかったけど、CDのブックレットに僕たちのFacebookのチャットがそのまま載っているので、そこに全部書いてあります。なぜ南米色が出てきたのか、意外な事実も載っているので、ぜひ読んでみてください」

この後、彼らはアルバムの最後に置かれた“ワイタ(花)”を演奏。笹久保の弾き出すクリスタルのようなハーモニクスと藤倉の流れるようなピアノが溶け合い、緊張感のなかにも美しさを湛えたサウンドスケープを現出させていた。笹久保が自身のアイデンティティーを追求するなかで〈秩父〉というローカルにこだわりを持ちながら、現代ならではの手法を用いつつ藤倉とグローバルな規模感で完成させた『マナヤチャナ』。その複雑な成り立ちを立体的に理解することができたイヴェントだったのではないだろうか。なお、藤倉はこの日のライヴ音源について〈このまま出しても良いクオリティ〉と語っており、共作の正式な続編も含めて、リリースを期待したいところだ。

































