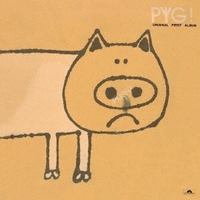多種多様なキャラクターを演じわける役者としての優れた表現力や独特な佇まいが、ひとたびマイクを握れば音楽の世界でも活きる俳優たち――。専業のアーティストとはまた一味違った趣に溢れる彼らの歌が、時にその時代を象徴する大ヒットや長く聴き継がれる名曲となることは少なくありません。そんな役者ならではの歌の魅力に迫るべくスタートした連載〈うたうたう俳優〉。音楽ライターにして無類のシネフィルである桑原シローが、毎回、大御所から若手まで〈うたうたう俳優〉を深く掘り下げていきます。
第8回は、初のソロアルバム『惚れた』のリリースから今年で50周年を迎える萩原健一をピックアップ。俳優、歌手として熱狂的に支持され続ける唯一無二のカリスマ〈ショーケン〉の音楽キャリアを振り返ります。 *Mikiki編集部
ザ・テンプターズで開花させたボーカリストとしての魅力
ショーケンがこの世を去ってからもうじき6年になる。今日までの間、ボーカリストとして、ロックミュージシャンとしての彼の功績をもっと積極的に評価すべきだ、という声はそこかしこでしょっちゅう立ち昇っていた気がする。果たしてそれはちゃんと実行されたのであろうか?という自問自答を含めて、本稿では彼が残した楽曲や作品をざっくばらんに振り返ってみたいと思う。
60年代の後半、ザ・タイガースと人気を二分したGSグループ、ザ・テンプターズの一員として始まった彼のキャリア。リーダーの松崎由治が作詞作曲した“神様お願い!”(1968年)、最大のヒット曲となった“エメラルドの伝説”(共に1968年)などが代表作として頻繁に語られる彼らだが、そもそもはヤードバーズ、ローリング・ストーンズ、アニマルズのようなブリティッシュ系のブルースロックをプレイしたいという動機がバンドの出発点であり、レコーディングもすべて自前の演奏でまかなうという高い意識は多くのGSバンドと一線を画すポイントでもあった。
そんなグループの中心で、狂おしい恋に身をやつす若者たちの心情表現と真摯に取り組んでいた10代のショーケン。人気作曲家の村井邦彦が手掛けた“エメラルドの伝説”のような少女趣味的な世界において披露されたセンシティブな感性が滲む歌唱も特徴的だったが、バンドの出自とも言うべき不良っぽさが際立つようなロック、R&B系にアプローチしたときこそ魅力が大きく開花していたのは間違いない。
もっとも顕著な例が、ロックとブルースのメッカに赴いて作られたアルバム『ザ・テンプターズ・イン・メンフィス』(1969年)でのパフォーマンスだろう。日本人アーティストで初めてメンフィスでのレコーディングを敢行した本作では、アレサ・フランクリンの数々の傑作で名サウンドを轟かせたディキシー・フライヤーズ、メンフィス・ホーンズの面々がバックを担当。サザンソウルの巨人、ジェイムス・カーのカバー“Everybody Needs Somebody”などに果敢にチャレンジしているのだが、本格的な南部サウンドと正面から対峙し、歌声にはいつになく太い響き、大らかなヴァイブが宿る結果となっている。
まぁ、超ディープなオリジナルと比べてしまうと、歌の端々に〈坊や〉感が目立ってしまうのは仕方がなかろう。ただここで見せる負けん気にも似たアグレッシブさには大いにそそられるものがあって、歌の背後に見え隠れする青白い炎には、メンフィスから登場したブルーアイドソウルバンド、ボックス・トップスのアレックス・チルトンのことをふと思い出したりしてしまう。
ショーケン初のソロアルバムとなるプランも用意されていたこの画期的な作品は、発売当時はさほど話題にならなかったが、果敢な挑戦が実を結んだ重要作品だという評価が現在ではしっかり確定している。その他の収録曲では、バネのあるショーケンの歌声が光るノーザンソウル調の“世界は僕の両手に”が和モノ愛好家からすこぶる人気が高いことも記しておきたい。
沢田研二らと組んだスーパーグループ〈PYG〉
70年代に入ってGSブームが終焉を迎え、それと交差するようにニューロックの時代がスタートする。そしてテンプターズの解散後にショーケンが合流したのが、当時スーパーグループと呼ばれたPYGだった。メンバーは、タイガースの沢田研二と岸部修三(現:岸部一徳)、ザ・スパイダースの井上堯之と大野克夫、そしてテンプターズの大口広司とショーケンというまさにスペシャルなラインナップ。彼らがここでやりたかったことを端的にまとめると、混沌とした60年代との決別だとひとまず説明することができよう。
例えば、シングルに選ばれた“花・太陽・雨”(1971年)に象徴されるような鎮静ムード漂うサウンドからは、たぶん60年代産ロックに感じられた、ただならぬ高揚感から遠く離れた印象を抱くはずだ。当然ながらショーケンもそんな雰囲気にどっぷり呑み込まれていて、〈萩原健一+PYG〉名義のサードシングル“もどらない日々”(1971年)などで何とも言えない倦怠感を振りまいているわけだが、これはこれで貴重というか、時代の転換期にしか生まれ得なかった特異なフィーリングとして興味深く受け止めることが可能であると言っておきたい。
そんなPYGは宿命的に『PYG!』(1971年)という1枚のオリジナルアルバムを残しただけで分裂してしまう(ちょうどショーケンは1972年7月から始まったドラマ「太陽にほえろ!」にマカロニ役で出演、役者として人気街道を驀進中だった)。