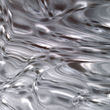ドラマーは現在のジャズでたいそう重要な位置にいるのはどなたにも異論はありますまい。クリス・デイヴ、ブライアン・ブレイド、ジャマイア・ウィリアムスしかり、リチャード・スペイヴンなど、当初R&B~ヒップホップといったモダン・ブラック・ミュージックの換骨奪胎に心血を注いだポスト・グラスパーの潮流はすでに、掘り返すにはいささか生々しかったはずの90年代の臭いの拭えない、たとえばドラムンベースなどに食指をのばしてみたらかなり香しかったのである。彼らによって時代は底から変わりつつある。なかでもマーク・ジュリアナはユダヤ系ジャズの急先鋒であるアヴィシャイ・コーエンのトリオの屋台骨として名を売ったのをきっかけに、ブラッド・メルドーとのMehlianaやナウ・ヴァーサス・ナウなどでテクニックの革新性だけでなく、それをアンサンブルにいかに組み込むか、センスというと掴みにくくなってしまう、それでもやはり彼一流のセンスというしかないもので群雄割拠状態のドラマーたちのなかでも頭ひとつ抜けていた。抽象的な音楽言語で物語を語る術があった、だけでなく色もある。
このたびみずからレーベル、ビート・ミュージック・プロダクションズをたちあげ2作同時リリースとなる『Beat Music: The Los Angeles Improvisation』『My Life Starts Now』でそれはいっそう明らかになっている。

前者は一見、J・ディラを本歌どりしたビートアルバムで30曲の曲というよりトラックと呼んだほうがしっくりくるスケッチ集に似たつくりだが、それでもそれぞれに聴きどころはいくらでもある。
後者と並べてみるとこの2作はつくり方を含め、個人的な密室的なところ、つまり偽らざる彼の色があり、その淡色のトーンは、親交厚いミシェル・ンデゲオチェロやグレッチェン・パーラトが参加しジャズはもちろんレゲエやヒップホップや即興を仄めかしたとしても、歴史や記号、音楽そのものの重さとまで切れた、その漂白(泊)ぶりこそ“いま”であるといいたがっているように思える。