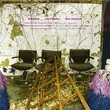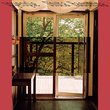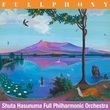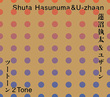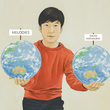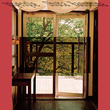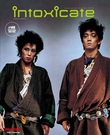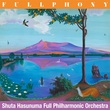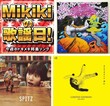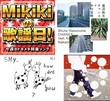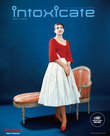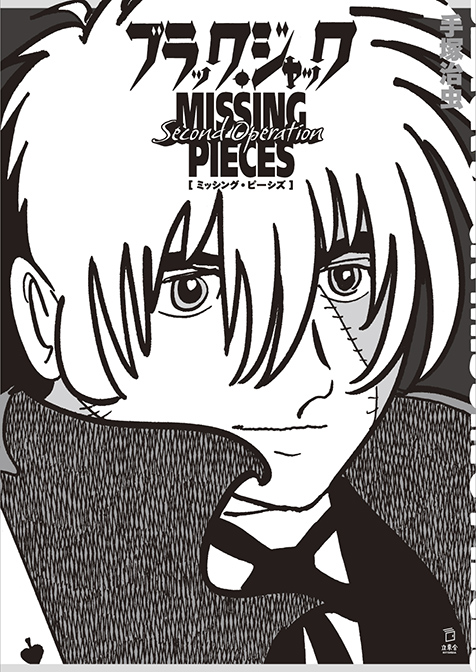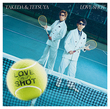もしあなたがふたりの名前にゴリゴリな音を想像したのだとしたら、あまりに自由で軽やかなサウンドに両の耳を躱(かわ)されてしまうかもしれない。魂を操る司祭の異名をとる灰野敬二と、音の多義性を多義的なまま作品に昇華する音楽家、蓮沼執太との初のコラボレーションは2017年に端を発し、2021年にいったんスタジオでかたちとなったが、その後も両者は音による会話を絶やすことはなかった。
本稿は2025年8月26日火曜日の取材によるもの。対談は本作の録音もおこなったという川越のスタジオに立ち寄り、灰野さんのお宅にお邪魔して収録した。5時間を超える対話は多岐にわたったが、こうして原稿をまとめるにあたりふりかえってみると、怒りや憎しみや悲しみのような世に蔓延する輪郭のはっきりした感情に縁取られていないことに気づいた。風通しがいいのである。というよりむしろ『う た』と題したこの作品が風そのものといえばいいか。窓を開けてご一読ください。
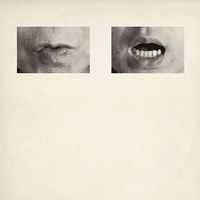
〈パラドックス〉として日本語で歌う
──まず、この今回のプロジェクトの成り立ちからお話しいただかなければなりません。
蓮沼執太「とあるイベントが2017年にありまして、それが当日まで誰と演奏するかわからないというものだったんですね。各自もち時間は5分で即興といわれる形式です。そのときにステージ上で〈はじめまして〉という感じでした」
──灰野さんは蓮沼さんのことをごぞんじでしたか。
灰野敬二「ごめんなさい」
蓮沼「ごぞんじでいらっしゃるはずがないですよ。そのとき、灰野さんは声で、僕はBuchla(シンセサイザー)を演奏しました」
──灰野さんは音楽を通して蓮沼さんと出会い、どう思われました。
灰野「やりやすいと思った。そうじゃなきゃこの流れ、ないよ。その日僕は“君が代”を歌おうと思っていて、なるべく自然に歌いたかったから、歌の隙間にお星さまのように蓮沼くんの音がピカッ、ピピピッ、パッ──というような感じでなって、ああやりやすい、と思った」
蓮沼「僕は灰野さんが“君が代”を歌っていると気づくのに1分半くらいかかりました。これはなんだ、と自分が音を出すよりまずは聴いたんです。持参したBuchlaはランダムに音が出るように設定してあって、鍵盤のようにつかえもするので、最初は音楽的に、隙間を狙っていたんですが、だんだんとそれが絡み合っていく空気をやりながら感じて、楽しいなと思いました」
──灰野さんなので、正調というよりは灰野さんの流儀の“君が代”だったと思いますが、そもそもなぜ“君が代”だったのでしょう。
灰野「歌いたいから。それ以外になにか理由がいる? ひょっとすると理由に至ることかもしれないけど、以前、ハーディ・ロックス(HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS)というバンドか、その前身のハーディ・ソウルで“君が代”をやっているの。ただ両方とも英語で歌うというコンセプトだから、日本の演歌も“君が代”も英語で歌う。わざわざ“君が代”が成立した10世紀初頭の古英語で歌ったんだけどね。
蓮沼くんとやったときは、こういう面倒くさい言葉はつかいたくないけど、〈パラドックス〉として今回は日本語にしようか、ということだよね。やっぱりね、ほかとちがうことをやんないとつまんない。〈即興〉といいながら最後は(枠に)収まりたがる考え方に一矢報いるためにも、おそろしく保守的なことをやろうかな、ということだよね」
──メタフィジックな観点だったと。
灰野「もちろんだよ。ジミヘンが米国の国歌をギターで弾いて、ある時期までは右翼がよろこんだけど、いまは左翼もよろこんでいるじゃない」