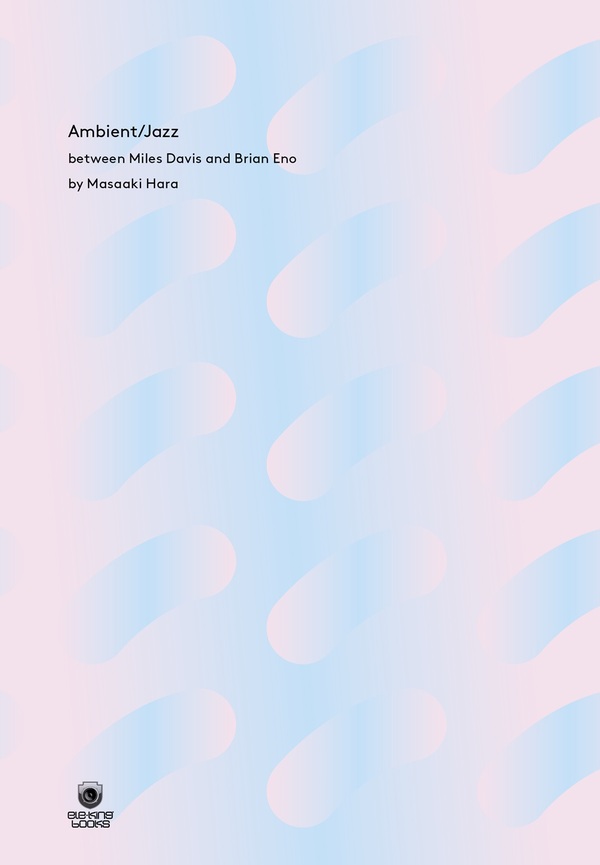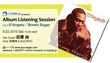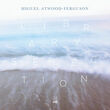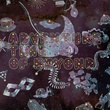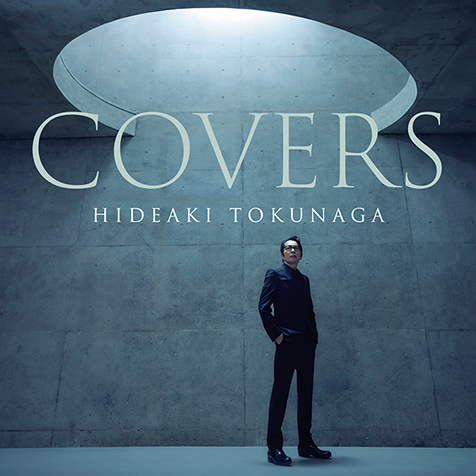マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノのあいだ、とその先へ
〈アンビエント〉という概念が、その名称(それはもちろん、形容詞を固有名化したものだけれど)とともに、音楽史に登場したのは1978年、ブライアン・イーノによる『Ambient 1: Music For Airports』によってである。それは、イーノがフリップ&イーノや、自身のソロ『Discreet Music』などをへて辿り着いた、新しい音楽のあり方だった。アンビエントはその後、ある種のスタイルを表すものとなり、新しい音楽を思考するためのひとつの指針となった。アンビエントというあり方が、さまざまな音楽ジャンルに導入されていくことになる。ジャズもそのひとつだった。
この本は、マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノという、二人の出自も背景も活動時期も異なる (がゆえに、直接には出会い損ねた)音楽家と非音楽家が作り出した音楽から、アンビエントという概念を抽出する。それは、『In A Silent Way』がその始まりと位置付られるように、ジャズが録音という手法を導入することで生まれた新しい感覚だった。イーノは、『Another Green World』以降、『Before And After Science』や『Music For Films』などのソロ作において、アブストラクトでジャズ的なスケッチ風楽曲を多く制作している。原は、『Music For Airports』について、〈モーダルな響きがあることによって聴くことを促す何かがある〉とアンビエントの性質を分析する。それは、あらためてアンビエントとは何であったのかを問い直すものでもある。

書名は〈マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる〉とあるが、英語タイトルは〈between Miles Davis and Brian Eno〉とあり、両者の〈あいだ〉であることが強調されていることは、この本がどのような本であるのかを表すものとなるだろう(本書〈intro〉でふれられているとおり)。もちろん、本書の射程は、たんに〈/〉で分たれた、ジャズとアンビエントの出会いにとどまるものではなく、さまざま接続され得る、〈/〉が隔てる両者が想起させる、可能性としての〈あいだ〉から生み出される新しいジャンルにこそあるだろう。それは、本書の後半で展開される、ECMや菊地雅章、そして日本の環境音楽であり、清水靖晃や高田みどりといった音楽家である。そして、原が自身で主宰するレーベルringsから新しいジャズのかたちを紹介し続けていることによっても実践されている