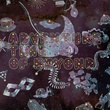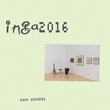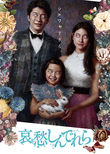けっしてキャリアの短い人ではないのに、ここ最近、一見それぞれは無関係に見えるいくつかの興味深い場面で、原雅明の名前を目にする機会があった。あるときは〈Redbull Music Academy Tokyo 2014〉での中原昌也や鈴木勲らのインタヴュアー、あるいは冨田勲によるレクチャーの優れた導き手として、またあるときは、話題のムック「Jazz The New Chapter」の監修者・柳樂光隆が挙げる同著のインスピレーションの担い手の一人として。
近年では、世界中にファンを持つLAのインターネット・ラジオ、dublabの日本ブランチ〈dublab.jp〉の運営者としても意欲的な活動を展開する原氏が今秋、自ら〈レーベルと呼ぶにはややしっくりこない〉と語るringsをスタートさせた。
いま新たなアクションを起こそうとしている原雅明は何を考え、その自由なバランス感覚はどこに由来するのか。普段は、主役である音楽を紹介する立場に徹することの多い彼にじっくりと話をうかがうべく、dublab.jpのプログラムを定期的に配信している中目黒のカフェ・Malmoまで足を運んだ。
ringsとは何か
――rings発足時のステイトメントに、「ringsをレーベルと言うことに多少しっくりこない気持ちも実はあります」という言葉があったのですが、そのような表現を使った理由も含めて、改めてringsとはどういったものなのかを教えてください。
「いままでdisques cordeというレーベルを運営してきて、その前にもsoup-diskというレーベルを初期の頃は虹釜太郎くんと一緒にやっていたのですが、その後はずっと一人で続けてきたんです。小さなレーベルとしてインディーで活動してきたんですが、この数年はリリースしたい作品の予定は立てていたものの、なかなか続けていくのが厳しいな、という実感があって」
――それは経済的な部分も含めてですか?
「経済的な面もそうですが、自分のなかでしっくりくるか否かという部分で、どうもしっくりこない。そこで何がしっくりこないのかを改めて自分自身で考えてみたんです。
いまレーベルをしっかりやっていくことって難しいじゃないですか。誰もが簡単に〈レーベルです〉と名乗ることができる状況だから、レーベルの数自体はたくさんあると思うんです。でも、インディーから大きくなったレーベルの数はすごく限られていて、メジャーなレーベルも企業の統合などで数が少なくなってきている。昔はレーベル買いだったり、レーベルそのものに興味を持つような状況も多々あったと思いますが、いまはレーベルより先にアーティストの影響力の方が前に出てきてしまうことが多いように感じています」
――レーベルの持つ影響力や意味合いが昔とは変わったということですか?
「レーベルのやることが、アーティストのマネージメントに近いものになってきている。端的に言うと、CDやレコードが売れないから、マネージメントまで総合的にやることでレーベルを維持していこうという発想だと思うのですが、そういった状況に傾いてきているのを感じながら、そこで自分がレーベルをやっていくのはしんどいな、しっくりこないな、という気持ちがあったんです。
ただ、リリースする予定の作品はたくさんあって、アーティストから音源までもらっているものもあったのですが、僕が忙しいせいでなかなか出せないという状況で。だから正直、ここ数年は以前から貯めていたものを、なんとかリリースしていったというのが実状だったりします」
――お一人で運営されていることもあって、なかなか動けなかったんですね。
「ノブくん(sauce81/N’gaho Ta’quia)の作品(N’gaho Ta’quia『In The Pocket』)が最後というか。あれも1年以上前に音はもらっていたし、中原くん(中原昌也)にも怒られてばっかりで(笑)」
――中原さんのアルバム(Hair Stylistics『Dynamic Hate』)は、企画としてもすごく面白かったです。中原さんがビートもののアルバムを作るという。
「あれも1年くらい前。僕がなかなか出さないから、中原くんから〈ほかに持っていきますよ!〉とか言われたけど(笑)」
――(笑)。先ほど名前の挙がったsoup-diskやdisques cordeを始められた当時と2014年の現在では、インターネットの発達による音楽にまつわるさまざまなインフラの普及や、一方では旧来のビジネス・モデルがうまく機能しなくなったりなど、音楽を巡る状況に大きな変化があったと思うのですが、当時と現在とでは〈レーベルを運営すること〉に対する意識はどのように変わりましたか?
「レーベルを運営していくことがしっくりこないという感覚はずっとあったんですが、ちょうどdublab.jpを始めたのが1年以上前で、それを経験したことが意識の変化のうえでは大きかった気がします。
dublab.jpでは、何人かのスタッフと一緒になって何かしら形にしていくような活動を基本的には非営利で行っているのですが、組織を維持していく最低限のお金は確保していく必要があって。いろんな工夫をしていくなかで、自分がレーベルでやっていることと、どうしても比較する場面が多かったんです。そうすると、dublab.jpで行っている活動の方がいまの時代にマッチしているなと感じ始めて。もちろん、一人でレーベルをやっているときもいろんな人の協力は得て進めてきたのですが、dublabの場合はもっと音楽をシェアしたり、共有して何かを進めるという意識のもとで動いているんですね。そういった形で音楽を紹介することの面白さを、実際に自分たちでdublab.jpを動かしてみて感じました。
〈音楽を紹介する〉という面で、レーベル的なものを同じようなスタンスでできたら面白いなと感じたことが、ringsを始めることになった一つの理由かもしれません」