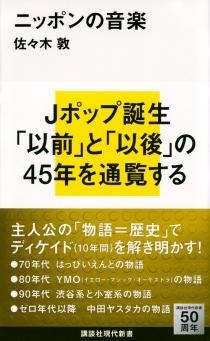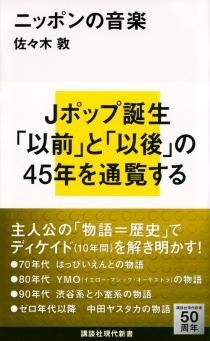この二冊は、日本の(ニッポンの)ポピュラー音楽と教育音楽についての本である。後者は日本に限った話ではないかもしれないが、二冊に共通するのは内と外という考え方だと思う。
佐々木敦『ニッポンの音楽』は、「Jポップの形成、あるいは、いかにしてよそ(外)と同化しようとしつつ、ここ(内)に向けての音楽が作られるようになったか」というべき本だ。それは、日本におけるポップスの受容史および形成史であり、いかにして「Jポップ」なるジャンルが形成されたのかについて、日本において、ある意味特殊な音楽状況が形成されるにいたる経緯を考察した本でもある。
そこで、著者は日本におけるいわゆる「日本語ロック」を確立したとされる、はっぴいえんどをその嚆矢として考える。以降、70年代から10年ごとの事象を、幾人かのキーパーソンとなる音楽家および周辺状況とともに論じていく。それは、はっぴいえんど、YMO、の系譜からはじまり、80年代末のいわゆる「Jポップ」の誕生を転回点に、渋谷系、小室哲哉、中田ヤスタカと受け継がれる系譜である。キーワードとなるのは「リスナー型ミュージシャン」ということである。
ニッポンの(ポピュラー音楽の)歴史とは、遠くにあった理想の外部をいかに内在化していくかの歴史である。理想あるいは模範のようなアメリカあるいはイギリスのロックがあり、そこからの距離感、遠さをひっくりかえして、外部をより身近な共感できる内部へと取り込んで形成されたものであろう(しかし、失敗の連続として)。ロックをするためには英語で、あちらへ飛び込んでいかなければならなかった時代から、ニッポンの中にロックを取り入れる時代。その中ではっぴいえんどとフリッパーズ・ギターが重ね合わされる。そして、つねに外を参照軸としてきたニッポンの音楽が、参照されてきた外部が消失しつつ、外を完全に内へ対象化し終え、ひとつの終着点としての現在にいたるというサイクルをひとつの歴史=物語として著している。
大友良英『学校で教えてくれない音楽』では、音楽のより根本的な問題をあつかっている。といってもそんなむずかしい話ではない。それは、「学校で教わる音楽」というものに対するちょっとした懐疑である。学校教育では、音楽とはこういうものだという既成概念を最初から与えられてしまう。そして、大友自身、音楽の時間が苦手だったというように、それ自身が音楽というもののハードルを上げてしまっているという問題である。そこには、音楽のための前提があり、基準があり、集団における関係があり、とさまざまな制約がある。そこでも意識されるのが、自分(内)と他者(外)ということになる。音楽の授業がいやになるのは、このポイントが大きい。人より歌がヘタであるとか、人前で大きな声で歌うのがはずかしい、というのも結局それでそこで尻込みしてしまう人は多いのだろう(私もそういうクチでした)。
しかし、そうした約束事をもっと原初的なところまで引き戻して、より自発的で開放的なものに変えられれば、音楽をより楽しむことができるのではないか。気持ちでは音楽したいのに、音楽によってそれを阻まれてしまうのはもったいない。実際、ここで大友の授業(この本は講義録なのです)を受けている参加者たちは、音を出し、そのことが(自分たちの)音楽を作り出しているということを、まさに楽しんでいる様子である。本書の半分を割いて紹介される「音遊びの会」から始まる障がい者との試みも、「既に作られた音楽」が演奏できるようになるプロセスなのではなく、むしろ音楽の発生にまでたちかえり、あたらしい「音楽」を創造するような、より根源的なことなのである。それはあらゆるイディオムから逃れようとする即興演奏とたしかに類似するのかもしれない。それは、互いを認め合い、内も外もない関係性をつくりながらその場に生起する、なにものでもない「音楽」そのもののための試行なのである。