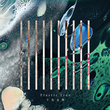四者四様のスタイルを持ち込むことでひとつの作品を作り上げる。そんな〈バンドという生き物〉の現在を、形を損なうことなく留め置いたもの。目の前に出現した剥製たちは、かつてないほどの〈4人の音〉を鳴らしていて……
この時期のPlastic Tree
あたりまえの話なのだが、〈この4人はバンドなのだ〉ということを改めて、かつ強烈に思い知った作品――それが、フル作としては約3年ぶりとなったPlalstic Treeのニュー・アルバム『剥製』だ。アレンジは全員で行っているとはいえ、3枚の先行シングル“マイム”“スロウ”“落花”以外の書き下ろし曲は、ほぼすべて単独のメンバーが作詞/作曲の両方を担うこととなった本作。つまりは、個々の持ち味が濃厚に表出したナンバーのみで構成されているのだが、全12曲を通してのトータリティーはこれまで以上。これはいったいどういうことだろう?
「今回は特にコンセプトを設けないで作りはじめたんですけど、統一感があるっていうのは、作った時期が一緒だからっていうのもあるんですかね? 曲調はバラバラにしろ、〈Plastic Treeの音楽はこういうもの〉みたいなのにそれぞれが向かっていたというか」(長谷川正、ベース)。
「今作のなかでいちばん早く出来た曲が“マイム”なんですけど、その頃から次のアルバムを見据えて曲を作ったり、アイデアをバンドに持ち込んだり、そういうことを各々がやってたと思うんですよね。とにかく、この4人のメンバーでのベストの作品を作ろうと。そうすれば、Plastic Treeの現時点の代表作になるだろうし、アルバムってそういうものだと思うので。だから、“マイム”以降の長いタームで見た〈この時期のPlastic Tree〉が、この『剥製』というアルバムなんです」(有村竜太朗、ヴォーカル)。
四者四様の作風を突き詰め、それを薄めることなくバンドに取り込むことで完成した楽曲群。そのオープニングを華やかに演出するのは、ナカヤマアキラ(ギター)が手掛けた“フラスコ”だ。開放的にドライヴするバンド・サウンドに光の乱反射のようなエレクトロニクスを重ねた同曲は、シチュエーションが鮮明に浮かぶものの、唐突な設定が敷かれた詞世界も彼の十八番。加えて狂騒の電子ロック“スラッシングパンプキン・デスマーチ”ではそうした特性がより前面に出ており、字面だけで想像できるか不明だが、まさに表題通りに進むストーリーが途轍もなくエキセントリックで……。
「その感想はありがたいですね(笑)。そういうふうに言われたり、思われたりするために、この歌詞にしたようなものですから。4人それぞれ、得意な分野に特化した曲を書いてみないかい?っていう期間があったので、よく〈らしい曲ですね〉って言われるようなところを意識して書いてみました」(ナカヤマ)。
続く“ハシエンダ”“インソムニアブルース”の2曲を手掛けたのは長谷川。パンク経由の豪快さを持つ前者、往時のインディー・ダンス勢を想起させる後者とテイストは違えど、強引なほどのグルーヴ感に自身のルーツを投影している。
「言ってしまえば、最近、曲を作るときはそういうのばっかりなんですよね。もう自分のルーツにあるものを割と素直に出してしまおう、みたいなところがあって。“ハシエンダ”はちょっと暴力的なグルーヴというか、そういう曲があってもいいんじゃないかな?と思って持ってきました。タイトルは自分が憧れてる世界観の象徴というか……もちろん実際に行ったことはないんですけど、(ハシエンダを運営していた)ファクトリーっていうレーベルには自分の好きな作品が多いんで、そういう音楽がいつも流れてる場所にパーティー・ピープルが日夜集まって……それが自分としては、理想のコミュニティーっていうイメージなんですよね。そういうところに現実逃避するみたいな感じです。“インソムニアブルース”もPlastic Treeを結成したときからずっとやってみたいなって、何度か作ってきたタイプの曲で。結構前からあったんですけど、ここでアルバムに入れようと思って、みんなにいろいろとアイデアをもらって完成しました」(長谷川)。
なお、起伏を抑えたメロディーに揺らぐギター・サウンドが映える“float”の作曲者も長谷川。そこに詞を乗せ、センティメンタリズム全開の言葉が瑞々しく疾走する“告白”の詞/曲も担当したのは佐藤ケンケン(ドラムス)だ。
「“float”は、音のふわふわ感を言語化した感じ……ですかね。“告白”も含めてですけど、特に歌詞は、〈らしさ〉みたいなものをもっと出したいなと思ってました。まあ、その〈らしさ〉がなんなのかは自分でもわかってないんですけど、〈ロマンティック〉みたいなことはいつも言っていただけるので、そう思うようにしてます(笑)」(佐藤)。




生き物だけど止まってる
そして、ラストの有村が本作で唯一披露した新曲は“剥製”。時間の循環をゆるりと綴った直前の“スロウ”からさらに速度を落とし、ついには時を止める瞬間に――沈み込むような〈終わりのとき〉に目を向けるメランコリックな逸品だ。
「曲はもう揃ってたし、今回、俺の曲はなくてもいいのかなと思ってたんですよね。アルバムで俺が担うところって、これまでは結構、弾き語っちゃうものが多かったんですけど、このタイミングでは〈バンド〉っていう方法論でキッチリやれる曲じゃないと嫌だなと思って。で、そういう曲を自分では見つけられなかった。それが、ギリギリでこの曲の前段階のデモを持って行ったら、正君が〈この曲やってみたらいいんじゃない?〉って言ってくれたんで、それなら考えてみようかなってことで形になった曲ですね。“剥製”はアルバムのタイトルにもなってますけど、バンドがもともと持ってる世界観とか、バンドそのものだとか、自分らが詞曲を作る意味とかは、いろいろ考えると剥製のようにも思えるなって。といっても、〈これがいいんじゃないかな?〉〈いいと思うよ〉みたいな正君との会話で、なんとなく決めたぐらいの感覚なんですけど。ただ、不思議なのは、そういう曲ってSEを作ったりとか、何かしら他にも発展性があるんですよね。出来上がった曲の集合体の、ちょうどまとめ役になるというか……」(有村)。
〈バンドであることを求めた楽曲〉のパーツをモチーフにしたそのSEは、“○生物”“●静物”と題され、本作のプロローグとエピローグ的な位置に配されている。「生き物だけど止まっちゃってるな、とか(笑)、そういう表現ができればいいなあと思って」と有村は語っていたが、〈生〉と〈死〉とも受け取れるこの2曲と、その狭間に陳列された10曲の集合体は、言わば4人組バンドとしてのPlastic Treeとその現在を、形を損なうことなく留め置いたもの。剥製化された2015年の彼らの音楽は、ときが経っても風化することなく、生き生きとした輝きを放ち続けるのだろう。まるで、プラスチックの樹がそうであるように。