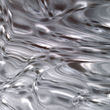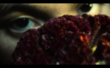昨年は自身のレーベル=Thursday Clubからシングル“radiotooth”を発表するなど飛躍の1年を送り、Mikikiブログ〈ヤセイの洋楽ハンティング〉も好評なYasei Collectiveが、待望のニュー・アルバム『Lights』を4月6日にリリースすることが決定! Mikikiではそのカウントダウン特集として、ヤセイのルーツであるビッグな海外アーティストとの対談企画を前後編でお届けします。
まず前編では、デヴィッド・ボウイの新作(にして遺作となった)『★』への参加で時の人となり、今年1月初めに自身のジャズ・クァルテットを率いて来日したマーク・ジュリアナが登場! ヤセイのリーダー・松下マサナオにとっても、今回の対談は念願だったとのこと。プレイヤーとしての哲学を熱く語るマークと、日本でいち早くマークの才能に注目していた松下のやり取りは、これからミュージシャンを志す人にも大きなヒントを与えることでしょう。さらにマークは、ボウイ『★』レコーディング時のエピソードも披露。日米の最重要ドラマーが共振し合った、熱い語りっぷりをご堪能ください! *Mikiki編集部
※編注・こちらの取材は2016年1月5日に行われました。
★ブログ〈ヤセイの洋楽ハンティング〉より「唯一無二なスタイルを確立したドラマー、マーク・ジュリアナの観ておくべき映像たち」はこちら
★【ヤセイの同業ハンティング】Vol.2 Yasei Collective松下マサナオ×クラムボン伊藤大助のドラム対談はこちら
★来日前に行ったマーク・ジュリアナのインタヴュー記事はこちら
★デヴィッド・ボウイ『★』特集はこちら
機材から演奏スタイルまで、ドラマーとしての矜持
――松下くんはマーク・ジュリアナの大ファンで、すごく影響を受けてるんです。
マーク・ジュリアナ「グレイト!」
――昨日(1月4日)ライヴを観たんですけど、マークが日本でアコースティックのライヴをやるのは初めてということもあって、ファンも驚いていましたね。今回あなたが使用したドラム・セットの特徴を教えてください。
マーク「サイズなんかのスペックのことだよね。自分の好きなジャズ・ミュージシャンから影響を受けて、ああいうセッティングにしているんだ。18インチのベース・ドラムと12インチのタム、14インチのフロア・タムと14インチのスネアを使っているよ。チューニングはアート・ブレイキーやロイ・ヘインズ、トニー・ウィリアムズといった60年代のジャズ・アーティストと似たものにしている。今回(クァルテットで)やろうとしていたのは、そういったセッティングのなかで自分の音楽をどう表現するかの挑戦だったんだ」
松下マサナオ「シンバルについて訊きたいんですけど、あれはプロトタイプを使っているんですか?」
マーク「そう、どっちもセイビアン(シンバル・メーカー)の21インチのプロトタイプだよ」
松下「あれは本当にいいシンバルですね。ジャジーだし、デフィニション(音の解像度)もしっかりある。ハイハットは13インチ?」
マーク「14インチだね。どれもすごく薄いものを使っているんだ」


――ビート・ミュージック名義でのドラムと、今回のようなアコースティック編成のドラムとでは叩き方も違っているのでしょうか?
マーク「確かに違ってくるね。自分の出したい音によって、叩くときのテクニックが変わってくるから。チューニングを低くしたものは、静かに叩くと音があまり鳴らないからきっちり叩かないといけないんだけど、今回はチューニングを高くしているので静かに叩いてもちゃんと音が出るようになっている。でも、心構えはどちらも同じだね。ドラムスローンに座ったら、その音楽に相応しい音を正直に鳴らそうとするだけさ。ただ、物理的というか、フィジカルな面ではちょっと違った叩き方になっているのかな」
――そのフィジカルな違いを言葉で説明するとすれば?
マーク「叩く力自体が違うね。静かに打っても音が出るということは、冒険する枠が広がるということなんだよ。逆にエネルギーを使って叩くときは、静かに叩くこと自体が難しくなるし」
――松下くんは、セッティングでもマークにすごく影響を受けてますよね。
松下「僕は最近また22、24インチのような大きいサイズのライド・シンバルをよく使ってます。クラッシュとしても使うのとバンド・サウンドとの兼ね合いもあって、去年は20インチをよく使っていたんですけど、今年のマイネル(シンバル・メーカー)との契約を機にガラッとキャラクターの違うモノに替えたところです。あとはマークが狙っているものより、もう少し〈ダークなトニー・ウィリアムズ〉みたいな音が出せそうな24インチも、いまドイツから(日本に)向かっているところです。ドラマーによって求めるものは違うんですよね。僕はすごくマークの影響を受けてます。いままでに影響を受けた過去のレジェンドたちと同じくらいに。ただいつも大事にしているのは、彼らのサウンドをただ再現したいわけじゃなくて、アイデアとしてもらって、それをバンドや自分の音楽に反映させるってことなんです」
マーク「グレイト!」
――こういうセッティングって、どういうところからアイデアを得ているんですか?
マーク「セッティングについては、まずはどういう音を最終的に出したいか、どんな音楽を演奏したいかで決めているね。機材を先に考えるのではなくて、まずは自分が表現したいサウンドをイメージして、そのサウンドを出すためにどういった楽器や機材が相応しいのかを考えるんだ。僕の意見では、音楽ありきで考えて、それを受けて機材を調整することが大事だね。残念なことに機材ありきになってしまう人もいるけれど、そうすると機材に音楽が付いていくような形になってしまうしさ。例えば、ビート・ミュージックのときはエレクトロニック・ミュージック寄りの音だから、それを再現するにはどうしたらいいのかをまず考える。とにかく、音楽の〈表の面〉を常に念頭に置いているよ」
――それはアコースティックの場合でも同じですか?
マーク「そう。太鼓類はサイズがとにかく大事。自分がその音楽で普段使っているのと同じサイズのものであれば問題ない。だからサイズだけは自分が希望するものをいつも準備してもらっている。そうすることで、そのときの音楽に相応しいサウンドが出せるから」
――(日本を含めた)海外のライヴでも、ドラム・セットを一式持ってきているんですか?
マーク「いや、自分のものはシンバルだけだね。NYでも大抵の会場にはドラムセットが準備されているから、自分のセットを持っていくことはほとんどない。レコーディングの場合は持っていくことがあるけど」
松下「マークにとって、一番重要なポジションにあるのはシンバル?」
マーク「というよりは、〈もっとも個性がある〉ものかな。どのシンバルもそれぞれ違っていて、まったく同じものなんて存在しない。プロトタイプについてはたしかに一点ものだけど、既存の商品モデルで同じタイプのものでも重量感が違ったり、シンバルってそれぞれが個性を持っているんだよね。それは調整でどうにかなるものではない。それがドラムであれば、テープを貼ったりクッションをかませて調整することはできるんだけど」
松下「確かにシンバルは絶対持っていきますね。僕はペダルも持ち込むことが多いです。日本のライヴハウスの場合、ペダルが死んでいることが多いので。地方でしかも個人で移動の場合は、ヘッドだけ持って行って、本番までに時間があるときは変えたりしていますね」
――へ~、なるほど。
松下「あとマークのプレイについては、人によっては最初の頃に(彼の音だけを聴いて)ツイン・ペダルで演奏しているんだと勘違いしていたんですよ。マークのフット・テクニックは時代を変えたところがありますね。ハイハットとキックの連打でエイフェックス・ツインやスクエアプッシャーみたいなビートを人力で叩くアレは、日本人ではたぶん僕が最初にマークから〈借りた〉ドラマーだと思います(笑)。黒人のドラマーだったらソニー・ペイン、トニー・ウィリアムズときて、デニス・チェンバース、クリス・デイヴという大まかな流れがあると思うんですけど、マークは白人のそういった系譜のなかで本当に重要な人物です」
――そうですよね。
松下「どれだけこの人がすごいのか、僕は10年以上見てきているけど、日本のオーディエンスはようやくそれに気付きはじめている。デヴィッド・ボウイの作品に参加したのも大きいんだろうけど。そこで僕が訊きたいのは、マークの音楽人生のなかで、いまの成功を掴むうえで一番の転機となったポイントがどこなのかということ」
マーク「う~ん、強いて言うなら一番最初に受けたドラムのレッスンがそれに当たるのかな。家族や親戚にミュージシャンがいないのもあって、ミュージシャンは身近な存在ではなかったんだ。両親が僕に望んでいたのは、なにかに熱心に取り組むこと。それでドラムのレッスンを受けることになったんだけど、それまではドラマーになろうなんて考えてなかったよ。でも15歳のときに初めてレッスンを受けて、〈これは趣味の域を越えたものになるかもしれない〉と感じたんだ。 普通のミュージシャンが楽器を始める年齢よりも遅いでしょ。あとは最初の(ドラムの)先生だね。ジョー・ベルガミーニ(Joe Bergamini)という人で、音楽が人生にとってどういうものになり得るかという可能性を示してくれたんだ。非常に大きな出会いだった」
松下「じゃあプロになってからだとどうですか。アヴィシャイ・コーエンやウェイン・クランツ、ティグラン(・ハマシアン)とか、多くの出会いもあったと思うし、〈このときに自分は変わったかも〉、あるいは〈周りの人が自分を見る目が変わった〉と思うようなポイントはありましたか?」
マーク「実は、そういうことは考えないようにしているんだ。自分がなるべく変わらないようにね。デヴィッド・ボウイとのことにしてもそう。彼のアルバムに参加するのは本当に名誉なことだけど、僕自身は彼と出会う前の自分となんら変わっていない。彼から本当にたくさんのことを学んでインスパイアされたけど、僕はただ前進するのみだよ。いまとなっては、むしろこれまでよりもさらに努力を積まなくてはと思っている。僕の目標は、自分が信じている音楽を作って、できるだけたくさんの曲を書いて、訓練して、そしてひたすら前進し続けること。努力というものは偽造できないからね。まだ若かった頃はもっと時間があって練習することができたけど、いまはそのときほど時間の余裕がない。それでも練習を重ねて前進したいし、現状に満足するなんてことはしたくないんだ」
――さすが。
マーク「だからNYが好きなんだ。あの街は常に動いているから、満足するなんてことはできない。実際に住んでいるのは真隣りのジャージーシティだけどね。いつも忙しい街だけど、僕はその感じが好き。常に努力をしているよう、背中を押してくれている感じがね」
松下「友人である(ニーボディの)ベン・ウェンデルにも同じことを訊いたけど、やっぱり同じようなことを言ってましたね。〈前に進み続けろ〉って。すごく重要なことですよね」
マーク「僕が幸運な機会に恵まれてきたのも、やっぱりそれまで努力を重ねてきたからだから。だから今後もそういった機会に関わりたいのであれば、これからも努力を続けないと。いつも謙虚に、自分に正直にあり続けることだよ」