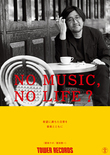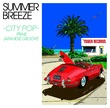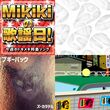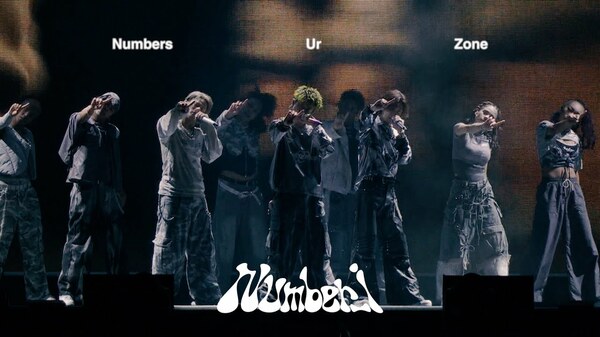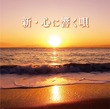ポスト・J・ディラ的なビートに、SMAPで聴かれるようなフィルが入ってくる
――『SUPERFINE』はそういうマシーンと身体性の関係をさらに遊んでいる印象です。全体的にビートメイカーっぽい音作りに聴こえるけど、そのニュアンスをバンド感と共に表現しているような感じもある。birdさんの『Lush』における、プログラミング・ビートを人力に置き換えた演奏をもう一度機械で打ちこんでみる、という手法をもう2ひねりした感じと言いますか。
「ビートメイカーっぽく聴こえるのは、実際にマシーン・ビートだけの箇所もあるからだよね。でも、そのマシーン・ビートを鳴らしつつ、ドラマーがもう一人いて、サビからは普通のドラムになったりもしているじゃない? “Radio体操ガール”とか。コムアイさんの“冨田魚店”もマシーン・ビートと一緒に、ジャズ・セッティングのドラムが普通に叩いているような作りになっているし。頭の2曲はビートメイカーっぽいけど、アルバム全体的にはそういうコンセプトの曲が多いかな」
――ビートメイカーっぽいクールな質感もあるなかで、物凄く人間臭いドラムが突っ込まれるのがおもしろいんですよね。いかにもドラマーらしいフィルがいきなり入ってくる(笑)。
「あれは何なんだろうね(笑)。僕がそもそもビートメイカーじゃないのと、やっぱり曲構造がポップスだからかな。J-PopでもABCとパートがあって、ビートだけはクラブ仕様みたいなのがあるけど、そういうのはよく聴くからやりたくないかなとか思って。あとは言うまでもないけど、僕はドラムが好きだからああいうふうに思い浮かんじゃうんだよね(笑)。そうやってストーリーを発展させていくスタイルなんだろうな。本当は全体的にクールな感じにして、〈あの冨田さんがフィル入ってないよ!〉みたいにやろうとも考えたわけ。でも、最終的にはいろいろやっちゃいましたね」
――だからこそ『Lush』の進化形のように聴こえるんですよね。あとは、僕がちょうど原稿を頼まれたので、『SUPERFINE』と並行して90年代のSMAPをずっと聴いていたんですよ。マイケル・ブレッカーやオマー・ハキム、ヴィニー・カリウタやバーナード・パーディなどが参加していた……。
「(ジャズ/フュージョン系の)海外ミュージシャンがたくさん参加していた時期のだよね※」
※象徴的なのがSMAPの95年作『SMAP 007〜Gold Singer〜』。同作のセッションは参加ミュージシャンにも刺激を与え、のちにオマー・ハキムの号令でスマッピーズとして再集結。同名義で2枚のアルバムを発表した
――そうそう。『SUPERFINE』にはポスト・J・ディラっぽい感じもあるじゃないですか。アンダーソン・パックやノーウォーリーズ、ノーネームみたいな雰囲気のビートもあるんだけど、そこにフィルが入ってくると〈あれ、SMAPで聴いてたやつじゃん〉みたいな(笑)。
「僕がドラムを打ち込みする時は、特定の何かをシミュレートするんじゃなくて、〈ドンスタタドドタ〉とかフィルも普通に浮かぶから、それをそのまま打っていくんですよ。ヴィニー・カリウタくらいまでの歴史はベーシックにあって、ロナルド・ブルーナーJr.もその延長線上に浮かぶかな。いまはそこにマーク・ジュリアナやクリス・デイヴも曲調により混じってきてる感じで。だから、非常によくわかるね(笑)。SMAPで聴かれるようなタイムとフィルのフレージングとか、ドラムのなかに出てきていると思う」
――『SUPERFINE』にバーナード・パーディはいないけど、ヴィニー・カリウタはいましたよ。
「わかる(笑)。そういえば、マーク・ジュリアナはヴィニーの譜面を読んでいるという記事を柳樂さんに教えてもらったけど、やっぱりなと思ったよ。ポリリズムやメトリック・モジュレーションを掘り下げる時は、みんなヴィニーを研究しているみたいだね」
――冨田さんのパブリック・イメージでもあるヴィニー的なドラムがある一方で、そのスタイルをちょっとずらしたらマーク・ジュリアナになるし、また違うずらし方をしたらクリス・デイヴになるわけじゃないですか。トニー・ウィリアムスからヴィニー・カリウタを経由して、現代に辿り着くまでのジャズ・ドラマーの歩みというか。冨田さんが打ち込むドラムにも、80年代から現在までのスタイルが混ざっているのがおもしろい。
「もうちょっとすると、さらに混ざってくる気がするんですよ。例えば、マーク・ジュリアナみたいなよくわからないフィルが浮かぶことはあるけど、あのドラミングがどんな曲でも真っ先に浮かぶというのはまだなくて。作っている曲調、構造の影響が大きいと思うんだけど、だから曲の呼吸として入るフィルインは、ヴィニーというか、伝統的なものが真っ先に浮かんじゃうんだろうね」
――あとはこの音作りで、ファンクの要素がないのも興味深いです。
「“Radio体操ガール”もサビのパターンはJBなんだけど、もろファンクじゃないですよね。意識的にそうしました。日本語の曲でファンクをやると、コミカルな路線だと思われることが多い気がしていて。面白みは感じてほしいんだけど、笑わせにかかっている曲ではないというスタンスを重要に思っていて、そのためのYONCEさんでもあるの。YONCEさんは顔もイケメンなんだけど、声がとにかく二枚目なんだよ。実直さも感じるしさ」
――車のCMにも合いそうですよね、アーバンな感じで。
「みんな依頼した時よりもどんどん人気者になっちゃって、いろいろ困りますよ(笑)。藤原さくらさんもそう。まだ20歳なのに、英語で歌っているのを聴くと国籍も人種もわからなくなる感じがあって。おもしろい娘が出てきたなと思ってお願いしたの。そしたら1月のレコーディングが終わった後に、〈春から月9(のドラマ)に出るんです〉と言われて」
――藤原さくらさんのバックは、mabanuaさんやKan Sanoさんといったorigami PRODUCTIONSの面々が務めているんですよね。SNSを見ていても、いい感じのレコード屋さんに行って古い音楽を聴いていたりと趣味がいい。その話をフリー・ソウルの橋本徹さんにしたら、〈俺が福岡でイヴェントをやった時にライヴで歌ってたよ、まだ10代だったかな〉と言ってました。
「先日、彼女のラジオ番組(『MUSIC FREAKS』)にお邪魔したんだけど、韓国のギター・ポップやインディーの曲を結構かけてて。音楽のセンスがすごくいいんだよね。お父さんもミュージシャンで、冨田ラボに誘われた時もとても盛り上がったらしい。〈さくら、絶対にやれ!〉って(笑)」
――藤原さくらさんの“Bite My Nails”もアルバムのなかで大きいですよね。ああいう曲が入っていると全然違う。
「あれが最初に出来上がったの。今回やりたかったのは“Radio体操ガール”みたいな方向なんだけど、藤原さんが歌っているような、ああいう感じの曲がないアルバムは考えられなくてね。ちゃんと地に足の着いたものが1曲出来ると、自由に何でもできる気がしてくるんですよ」
――CICADAの城戸あき子さんが歌う“鼓動”もおもしろかったです。すごく綺麗なメロディーなんだけど、ドラムがかなり叩いている。
「生ドラムっぽいアプローチをするか、プログラミングっぽいアプローチをするか、みたいなバランスは常に考えていて。コムアイさんやYONCEさんの曲は両方混ざってる感じで、坂本真綾さんの“荒川小景”は完全にプログラミング重視。それで“鼓動”は歌を入れるまではワンループだったんだけど、あの曲は作りはじめた時から生ドラミングっぽい曲にしようと決めていたんだよね。何か1曲、あれくらいのBPMでドラムをいっぱい叩く曲をやりたかったから」
――あとはハイエイタス・カイヨーテのように、1曲のなかに何曲分も入っているような感じで、どんどん曲調やパートが移り変わっていく曲がいくつかありますよね。“荒川小景”もリズムが変わったり違う楽器が入ってきたり、どんどん曲が変化していく印象でした。
「そうかもしれない。でも、それって確かに情報量が多いとも取れるし、もうちょっと大雑把に聴くと〈カラフル〉くらいに聴こえる塩梅にしたかな。そういうつもりもあったから」
――歌だけ聴いていると普通に歌モノなんだけど、後ろの音は全然普通じゃない。だから、〈あれ?〉と思う瞬間がいっぱいあるんですよね。
「うん。〈歌だけ聴いている人〉にも届くのがポップスだという気はしているんだよね。そこは満たしながら、でも音楽には歌以外にも心動かされる要素が無限にあって、それらはバランスを考えながら盛り込むから、普通のポップスとは違うところもいろいろある。それを両立させたいというのは常にあるかな」