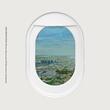女性シンガー・ソングライター、ユイミナコによるソロ・ユニット、MINAKEKKE(ミーナケッケ)のデビュー・アルバム『TINGLES』がリリースされた。アコースティック・ギターによる弾き語りを基軸としつつ、オルガンやファゴット、パーカッションなど必要最小限の楽器を加えて構築されたサウンドスケープは、アシッド・フォークやダーク・サイケ、ポスト・パンク、シューゲイザーなどさまざまな要素を感じさせる。シンプルだがヒネリの効いたコード進行とメロディー、そして孤独にそっと寄り添うような歌詞の世界は、エリオット・スミスやフィオナ・アップル、イールズ、ふくろうず、きのこ帝国といったアーティスト/バンドを彷彿とさせるが、何より印象的なのはそのヴォーカルだ。
魂を振り絞るようにソウルフルかつエモーショナルであったかと思えば、触れたら砕け散ってしまいそうなほど脆くて繊細な歌声は、アルバム・タイトルが示すように、記憶の奥底にしまいこんでいた感情をヒリヒリと刺激する。プロデューサーに〈和製ジョー・ミーク〉こと橋本竜樹(Nag Ar Juna)、サウンド・エンジニアにD.A.N.や蓮沼執太フィルなどを手掛ける葛西敏彦と、強力な布陣を迎えての本作は、間違いなくシーンに一石を投じるだろう。
実は、今回が彼女にとって記念すべき初のインタヴュー。作品から想像したダーク・ファンタジーの主人公のようなキャラクターと、天真爛漫な素顔とのギャップもまた魅力的だった。
「さらば青春の光」のようなユース・カルチャーが好き
――小さい頃から絵を描いたり歌を歌ったりするのが好きだったそうですが、本格的に音楽をやり始めたのは、どんなきっかけだったのですか?
「小学6年生くらいの頃から、詩のようなものを遊びで書いて、それに童謡みたいなメロディーを付けて遊んでいたんですけど、ちゃんと自分で曲を作ってギターも弾こうと思ったのは、中1の時にYUIさんを聴いたのがきっかけでした。女の子で、自分で曲を書いてギターを弾きながら歌うのってカッコイイ!と思って。私たちくらいの世代では、影響を受けた子は結構多いと思うんです」
――どんな気分の時に、曲が書きたくなりましたか?
「本や映画を観た後、これに主題歌をつけるとしたらこんな感じかな?って思って作り始めることが多かったです。中学生の頃は、それこそ重松清や森絵都など思春期の微妙な時期に刺さる小説をよく読んでいたので(笑)。それを自分なりの言葉で置き換えて、YUIさんっぽいメロディーを乗せるなどしていましたね。わりといまでも映画や本にインスパイアされて音楽が生まれることは多いです。この頃にやっていたことが、肥やしになっているのかもしれないですね」
――なるほど。音楽はどんなものを聴いていました?
「小学生の時も、親が聴いていたビートルズやカーペンターズ、スティングなどを聴いて、〈こんな音楽があるんだ〉なんて思っていたんですけど、中学生くらいからはアヴリル・ラヴィーンのような、〈ロックをやっているカッコイイ女の子〉に憧れてました(笑)。本格的に洋楽を聴き始めたのは、同じ高校にめちゃくちゃ音楽好きの子がいて、その子と仲良くなっていろいろ教えてもらったのが大きいです。私も何か提供しなきゃっていう、負けず嫌いな性格が出たのだと思うけど(笑)、図書館に行って棚にあるCDを片っ端から借りていくうちに、好きな音楽の傾向がどんどん変わっていきましたね」
――どんなふうに変わっていったのですか?
「その友人からレディオヘッドを勧められて、図書館で探したら『Kid A』(2000年)だけあったんですよ。初めて聴いた時は、何が良いのかわからなくて、聴いちゃいけないものを聴いてしまったような気持ちにもなったんですよね。でも図書館で借りてきたCDは取り敢えず全部iPodに入れて、シャッフルして聴いていたんですが、1曲ものすごく心に引っかかったのが『Kid A』に入っていた“Morning Bell”だったんです。それで、いまならアルバム1枚通して聴けるかもと思って聴き返したら、すごく良くて一気にハマりました。それからレディオヘッドのほかのアルバムも聴いてみたり、その周辺のUKロックやUSインディー、北欧のビョークやシガー・ロスなどを聴いてみたりするようになったんです」
――そうすると、作る曲の傾向も変わっていきましたか?
「そうですね。ネットでコード進行を調べたり、YouTubeに上がっている洋楽のカヴァーを観て、ギターの押さえ方を真似たり。〈あ、こんなコード進行になっているのか〉〈アコギ一本だとこんなふうに聴こえるのか〉みたいな感じで、少しずつ変わっていったと思います。好きなバンドのアコースティック・セッションとかすごく勉強になったし、観るのが大好きでしたね」
――音楽以外のカルチャーに興味はありましたか?
「幼稚園の頃からディズニーやTVで〈カートゥーン・ネットワーク〉を観るのが大好きで、洋楽を聴くようになってからは、より英・米のカルチャーに傾倒していきましたね。大学は英文学科だったんですけど、そのきっかけはポール・オースターやカート・ヴォネガット、フラナリー・オコナーなどアメリカ文学を読むようになったことでした」
――映画もお好きそうな印象です。
「はい(笑)。卒論で『2001年宇宙の旅』(68年)を取り上げたんですよ。自分は例えばイギリスだと『さらば青春の光』(79年)のような、ああいうユース・カルチャーが好きなんですけど、『2001年~』って一見関係なさそうじゃないですか。だけど、ある論評によれば当時のアメリカン・ニューシネマ――『俺たちに明日はない』(67年)や『イージー・ライダー』(69年)とかが社会に抵抗した若者たちが破滅する話だとすれば、『2001年~』は体制に刃向かった主人公が〈スター・チャイルド〉に進化するという形で自由を手に入れる話なのだと。それを聞いて映画を観直したら、〈なるほど!〉って思ったんです(笑)」
――ああ、それはおもしろいですね。
「あとはタイムリープ系のSFも好きで。『ドニー・ダーコ』(2001年)や『バタフライ・エフェクト』(2004年)、最近だと『インターステラー』(2014年)とか。結構、趣味がゴチャゴチャしていて、このあたりを話し始めると止まらなくなるかもしれない(笑)。でもやっぱり若者主体の映画に好きなものが多いのかなと思っていて。青春映画も普通に好きで、最近だと『ウォールフラワー』(2012年)とか……。アルバムの“L.u.x.”という曲のモチーフになっているのも、『ヴァージン・スーサイズ』(99年)でキルスティン・ダンストが演じる女の子のラックスなんです」
――グザヴィエ・ドランなんかも好きなのでは?
「『マミー』(2014年)はすごく好きですね。音楽の使い方や途中でフレームのサイズを変えるタイミングとか素晴らしいなと。やっぱり、映像と音楽って切り離せないものだと私は思っていて。自分の表現ではもちろん〈音ありき〉ですけど、どちらも大事にしていきたい」

一人でもいいから始めてみよう
――いま、ライヴではループ・マシンを使って一人で音を重ねるなどしているんですよね。そういうパフォーマンスに至るまでの試行錯誤はどのようなものでしたか?
「もともとはアコギ1本で活動しようとは思っていなくて、できればバンドを組みたかったんですけど、一緒にやりたいと思う人が身近にいなかった。なのでとりあえず一人でもいいから始めてみようと思ってやり始めたんですね。それでさっき言ったようにYouTubeなどでいろんなアーティストの演奏を観ているうちに、〈一人でおもしろいことをやったほうがバンドでやるよりカッコイイかもしれない〉と思ってきて(笑)。ループ・マシンを使った演奏もYouTubeに上がっているのを観て、へえ!こんなのがあるんだと衝撃を受けたんです」
――なるほど。
「ちょうどその時に作っていた曲が、アコギ1本だとちょっと物足りないなと思っていたところだったので、思い切ってループ・マシンを買って。スタジオに入り浸っていろいろ試していくうちに、使い方も覚えていきました」
――ループ・マシンを導入してからは、曲作りの方法も変わりました?
「うーん、すべての曲をループ・マシンで作っているわけではなく、骨子となるコードとメロディーをまず作って、アレンジの段階で〈あ、ここはループが使えるかも〉とか考えることが多いんですよ。ループありきで作ろうと思うこともありますけど、基本的にはまず〈曲ありき〉なので、曲作りそのものはさして変わっていないですね。大抵はデタラメ英語で適当に歌いながらメロディーを作って、曲の構成がある程度出来てきたら、そこに歌詞を乗せていきます。それとほぼ同時進行でギターをどうしようか考えていくんですけど、歌詞が出来上がるのは最後というパターンが多いですね」
――いまでも曲を作ろうと思うきっかけは、さっきもおっしゃっていたように映画を観たり小説を読んだりした後が多い?
「そういうパターンも多いんですけど、歌詞を書く時は、自分のその時の感情だったり、その時に自分に起きた出来事だったりすることが多いですね。何かしら、感情を揺さぶられることがないと歌詞は書けないので。よく空想の世界を書いていると思われがちなんですけど、実際はめちゃくちゃパーソナルな歌詞なんですよ(笑)」
――なるほど。映画や小説はあくまでもきっかけであって、フォーカスしていくのは自分の感情なのですね。
「そうですね。そうやって自分の感情を楽曲として昇華することで、救われていることも多いですね。特に10代の頃はそうでした。それで書き続けている部分も大きいと思います」