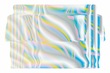元・森は生きているの岡田拓郎が初のソロ・アルバム『ノスタルジア』を完成させた。岡田自身が作詞/作曲やさまざまな楽器の演奏に加えてヴォーカルもみずから担当し、バンド時代の一歩先を示すような仕上がりの本作には、ゲスト・ミュージシャンとして元・森は生きているのメンバーや、ROTH BART BARONの三船雅也、吉田ヨウヘイgroupの西田修大、ドラマーの石若駿らが参加。エンジニアは岡田自身に加え、バンド時代からの付き合いである葛西敏彦と吉田ヨウヘイが担当している。才能溢れる若き音楽家のカムバック作であると同時に、現在の東京のインディー・シーンが、かつてのシカゴやブルックリンのような豊饒さを誇ることを改めて示す意味でも、2017年の重要な一枚だと言えよう。
――今回のリリースに関して、マネジメントがonly in dreams、レーベルがHOSTESSというのはちょっと意外でした。
「バンドを解散してボーッとしてたときに、Gotchさんが連絡をくれたんです。流れ星(への願い事)のつもりで〈金さえあれば、いいアルバム作れるのにな〉みたいなことをつぶやいて3秒で消したんですけど、一個だけついてたコメントがGotchさんで、〈いずれやりたい〉みたいに言ってくれて。それからメールでやり取りして、以前ラ・ラ・ライオットをHOSTESSから出してたこともあり(ラ・ラ・ライオットの日本盤をonly in dreamsがリリースした際、HOSTESSとのダブルネームだった)、今回出させてもらうことになりました」
――Gotchさんとは以前から面識があったんですか?
「2014年に1回フェスで一緒になったことがあって、ライヴを観てくれたみたいなんですけど、その頃って僕が一番尖ってた時期なんですよ。ネイキッド・シティーみたいなハードコア・ハーシュ・ノイズを10分くらいやった後に曲やるみたいな感じだったんですけど(笑)、でもそれが印象に残ってたみたいで。Gotchさんがいなかったらアルバムを作ってなかったかもしれないし、少なくともグレッグ・カルビ(マスタリングを担当)にはなってないと思うので、感謝してもし切れないです」
――森は生きているの解散からは2年が経つわけですが、ソロのレコードを作ろうという構想はいつからあったのでしょうか?
「もともとは新しいバンドを組むつもりで、解散する前後から一緒にやってみたかった人にメールして、何回かスタジオにも入ったんです。そもそも自分で歌いたいと思ってもいないし、ソロでやるつもりはなかったんですけど、そのバンドが上手くいかなかったというか、作業を進めていくうち、〈自分の感情を歌いたい〉ということとは別のところでパーソナルな表現になりすぎて、それを誰かと共有しながらやるっていうのが難しくて。トータル・コンセプトを全部一人で握って作るっていうことを、今くらいの時期に一回経験したほうがいいかなっていうのもあったので、修行と思ってソロでやることにしました。さんざんみんなに無理言って、スケジュール空けてもらったのに、〈やっぱ一人でやるわ〉っていうのは申し訳ないし、バンドもまたやりたいとは思ってるんですけど」
――一言で〈ソロのレコード〉と言っても、岡田くんだったらいろんなタイプの音楽性が考えられたと思うんですね。結果的には、作詞/作曲はもちろん、歌までみずから歌うポップスのレコードになっているわけですが、なぜこういった作品になったのでしょう?
「最初はインストを考えてたんです。もともと自分では歌えないし、ジャズとかポスト・ロックが好きだったからそういう曲を書きました。たまたまはっぴいえんども好きになったがゆえに、森は生きているというバンドでポップスをやってた時期があったけど、そのバンドも解散したわけだし、元に戻って全部一人で完結できるインストを作ろうと。そのほうが歌とか歌詞の制約もなく、自由にできるなって。でも、〈これからどうしようかな?〉みたいな話を吉田(ヨウヘイ)さんとしたときに、ソロのキャリアの1枚目でインストを作っちゃうと、〈岡田くん、そういう人になっちゃった〉みたいに思われて、せっかく森(は生きている)を観てくれてたお客さんたちはみんないなくなっちゃうんじゃないかって(笑)。それで〈確かにそうだな〉って思ったので、じゃあ、ポップスを作ろうっていうのが、いろいろ要因はありましたがひとつの動機でした」
――(岡田のフェイヴァリットの)ジム・オルークで言うなら、『The Visitor』(2009年)ではなく、『Eureka』(99年)を作ったというか。
「まさに、最初は『The Visitor』をやろうと思ったんです。でもあれって、30歳とか40歳になって、キャリアを築き上げた人が個人に立ち返ることでできるライフワークみたいなアルバムでもあると思うんです。僕なんてまだスタートしてもいないようなところにいるのに、いきなりあれやっちゃったら、ホントにアンダーグラウンドな人になっちゃうかなって。僕、売れてる音楽も好きですからね(笑)」
より過激なはっぴいえんど
――本作の作品としての青写真は、どの程度描いたうえで制作に入ったのでしょうか?
「60~70年代のポップ・ミュージックは本当に良く出来ていて、その後のポップ・ミュージックの歴史は機材や奏法の発展、他ジャンルとの融合、テクスチャーの進化だと思っています。これはとてもポジティヴに捉えていい話だと思っていて、歴史に対して〈少しでも新しい〉を加えて、少しでも新たなアーカイヴを生み出したいという点では森は生きているからのスタンスと変わらないんですけど、森のときの〈新しい〉感覚として、自分の言語でアウトプットできるまで一旦消化できたのは、言ってもポスト・ロックやエレクトロニカ、フリー・フォークあたりの2000年代半ばあたりまでの感覚だったと思います。それ以降のものは聴いてはいたけど、消化するのにすごく時間がかかりました。バンドが解散するギリギリ前くらいにやっとダーティー・プロジェクターズの『Bitte Orca』(2009年)とかグリズリー・ベアの『Veckatimest』(2009年)を聴いて、改めてすごい感動して、それを拙くとも自分の言葉で何が新しく感じたのかを言語化できるようになりました。あれって60~70年代に出来上がってしまったポップスに、ポスト・ロックやエレクトロニカよりさらに過激な要素を加え、なおかつ意識的にポップ・ミュージックとして構築していくことで、まったく新しく聴こえる音楽へ更新したっていうことだと思うんです」
――それを日本語のポップスでやろうとしたと。
「はっぴいえんどは、(洋楽からの)借り物であるロックやポップスのメロディーとの相性がどう考えても悪い日本語を、いかに英語の音楽を聴くように乗せるかということにとても意識的だったと思います。そしてサウンドは、当時とってもオルタナティヴな響きを持っていた(US)西海岸のロックを手本にしていて。僕がはっぴいえんどの何に感動したかというと、出来上がった音楽の美しさはもちろんですが、一番はそのプロセスなんです。そういう意味で、僕はその後のはっぴいえんどを引き合いに出して語られる〈喫茶ロック〉とかは好きになれない。はっぴいえんどが何を作ったかというのはもちろん重要なファクターですが、あの時代に〈なぜ〉ああいったプロセスが生まれたかがとても重要だと思います。今回の僕のアルバムの制作時に明確な意識としてあったのは、フォーマットは自分が新鮮に思う新たなサウンドに対して、はっぴいえんどが持っていたと思う〈日本語をいかに扱うか〉というプロセスを自分の方法で試すということでした。今、アルバムが出来上がって自分で聴いて、それが上手くいったかどうかはわからないし、そもそもそんなに重要なことではなくて、〈試みること〉がとても重要なことでした。
とはいえ、2017年の今となってはロック・バンドの音自体が新しい音楽かって言われると、それも難しい話かもしれないですけど……今回のアルバムを作ってる途中にボン・イヴェールがあんなの(2016年作『22, A Million』)を出したから、やっぱり迷いはしました(笑)。ディアンジェロが久々に出したの(2014年作『Black Messiah』)とかって、自分はそんなに衝撃ではなかったし、自分とは別のモノって考えられたんですけど、ボン・イヴェールの新作とか、あとダープロの新作(2017年作『Dirty Projectors』)もあんまり評判よくないみたいで、みんな〈がんばったね〉しか感想言わないけど(笑)、でも自分はあの1曲目とか衝撃だったし。なので、日本のなかでは新しいことをやってると思いつつ、視野を広げると〈もっとヤバイの出ちゃってるな〉とも思ったんですけど、でも〈これは一回やっておかないと〉と思って作ったんです」
――実際サウンド面においてはかなり実験的で、非常に独特な音像になっていますね。
「森とあきらかに違うのはドラム・パターンを解体したことで、〈スネアが3拍目に入る〉みたいな、決まりきったことは絶対したくなくて。ダープロとかグリズリーの過激な部分のひとつって、そういうドラム・パターンとかギター・サウンドとかが普通じゃないってとこだと思うんですよね。あと楽器をいくつも重ねて違う音にするっていうことは結構やってます。例えば、“アルコポン”とか“硝子瓶のアイロニー”では、オートハープのエコー成分をアコギに重ねることで、アコギだけだと出ない倍音を出したり、ピアノにしても、部屋鳴りそのままよりはルームの音をコンプで潰して、アコースティック楽器をマイクに通すことでできる音響的なアプローチはいろいろなところで試してみました」
――最初に言ってくれたリズム・パターンのことで言うと、今だとヒップホップっぽいループで、ビート感を強く押し出すものも多いですけど、そういうものとも違いますよね。
「グリズリー・ベアの新作(2017年作『Painted Ruins』)はドラムの音めっちゃ近かったですよね? あれが先に出てれば、そうやったかもしれないですけど(笑)、でもドラムに関してはできるだけ広い部屋で録ったルームっぽい感じのほうが好きなので、いわゆるビートものっぽいアプローチはしませんでしたね。少し意識したところでは、“ブレイド”のところどころで細かいハットを刻んでもらったんですが、これはプロトゥールスのグリッドの概念ではなく、大きいタイム感のなかで、マシーン的な細かいフレーズを同時に体現することを意識しました。音響的なところで言えば、キックをもっと前に出せば音圧も出て今っぽいと思い、ミキシングでいろいろ試したんですが、録音のときにそこを意識して録っていなかったので、録り音を活かしたほうがいいかなというところで、今回はこの塩梅になりました」
――そもそも、石若くんの参加はどういった経緯だったんですか?
「僕も新しいジャズは好きなんですけど、ヒップホップっぽいものよりも、ブラッド・メルドーとかブライアン・ブレイドとか、フォークっぽいジャズをやる人が好きで。石若くんのソロ・アルバムを聴くと、ドラマーのリード・アルバムなのに、ビートっぽいことをやるっていうよりも、フォーキーな良い曲のアルバムなんですよね。めちゃめちゃ叩ける人がそういうのを作るって、ある種の抑制されたプロデュース感覚がないとできないと思うんですよ。自分のリーダー・アルバムで、アート・ブレイキーにはならずに……アート・ブレイキーも中期からはすごいプロデューサーでしたけど(笑)、とにかく、いわゆるドラマーみたいなことはしないで、どう楽曲を良い方向に持っていくかっていう視点を持ってるのがおもしろいなって思って、一緒にやりたいなって。“ブレイド”は特に石若くんのフィーリングが必要で、ジャズのドラマーが普通のエイト(・ビート)を叩いてる雰囲気が欲しかったんです」
――“ブレイド”には吉田ヨウヘイgroupのギタリスト・西田くんも参加していて、石若くんともども個性の光るプレイを聴かせてくれますね。
「このドラムとギター・ソロを入れたいがために作ったような曲です(笑)。西田に関しては、基本的にインダストリアルでマシーンを用いながらベンドすると、ジョン・フルシアンテくらいエモいイメージもあるんですけど(笑)、普段の西田みたいにはしたくなかったから、〈アブストラクトなエフェクターを使わずに、この小節はカート・ローゼンウィンケルみたいに弾いてくれ〉とか、いろいろ注文しました。なので、これインプロっぽく聴こえると思うんですけど、ソロを組み立てるのに2か月くらいかかって、何回も弾いてもらったんです。〈ジョン・フルシアンテじゃなくて、カート・ローゼンウィンケルがいい〉とかって、言うのは簡単ですけど、やるのはすごく大変だったと思います(笑)」
一回諦めてから、そのうえで何をしよう
――自身の歌に関しては、アルバムを録り終えた今どんな手応えがありますか?
「二度と歌いたくない(笑)。もともと歌うことは苦手だし、ましてや言葉のノリが悪い日本語で歌うのはホント自分にはできないって、一回諦めてから、そのうえで何をしようかって感じでしたね。まあ、シンガー・ソングライターだって思えば、そんなに歌が上手である必要はないって言い聞かせながら作りました。歌い方はいろいろ試して、張ってみたり、加山雄三みたいに歌ってみたりもしたんですけど(笑)、ニュアンス的には、自分の声質は加藤和彦さんに似てるわけではないけど、近いところはあるかな、とか。加藤さんとか細野(晴臣)さんって、いい意味で言葉と歌う人の人格が離れてて、情念があきらかにないじゃないですか? 情念臭さが日本語の野暮ったさに繋がってると思うので、そういうのを消すって意味では、自分がサラッと歌うのもいいかなって」
――例えば、オートチューンを使ったりしようとは思わなかったですか?
「もちろん、やりましたよ(笑)。今、ケロケロしたりピッチを変えてもあんまり新しくないっていうか、直近の新しさってとても扱いづらいと思うんですよね。日本語の響きにもあんまり向かないように思いますし……10年後ぐらいにもう一度トライしてみたくはありますが(笑)。フランク・オーシャンとかは、もちろん大好きです」
――あと、ゲスト・ヴォーカルが2人参加しているのは、もともとの構想だったんですか?
「長いこと制作していたので、どんどん擦り減ってしまって……何か新鮮な出来事欲しさでお願いしました(笑)。“遠い街角”は最初から優河さんと一緒に作ったんですけど、“アモルフェ”はもともとボツ曲なんです。理由は自分が歌えないから(笑)。あのおどろおどろしい感じを日本語で嫌味なくできるのは、三船くんくらいかなって。全曲違うヴォーカルっていうのも考えはしたけど、でもプロデューサー主導でたくさんヴォーカリストが参加してるパーティー・アルバムって一枚も持ってないし、好きじゃない(笑)。そういうのを作りたくはないから、最初は全部自分で歌うつもりだったんです。でも、ジェイムズ・ブレイクのアルバムにゲストがフィーチャリングで参加してるのとかオツだなとも思ったりして、クレジットの遊び心も含めてって感じです」
――“グリーン・リヴァー・ブルーズ”にはコラボ・アルバム『Mujo』もリリースしているDuennさんが参加していますね。
「ダープロの作品にタイヨンダイ(・ブラクストン)が参加してるニュアンスっていうか、どの音やってるかわからないけど、クレジットにいるみたいなのがいいなって。〈可聴域より低い低音のサンプルを送ってもらえませんか?〉って送ってもらって、それを使ってるので、iPhoneだと誰もDuennさんの存在に気付かないと思います(笑)」
いかに表層的な情念をなくすか
――これだけまとまった量の歌詞を書くこともなかったかと思いますが、やはり松本隆さん的な色合いは感じられますね。
「演歌とか歌謡曲は情念が強くて、情念的に歌うことで人の心に訴えかけるみたいな、その情念の良い意味での強さみたいなものが歌謡曲の歴史だと思うんですけど、バッファロー・スプリングフィールドにその日本的な情念を乗せるのは野暮ったいから、そこをいかに、表層的な情念をなくすかっていう、はっぴいえんどの実験はそこにあったと思うんです。その後のフォロワーはそのポイントが曖昧になっていったような気がするんですけど、僕は、〈表現したいこととしての情念〉はもちろんあるにしても、表面的な情念は削げるだけ削ごうと思って書きました」
――〈眠れぬ夜の 黙り込んでいる ぼんやりと見つめる 鏡の向こう ただの霧さ〉という1曲目の“アルコポン”の歌い出しからして、内省的な雰囲気が漂っています。
「〈この人大丈夫かな?〉って感じですよね(笑)。まあ、音楽における言葉はわかりやすいメッセージで人の心を煽るようなことはせず、詩情のようなものでイメージが浮かぶような、浮かばないようなくらいが良いかなと思います」
――“アルコポン”というタイトルは尾形亀之助の詩集「色ガラスの街」からの引用だと思うのですが、彼の作品に今、岡田くんが話してくれたような日本語の魅力を感じたわけですか?
「尾形亀之助はすごい好きで、『色ガラスの街』は特に好きな詩集です。10代の頃に初めてちゃんと読んだ詩集ということもあるんですが、日本語でしかできない表現ってあるんだなと、当時、漠然とですが感じました。詩や音楽に限らず、映画でも写真でも、ふとそこから滲む言葉にするのが難しいポエジーのようなものだったり、郷愁のようなものに強く惹かれてきました。これは懐古みたいな感覚とはまったく違って、何かもっと普遍的な感覚の話です」
――『ノスタルジア』というタイトルは、そこから来ているんですか?
「このタイトルを付けた理由はいろいろありますが、そのひとつではあります」
――アルバムが完成して、この先ライヴは予定しているのでしょうか?
「ライヴは一旦やらないつもりです。そんなに気が進まない(笑)。年内は他の仕事で埋まってるし、もともと表に出て場を沸かしたいと思うタイプでもないから、後ろで好きなことやってるのがいいなって。外タレの前座専門とかだったらいいですね(笑)。グリズリー・ベアとか超やりたい」
――じゃあ、これから先もいろんな形での活動が続きそうですね。
「まあ、今回は〈習作〉って感じかな(笑)。今は自分に何ができて何ができないかを見極める時期だと思うんですけど、そのなかで作品が出来たときは、できることならちゃんと世の中に出しておきたいし、それがどこかで拾われると嬉しいなって思います」
Okada Takuro
東京を拠点とするマルチ楽器奏者/音楽家。2012年にバンド、森は生きているを結成。『森は生きている』(2013年)、『グッド・ナイト』(2015年)という2枚のアルバムを残して2015年に解散。ソロワークとしてはダニエル・クオンやジェイムズ・ブラックショウのレコーディング/ライヴへの参加や、菊地健雄監督作品「ディアーディアー」において音楽を担当している。その後は、South Penguinの2016年作『alaska』と2017年作『house』のプロデュースや、瀬田なつき監督映画「PARKS パークス」への楽曲提供、okada takuro+duennとしてのコラボ作『Mujo』の発表など、多岐に渡って活動。このたび、ファースト・アルバム『ノスタルジア』(HOSTESS)を10月4日にリリースする。