ミシェル・ンデゲオチェロの新作『Ventriloquism』は、プリンスやTLC、シャーデーらの楽曲をカヴァーしたアルバムだ。
ここで取り上げられているのは主に85年から90年にかけて発表されたR&Bやヒップホップのヒット・ソングで、68年生まれのミシェルが10代後半から20代前半にかけて愛聴していたであろう楽曲たち。本作はいわば自身のルーツを明かしたような作品だが、そこはミシェル・ンデゲオチェロ、やはり一筋縄ではいかない。ソウル・ミュージック、ヒップホップ、ジャズとジャンルにとらわれないサウンドを提示してきた彼女らしい独自の折衷感覚、そしてシンガー・ソングライター的な作家性がどの曲にも溢れており、懐古的なムードは皆無、実にフレッシュなアルバムとなっている。
そんな『Ventriloquism』をきっかけに、「Jazz The New Chapter」シリーズの監修者としても知られる柳樂光隆がミシェル・ンデゲオチェロの長きにわたるキャリアを紐解き、その音楽性を論じた。〈「Jazz The New Chapter 1」の裏テーマはミシェルの再評価だった〉と語る柳樂による以下の論考は〈ミシェル・ンデゲオチェロ入門〉としても読めるであろうし、画期的なミシェル論としても読める充実の内容となっている。
柳樂が作成したミシェルのカヴァーと原曲とが交互に聴けるプレイリストも記事の最下部に掲載しているので、ぜひそちらを聴きながら読んでいただきたい。 *Mikiki編集部
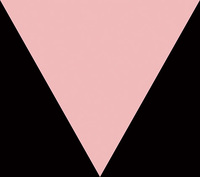
MESHELL NDEGEOCELLO 『Ventriloquism』 Naive/Pヴァイン(2018)
ネオソウル? ヒップホップ? ジャズ? デビュー時から衝撃的だったミシェル・ンデゲオチェロ
ミシェル・ンデゲオチェロという人はずっと僕の関心の中心にいるが、いつまで経ってもその全容が掴めない人だ。ネオソウルの枠で語られることも多い彼女だが、ディアンジェロやエリカ・バドゥらソウルクエリアンズ周辺とも違うし、かといって、ジル・スコットあたりのネオフィリー系の人脈とも違う。どの作品に関しても、どこに置いてもしっくりこない。要は浮いていると言っていいし、困った挙句〈彼女はミシェル・ンデゲオチェロというジャンルだ〉みたいなことを言って済ませたくなる、それくらいに特異な存在だ。そんな彼女のキャリアはいつもとても魅力的だ。その上手く位置づけられないキャリアのなかには示唆的で、時に予言に近いようなものが埋まっていることもあるように思う。ここでは新作の『Ventriloquism』をきっかけに、彼女のキャリアを振り返りながら改めてその音楽について考えてみたい。
ミシェル・ンデゲオチェロは最初期の『Plantation Lullabies』(93年)、『Peace Beyond Passion』(95年)から既に才能がほとばしっている。両作には天才ベーシスト登場と言った雰囲気もありつつ、同時にヒップホップをも視野に入れた新しい時代のブラック・ミュージックが生まれつつあることを予感させてくれる。クレジットを見るとジェリ・アレンやデヴィッド・フュージンスキ、ジーン・レイク、更にはジョシュア・レッドマンまでがいて、敏腕の集まりと言った雰囲気があり、サウンドもかなりフィジカルで、彼女の出自がゴーゴーであることや、スティーヴ・コールマン『Drop Kick』(92年)やスティーヴ・リーマン『Demian As Posthuman』(2005年)などにベーシストとして参加するMベース人脈の敏腕であることがよくわかる。
一方で、スクリッティ・ポリッティの名盤『Cupid & Psyche 85』(85年)にも貢献したデヴィッド・ギャムソンの力を借りていることもあり、強力な生演奏と共に密室的な雰囲気が同居しているのが面白い。それはどこかスタジオにこもり、全ての楽器を自分で演奏し、それを重ねた多重録音で音楽を生み出していたプリンスとも通じるものでもあり、そのサウンドが若干ジャズ的なことを考えれば、プリンスを強く意識していた80年代のマイルス・デイヴィスがマーカス・ミラーらと作っていた『Tutu』(86年)あたりのサウンドを思わせる部分がある。ただ、ミシェルはそれを更に洗練させ、90年代におけるその完成形を提示しているようにも思える。
例えば、ミシェルの作品では、個々の楽器がレイヤーされていたり、もしくは楽器が並走しながらも機能的に作用したりしていて、そこではメロディーに対してハーモニーを付けていくようなオーソドックスな編曲作法で得られるわかりやすい情感が失われるが、その分、音楽は即物的でクールで軽やかになる。生演奏によるフィジカルな人間味を軸にしながらも、編集や編曲により人間的な情感をそぎ落としたようなサウンド――そこには、人間と機械の対立ではなく、新たな関係性の構築とそれによる新たなフィーリングの獲得へのチャレンジがある。それもまたマイルスやプリンスにも共通するところでもあるような気がする。


































