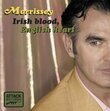Mikikiがいま、このタイミングで観てほしい出演陣を揃えたショウケース企画〈Mikiki Pit〉。次回は2月2日(土)に東京・下北沢 BASEMENTBARで、毛玉、Crispy Camera Club、Half Mile Beach Club、So Sorry,Hoboの4組を迎えて行います。
先日公開した各出演者の観どころ/オススメ楽曲をまとめた記事に続いて、ここではアーティスト自身に選曲してもらった〈バンドを形成した10曲〉を公開していますが……最終組、So Sorry,Hoboはギター・ヴォーカルの梶原笙が超長文をしたためてきたので、まずはプレイリストを掲載し、その後に文章を掲載いたします。たしかに字数指定はしなかったけど、9000字超って……。あまりに長すぎるので、ぜひプレイリストを聴きながらお読みください。そして、この文章に関する文句は全部梶原さんへお願いいたします。
〈Mikiki Pit Vol. 7〉
So Sorry,Hobo 梶原笙を作った10曲
まずは簡単に自己紹介。
So Sorry,Hoboというバンドでヴォーカルとギターをやっている。名前は梶原 笙(かじわら しょう)といって、笙というのは雅楽で使う笛のことらしいのだけど、笛なんてリコーダーすらろくに吹けないし、昔から音痴だったから大層馬鹿にされた。名付け親の祖父を恨んだりとかそういうのはないものの、もうちょっとなんとかならなかったかなとも思う。
1992年生まれの26歳で、いまは働いていない。当然収入もない。誰か仕事を紹介してほしい。夜中にどこかの倉庫で本を読みながらじっとしていればお金がもらえるような、そういう仕事だったらやりたい。それ以外はやりたくない。どうか、頼む。社会性はない。
バンドは去年の9月に『大なつかしい展』というアルバムをリリースした。はじめての全国流通盤だったけど、まああんまり売れなかった。それでもすこしだけ売れたのは、発売のタイミングでこのMikikiというサイトに掲載してもらったインタヴューのおかげかなと思っていて、そのインタヴューを担当してくれた編集の酒井さんから依頼されてこの原稿を書いている。
依頼のメールには〈字数指定なし〉とあった。酒井さんから参考に、と送られてきたほかの人がつくったプレイリストの記事を見ると、プレイリスト以外になんのテキストも記されていなかった。つまり、いま書いている(そしてあなたが読んでいる)この文章はなくてもいいもの、ということになる。人生の縮図だ。でも無職で暇だから、思いつくだけ書いてみる。原稿料はたぶん出ないけど、お金が欲しければこんなものを書いていないで働けという話なのでべつにいい。(※編集部注:プレイリスト以外にアーティストからのコメントも掲載する、というのは今回からの試みです)
音楽について言葉で表すのなんてダサいという意見がある。怒る人はたくさんいそうだけど、わからなくもない。ミュージシャンなら作品で意思は表示するべきで、それ以外の方法を用いるべきではないという意見もある。もしかしたらプレイリストを作る以外何もしなかったあの人も、そう思っていたのかもしれない。これもまあ、正しいかはともかくとして、目指したいし尊重したい考えかただ。でもまあ僕なんかがいまさらダサいとかダサくないとか気にしてもしょうがないので、書けるだけ書く。飽きたらやめる。人生開き直ってからが本番という気が最近している。
曲の説明に入る前に言い訳させてもらうと、僕はあんまり音楽に詳しくないし、〈ベストアルバム聴けばいいじゃん〉とか平気で言ってしまうような人間なので、こういった企画にはあんまり向いていないと思う。なんで依頼が来たんだろう。実はそんな大したものじゃなくて、そのへんの野良犬も書いているようなシリーズなんだろうか。だとしたら僕が得意の自意識過剰を発揮して、無意味に肩に力を入れているだけか。それならいいんだけど。
見栄を張って自分の貧しい知識のなかから有名じゃない曲を列挙して音楽に詳しいフリでもしようかなとも考えたけど、なんだかそれってこの世でいちばんみじめなことなんじゃないかという気がしたのでやめた。このリストに入れた曲たちは〈それについて何か語れそう〉というのを基準にして選んだ。要はそれなりに思い入れのある曲ということになる。
需要があるとかないとかはどうでもいい。長いとかつまらないとか趣味が悪いとか読みづらいとかも知ったこっちゃない。文句はぜんぶ酒井さんに言ってほしい。人のせいにするのだけが上手い。
1.The Jam “Going Underground”
さて、こういうテーマでなにかについて語る(語る、と自分でタイピングした瞬間ちょっと笑った)ときは、やっぱり時系列に沿ってやっていくのがいい。流れがあったほうがそれらしいし、なにより書くのが楽だ。だから一曲目は自分が音楽を聴くきっかけになったバンド、ジャムからの選曲になる。
中学二年生の冬、愛媛県の松山市で芋をやっていた僕は中古ゲームソフトを買いに大街道(松山のメインストリート的な存在)にあったゲオの雑魚バージョンみたいなお店に入った。そこでかかっていたのがこの曲だった。
当時音楽にはほとんど興味がなくて、クラスで流行っている音楽をMDという終わったメディアで聴くぐらいだった。そんな僕がなんでジャムをいいと思ったのか、いまだによくわからない。でもなんだか気になってレジで店員のお兄さんに〈これ誰の曲ですか〉と聞いた。あのとき何かプレステ2のソフトを買ったはずなのに、それがなんだったかは覚えていない。
店内BGMは有線じゃなくて、そのお兄さんの趣味だった(シャザムもない時代だったから〈有線だからわからないです〉なんて言われたらそこでおしまいだった。そう考えると運がいい)。〈これはジャムっていうイギリスのバンドだよ〉とお兄さんは言った。このとき僕はバンドという言葉の意味がよくわかっていなかった。ゴスペラーズもバンドだと思っていた。イギリスのことはバンドよりは知っていたけど、ほとんど知らないようなものだった。
そのお店ではCDもすこし取り扱っていたけど、ジャムのCDは置いてなかったので、バンドの名前とお兄さんから教えてもらった『Compact Snap』というベスト盤のタイトルだけをメモして家に帰った。帰ってすぐ通販で『Compact Snap』を注文して、三日ぐらい後に届いてからはしばらくそればかり聴いた。
いま聴いてもとてもいいと思う。当時はポール・ウェラーにばかり興味が向かっていたけど、ブルース・フォクストンのベースも最高だ。ドラムスも相当上手い。黒地に銀色の文字でわけのわからない英語が散らばっていて、ダメ押しに胸元が紐になっているような最悪の服(でもあれを着られるのって男子中学生の特権だ)を着ていた僕にしてはなかなかナイスな選択だった。
でもまあ、正直に言うと背伸びをして聴いていた部分もかなりあった。“Going Underground”や“In The City”には誰でもわかるようなカッコよさがある一方で、“That's Entertainment”なんかは中学生が聴いてもよくわからない地味な曲だ。それでも当時は未知のものに触れたというある種の熱狂に後押しされる形で、何度聴いても退屈しなかった。
というかべつに背伸びして聴いてもぜんぜんかまわない。あのころ僕の回りには身の丈に合わないことをやると馬鹿にされる空気(英語の授業で真面目に発音すると笑われる、みたいなやつだ)が充満していたけど、あれは本当によくなかった。田舎の悪いところだ。背伸びをしたら本当に背が伸びるはずだ、という実感みたいなものをジャムから勝手に学んでいた。
ジャムをきっかけに〈音楽を聴くのってけっこう楽しいんじゃないか〉と思いはじめた僕は、彼らが影響を受けていたモッズや、同時代に活動していたパンクバンドを聴くようになった。
2.Ramones “I Wanna Be Your Boyfriend”
そうしていろいろ聴いたなかでいちばん好きになったのがラモーンズだった。
そんなに怒ってない感じが聴いていてリラックスできた。クラッシュやピストルズも好きで聴いていたけど、やっぱりすごく怒っているのでこっちに元気がないときに聴くと滅入ってしまう。ラモーンズはそんなことはなかった。
なんでラモーンズにだけそう思うのか考えてみると、歌詞にあまりメッセージ的なものがないことが大きい気がする。政治のこととかほとんど言わない。皮肉とか暗喩がたくさん込められていると解釈している人もいるようだけど、僕はそうは思わない。たぶん基本的には何も考えずに書かれている。なにかの引用にもそのへんにいた馬を盗んだだけ、みたいな気軽さを感じる。
そのなかでもこの“I Wanna Be Your Boyfriend”はすごい。ほとんど何も言っていない。ヒットソングなんかが歌詞の中身のなさについて批判されることがあるけれど、これに比べればどの曲も立派なメッセージを背負っているんじゃないかという気さえしてくる。僕はこの曲を繰り返し繰り返し聴いた。
タイトルの通り直接的なラヴソングで、それ以上の情報はない。というかラヴソングですらないんじゃないかと思う。もう〈べつに書くことないからメロディーに合わせて適当にでっち上げよう〉ぐらいの凄みすら感じるほどの中身のなさだ。
僕は最初のほうこそ額面通りにラヴソングとしてこの曲を聴いていたけど、だんだん〈なんでこんなことを歌っているんだろう〉〈そしてこんなに中身のない曲を、なんで僕は何度も聴いているんだろう〉という考えが生まれてきた。
そうして千回ぐらい聴いたとき(本当に一時期これしか聴いていなかった。どうかしていた)、急に〈これは何もない、ということの表明なんだ〉〈何もメッセージがなくてもこうやって曲はつくれるんだ〉と気がついた。
たぶん当時の僕はこの曲の中身のなさからなにか大事なことが得られるんじゃないかと感じていて、それで何度も聴いていたんだと思う。〈大事なこと〉なんて思い込みでしかないんだけど、まあ解釈は人それぞれだし、実際に十四歳の僕はいまに至るまで使い続けることになる大切な地図をこのとき手に入れたのだ。
この気づきは、言いたいことや伝えたいことがないとものをつくってはいけないんじゃないか、と考えていた僕にとっては非常に新鮮な発見だった。このことに気がついたあと、僕はすぐにギターを買って曲をつくりはじめた。同じような経緯で楽器や作曲をはじめた人は、たぶん何万人といるだろう。ラモーンズは偉大だ。
3.Pavement “Cut Your Hair”
ここからしばらく曲というよりはミュージシャン自体についての話になる。
たぶんパンクからの流れでたどりついたのだと思うけど、中学生の終わりから高校を卒業するまでの三年間は90年代のいわゆるシアトルオルタナみたいなものをよく聴いていた。こうやって改めて振り返ると、あまりにもわかりやすく冴えない少年の王道を歩んでいて笑えてくる。でも当時は真剣に〈俺は世の人間のほとんどがわからないもののよさがわかるんだ〉とか思っていた。ほとんど病気だった。
ペイヴメントはシアトルのバンドではない(〈シアトルオルタナ〉なんてカタカナ8文字書いたのが馬鹿みたいだな)。でも90年代のアメリカのバンドではいちばん好きだ。ほかにはマッドハニーとかダイナソーJrとかが好きだった。ニルヴァーナももちろん好きだったけど、演奏とか作曲とかがあまりにも上手すぎて長い時間聴いてられなかった。このころからすでにへろへろの演奏や調子のはずれた歌に冴えない自分を重ね合わせるような、情けない音楽の聴きかたをしていた。
彼らは基本的にへろへろやってるだけなんだけど、力感のない演奏が続くなかで突然叫んだり、やたらと長尺なギターソロが挟まれたりすることがあって、それがギャグとしてやっているのかどうなのか判断に困るというか、とにかくズレたユーモアを感じさせる部分が随所にあって聴いていて飽きない。このへんが僕にとってのペイヴメントを特別なバンドにしているのかなと思う。
それとやる気のない感じが聴いていてとても安心した。〈こういう感じでバンドをやってもいいんだ〉と音楽性はともかく姿勢の面ではかなり影響を受けた。それがいいことかどうかはわからないけど。
オルタナの括りだとソニックユースなんかも聴くには聴いたけど、なんというか上手くハマらなかった。
聴いていると3D酔いみたいな感じになる。
あと同じ90年代の話でいくとイギリスの音楽(ブリットポップとか呼ばれてるものだ)もオアシス以外はよくわからなかった。オアシスは好き。
友人のちゃんとした、演奏や作曲の才能があるミュージシャンはみんなブラー派で、それもセルフタイトルのアルバムがいちばんいい(みんなギターがいいと言う)みたいな感じだけど、僕なんかは〈ブラーはそこそこ好きだけど『パークライフ』がいちばんで、あとはあんまりわからない。セルフタイトルのってあれブラーがやる必要あった?〉とか言って顰蹙を買いまくっていた。
ストーンローゼスもそんな感じだった。ファーストが好きで、セカンドはギターがカッコいい以外あんまりだと言っては呆れられていた。
僕は基本的にセンスが悪い。
4.Sparklehorse / Flaming Lips “Go”
5.Daniel Johnston “Go”
へろへろな音楽が好きなので、当然ダニエル・ジョンストンも好きだ。とてもわかりやすい。
〈ダニエル・ジョンストンの歌〉というベストアルバムがあって、これがなかったらいまとは音楽の趣味がちがっていたかもしれないとすら思う。というのもこのアルバムは二枚組で、一枚は普通のベスト盤、もう一枚がその収録曲を2004年当時のインディー・シーンを代表する(言い過ぎかも)ミュージシャンたちがそれぞれカヴァーしたものという変わった構成になっているのだ。
参加メンバーはティーンエイジ・ファンクラブ、ベック、イールズ、ブライト・アイズ、スパークルホース、デスキャブ(略す)、フレーミング・リップス、それからトム・ウェイツ(!)となかなかに豪華だ。はじめて知ったミュージシャンも多く、このアルバムをきっかけに聴く音楽の幅がすこし広まった。
このなかではスパークルホースとフレーミング・リップスがカヴァーした“Go”がいちばん好きだ。正直お互いのよさを消し合ってしまっているような曲もいくつかあるのだけど、トータルではすごくいいアルバムだ。こういう企画盤がうまくいくのはけっこう珍しいんじゃないか。
それからこのアルバムのすごいところは、カヴァーを聴いた上でダニエル・ジョンストンのオリジナルを聴くと、改めてそのよさを再確認できるところにある。ダニエル・ジョンストンはギターも歌も録音もしょぼくて、どう考えてもカヴァー陣のほうが力量的には優れているのに、聴いてみるとオリジナルのほうがいいなと思ってしまう。“Go”なんてサビの歌がはずれすぎていて不安になるぐらいなのに、やっぱりとてもいい(もちろんカヴァーのほうが好き、オリジナルは下手すぎて嫌だという人がいても驚かない)。音楽ってよくわからない。
6.Eels “Climbing To the Moon”
イールズは前述のダニエル・ジョンストンのベストアルバムで知った。もう十年ぐらい聴いているけど、いまだに〈いちばん好きなミュージシャンは?〉と聞かれればイールズと答えるし、〈いちばん好きなアルバムは?〉と聞かれたら『エレクトロ・ショック・ブルース』と答える。でもそのよさを言語化するのは非常に難しい。
僕がいちばん魅力的に感じるのは悲しさや寂しさの表現で、そこにはマーク・オリヴァー・エヴェレットが体験した個人的な出来事の影響が多分に含まれているらしい。でもその表しかたはとてもさり気なく、〈こんなにつらいことがあったんだよ〉といった同情を目的とした押しつけがましい擦り寄りは一切ない。自分の傷跡を見せびらかして満足するような卑しさとは遠く離れたところでその音楽は鳴っている。
ただ平気な素振りで歩いているだけなのに、その所作から感情がこぼれてしまうような、それでもなお淡々と歩き続けているような、そういう音楽だと思う。これは歌詞とかそういうところとはまたべつの話だ(むしろイールズの歌詞では〈個人的な出来事〉についてかなり直接的に描かれている)。自分が傷ついたときやすべてがわからなくなったときには、可能な限りこうありたいというような態度。だから信頼して耳を傾けることができる。いつだって不安といえば不安だ。
音楽を聴く目的というのは人それぞれで、さらにはそのそれぞれの人たちのなかでも複数の目的が同時に存在している。僕の場合そのひとつとして〈静かでやさしい隣人〉というものを求めていて、そこにイールズの音楽は綺麗に収まった。たぶんこういう出会いというのは人生でそう何度もあることではない。だから僕は迷いなくイールズがいちばんだと言う。そしてやっぱりこれはとても個人的な話なので、共感を得ることは困難かもしれない。
それでもバンドを組んで曲を作るというマーク・オリヴァー・エヴェレットと(仮に形の上だけだとしても)同じ行動を選択した以上、自分がイールズから感じた親しさを誰かに繋げていければと思う。使命なんて大げさなものではないけれど。
7.Wilco “Impossible Germany”
ちょっと真面目っぽい話をしたら身体が痒くなった。慣れないことをするもんじゃない。
基本的に出不精でライヴを観に行くこと自体少ない。海外のバンドだとなおさらだ。だけどウィルコの来日公演は観に行った。たしか2013年の春だったと思う。場所はいまはもうないSHIBUYA-AXで、人生でいちばんいいライヴだった。
最初から最後まで素晴らしいライヴで、序盤にやった“Art Of Almost”なんて聴きながら(観ながら)本当に同じ人間がやってんのかよと思った。そのなかでもやっぱり“Impossible Germany”は飛びぬけてすごかった。“Ashes Of American Flags”というライヴDVDで観られるヴァージョンも最高(YouTubeにアップされているのはたぶん違法アップロードだ)だけど、実際に観たものはその比じゃなかった。
とにかくめちゃくちゃに長いインプロがあって、ジェフ・トゥイーディーとネルス・クラインとパット・サンソンが交互にギターソロを弾きまくっていた。あれは何分ぐらいやっていたんだろう。ネルス・クラインがウインドミル奏法までやってくれたのはこの曲だったかちがう曲だったか。とにかくサーヴィス満点だった。
〈こいつらいつまでやってんだ〉という気持ちと〈ずっと続けてくれ。やめないでくれ〉という気持ちが同時に押し寄せてわけがわからなくなって、隣の岩井(うちのギター)と泣きながら大声を上げて笑っていた。すごいものを観ると、人間はめちゃくちゃになってしまう。
それからこのときの来日公演で印象に残っているのは、本編の終わりかアンコールで、スタッフ(マネージャーだかローディだかドラムテックだかギターテックだか)がステージに出てきて、服を脱いでカウベルを叩きながら踊りだしたことだ。けっこう長い時間踊っていたような記憶があって、しかもあんまり盛り上がっていなかった。
ウィルコみたいな素晴らしいバンドでもライヴで滑ることがあるんだ、と思い出すたびに勇気が出る。
そういえばウィルコもダニエル・ジョンストンの“True Love Will Find You In The End”をカヴァーしていた。これもとてもいい。
8.The National “Bloodbuzz Ohio”
ここ二、三年でいちばん聴いたのはナショナルかアーケイド・ファイアだ。アーケイド・ファイアはアルバム丸ごと聴きたいタイプの音楽なので、ここではナショナルを紹介する。
僕はナショナルを〈詩人一人と四人の優れたミュージシャンから成るバンド〉として捉えている。ヴォーカルのマット・バーニンガーは完全に詩人だ。風貌もそうだし、ステージでの立ち居振る舞いや眼つきもほかの四人とは全然ちがう。いいとか悪いとかの話じゃないところで違う。詩人だから歌はあまり上手くないけど、それは何もマイナスの要素にはならない。本人(たち)も気にしていないように見える。
“Bloodbuzz Ohio”は、どんどん前に進んでいくビートと最初はそこに淡々と言葉を置いていた歌とが、まずは並走し、歌に感情がこもるにつれて徐々に離れていくような不思議な感覚にさせられる彼らの代表曲だ。
去年アルバムを制作していたころは、定期的にナショナルを聴いて自分を鼓舞していた。なんというか、背筋をすっと伸ばしてくれるような音楽なのだ。
ナショナルはルックスもとてもカッコいいバンドで、全員四十代半ばから後半ぐらいの年齢だったように思うけどめちゃくちゃビシッと決まっていて憧れる。
とくにマット・バーニンガーは僕も歳をとったらああいう装いになりたいと思うほどなのだけど、髭の生えかたが寂れた海水浴場の砂浜みたいで汚らしいことこの上ないのでどうにもならない。本当に悲しい。
9.Jeff Phelps “Super Lady”
ここまでが過去の話で、これからは現在の話をする。現在、つまりいまこの文章を書きながら聴いている音楽のことだ。
りきまるくんという北海道で小説を書いている友達がいる。彼はちょっとどうかしているんじゃないかと思うぐらい音楽(特にソウルとR&Bとファンク。僕なんてこれらのジャンルの明確なちがいもわからない)に詳しくて、定期的にオススメを教えてくれる。僕もたまに教える。
ジェフ・フェルプスはそうして教えてもらったもののひとつで、最近のお気に入りだ。エレクトリック・ソウルというんだろうか、しょぼいリズムトラックや不穏な感じすらするシンセのなかで所在なさげに漂う歌がいい。夜の散歩のお供にするには、これ以上のものはなかなかないんじゃないか。
最近はこれ以外だとフォックスウォーレンのセルフタイトルアルバムか、ユーエス・ガールズの新譜をよく聴いている。どっちも去年出たアルバムだ。もう新しい音楽なんて現れないとか散々言われてるのに毎年ちゃんといいアルバムがリリースされるんだから、みんなとても偉いなあと思う。僕のこの目線はどこにあるんだろう。
10.Pom Poko “My Blood”
過去、現在ときたら未来の話をしたほうがいいだろう。そうすべきだ。人間は過去と現在と未来によって形成されると誰かが言っていたような気がする。言ってなかったような気もする。
ポンポコはノルウェーのバンドで「平成狸合戦ぽんぽこ」から名前をとったらしい。本当かよ。海外のインディーバンドのスタジオライヴをアップしているYouTubeチャンネルで知った。ポンポコはこのチャンネル内の動画で“You'll Be Fine”という曲を演奏していて、それを観て一発で好きになった。
聴いてもらえばわかると思うけど、なんというかアプローチが全体的に少しずれていてへんてこなバンドだ。少し、というのが重要で、なんとか一言で表そうとして言葉を探すのだけど、うまくいかずに〈ロックバンド〉としか言えないような、そういうなんともいえないもどかしい感じがある。そこが非常に好ましい。四人組のオーソドックスな編成なこともなんだか意味あり気に思えてくる。
ポンポコは今年の2月22日にファーストアルバムをリリースする。たぶん何度も繰り返し聴くアルバムになる。
以上。
こうやってまとめてみると、自分のしょぼい音楽遍歴にもしょぼいなりに物語が付属しているということがわかる。音楽には、それを聴いたりそれについて考えたりすることで、小さすぎたせいで掌からこぼれ落ちていった物語たちを思い出させてくれる、そんなタイムマシン的な働きがあるんじゃないだろうか。
そう考えたら、音楽を聴いたりバンドをやったりなんてしていなければもっとまともな人生が歩めたはずだ、などと毎日悲しくなっている僕のような人間と音楽との関係にも、なんかしらの価値や意味があるんじゃないかと思えてくる。
まあ気のせいか。
ここまで読み切った方は少ないと思いますが、イヴェントのご予約はメール、TwitterでのリプライとDM、LINE@、Messengerまで。お名前、人数、学割希望の方はその旨を明記のうえ、ご連絡ください。みなさまのご予約を待ちしております。梶原さんの抱腹絶倒のMCをお約束いたします。

Live Information
〈Mikiki Pit Vol. 7〉
2019年2月2日(土) 東京・下北沢 BASEMENTBAR
出演:毛玉/Crispy Camera Club/Half Mile Beach Club/So Sorry,Hobo
開場/開演:12:00/12:30
終演:15:00
料金:前売り 1,500円/当日 2,000円/学割 1,000円
フード:クジラ荘
>>チケットのご予約は
Twitter(リプライ、DM):https://twitter.com/mikiki_tokyo_jp
Facebook Messenger:m.me/mikiki.tokyo.jp
メール:mikiki@tower.co.jp もしくは ticket3@toos.co.jp まで
LINE@:
![]()

※各出演者でもご予約を承っております