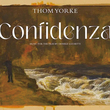本書の帯にはこんな文言が書かれている。〈20世紀最後の名盤『KID A』とは何だったのか〉。裏面はこうだ。〈僕はサウンドそのものを超えたところに『キッドA』を位置づけてみたい。僕が特にやってみたいのは、僕ら――オーディエンス、ファン、リスナー――みんなを議論に巻き込み、音楽を聴くという経験を社会政治的な重要性を持つ場として生き返らせ、好みの変化を通して自分たち自身についてさらに知ることができないか探ることだ〉。
この「レディオヘッド/キッドA」は、先に紹介した「J・ディラと《ドーナツ》のビート革命」と同じく〈33 1/3〉シリーズの一冊(ちなみに、同シリーズの訳書としては村上春樹訳の「ペット・サウンズ」がある)。そして著者は、音楽メディア〈Tiny Mix Tapes〉の編集長、〈Mr P〉ことマーヴィン・リンだ。彼が運営する〈Tiny Mix Tapes〉は、ヴェイパーウェイヴなどのアヴァンギャルドなエレクトロニック・ミュージックや文字通りの意味でのオルタナティヴな音楽を中心に批評するメディアで、オンライン・アンダーグラウンドに推進力を与えている場のひとつと言えるだろう。
そんな特異なメディアからも、あるいは〈ローリング・ストーン〉や〈ピッチフォーク〉、〈ガーディアン〉といった大きな媒体からも、そしてもちろん世界中のリスナーからも愛され、このうえない評価を得ているアルバム『Kid A』。2000年の10月にリリースされ、ある意味では21世紀のポップ・ミュージックを運命づけた同作とはいったいどんなアルバムなのか? 最初に引いた帯文のとおり、それに真っ向から向き合ったのが本書である。
イントロダクションは、著者の個人的な回想から始まる。彼がいかにレディオヘッドの音楽に心酔し、いかに〈新作〉『Kid A』に期待していたのか。まだ見ぬ『Kid A』の音楽が彼をどんな〈超越〉へと連れ去ってくれるのか――想像を膨らませながら、日付の変更とともに購入したCDを丁寧に、儀式的に再生し……そして彼は居眠りをした。そんなエピソードが綴られている。
もちろん本書は、リンが体験談を語ったつまらない本ではない。エレクトロニクスを大胆に導入したと言われるその音楽性や黙示録的な歌詞、リスニング環境の変化(CD、MP3、ストリーミング)、聴き手とメディアからの評価(リリース当時はかなりの批判にも遭った)、あるいは作品の政治性(環境問題、グローバリゼーション、新自由主義)など、多角的な視点から異形のクラシックを〈サウンドそのものを超えたところに〉位置づけようと試みている。その過程で読者はダダイスムや、制作中にバンド・メンバーが入れ込んでいたアクティヴィストのナオミ・クライン、そしてマーシャル・マクルーハンとジャン・ボードリヤールの思想にも出会うことになる(もちろん、メンバーの発言や当時の動向もたっぷりと読むことができる)。
……なんて書くと小難しくて、しかも音楽そのものとはまったく関係がない本に思われしまうかもしれないが、そうではない。「レディオヘッド/キッドA」が言わんとしていることをものすごく単純化してしまえば、つまり〈音楽を聴くことはとてもクリエイティヴなことなのだ〉ということになる。〈アーティスト〉が作った確固たる、不動の作品がそこにあり、私たちリスナーはそれを黙って受け取り、ただじっと耳を傾ける――音楽を聴くということはそういうことではないとマーヴィン・リンは論じている。
音楽を聴くことはかなり社会的な行為であるし、私たちの身体をも変化させ、もちろん精神的・感情的な変化も引き起こす。時間(本書を貫くテーマだ)に対する感覚が奇妙に伸び縮みしたり、あるいはそれまで見えていなかった風景が突然、見えてしまったりすることもある。かつては途中で居眠りをしてしまった『Kid A』が、ある日おそろしく刺激的な音の連続に感じることもある。音楽と聴き手との関係は常に変化し続け、その聴こえ方も変わり、言ってしまえば作品そのものも変容してしまう。本書のメッセージは、つまるところそういうことだろう。
日々、大量の新曲や新作を聴きながら、何かが違うと感じるときがある。10代の頃に〈狂気〉や〈勝手にしやがれ〉や『Kid A』を初めて聴いたときの、わけのわからない衝撃をもう一度感じることはできないのだろうかと思う。しかし、本書を読んで少し考えを改めた。音楽、作品とは何度でも出会い直すことができるのではないか? そう思って、『Kid A』をSpotifyで再生してみる。思っていたより地味で、アコースティックな響きが強調されていて、支離滅裂というよりは緻密で、そしてなにより美しいアルバムだと感じた。