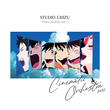ピアノの新しい〈Era〉 ~音楽の未来に出会うフェス~
ピアノはいつも新しい。最も身近な存在でありながら、どこか遠くへ導いてくれる存在だ。そして演奏家によって一旦音が放たれると、その人の背景が、その人の属している音楽文化までもが露わとなってしまう。それぞれの世界。それぞれの地平。タッチ、技術、リズム感覚、あるいはアンサンブルに対する感覚。聴衆は、それを理解し、その演奏を味わう。多数のピアニストが演奏してくれるのなら、楽しみもまた多様になる。
ザ・ピアノエラは、2013年から隔年で始まり、今年で4回目となるピアノのためのフェスティヴァルで、特定のジャンルに限定することなく、世界各地からトップ・レベルのアーティストが招致されている。皆、表面的には聴きやすいポップさがありながら、限りなく〈今〉を感じる深い実験性を内包している点では共通している、そんな世界的にも稀有なピアノ音楽のイヴェント。1日目、2日目、それぞれ3組が出演される予定だが、順番に見てみることにしよう。
アントニオ・ロウレイロは、『Livre』(2018年)の発表や、カート・ローゼンウィンケルのアルバム『Caipi』(2017年)の参加も記憶に新しい、2010年代以降のブラジル新世代を代表する多楽器奏者そしてシンガー。そもそも『Só』(2013年)などでも、ブラジル音楽の持つグルーヴと、同時代のマスロックやプログレッシヴロックの文脈を感じさせる変拍子を多用したテクスチャーと、ミルトン・ナシメントやMPBなどに由来する歌の情緒性の流れを共存させることに定評があったが、ローゼンウィンケルやマイク・モレーノなどNYのジャズシーンとの交流、さらにプロダクションにおける意識が高まったのだろう、『Livre』では歌がよりシャープに独立して聞こえるようになり、さらに洗練されたと評判だ。今回は初のトリオでの来日で、ベースとドラムのインテラクティヴな変拍子の重ね合わせの妙(とおそらく歌とのバランス)が冴え渡ることになると予想される。会場で演奏の拍子を感じながら体を揺らし、旋律を聴くとき、リズミカルなフローと感情表現の組み合わせの新しさに酔いしれることになるだろう。
モロッコとポーランドにルーツを持つユダヤ系の家庭に育ち、10代中盤でウィントン・ケリーとソニー・クラークに大きな影響を受けたニタイ・ハーシュコヴィッツは、クラシックの和声法、対位法、ピアノ演奏を音楽大学などの公的機関ではなく、個人的に教師に頼み込み師事した経歴を持つ。そんな彼にはどこか風通しの良い自由さと勤勉さがあったのだろう、やがて同郷のイスラエル出身の天才ベーシスト、アヴィシャイ・コーエンのトリオのピアニストに抜擢される。コーエンは、ジャズ文脈にクラシック音楽と中東の民俗音楽の要素を取り入れることで知られ、以前このトリオのピアニストだったシャイ・マエストロに代表されるようにイスラエルとジャズをめぐる、一つのシーンの源泉となっており、当然ながらハーシュコヴィッツもそれを継承している。『New Place Always』(2018年)では、ドビュッシーが中東音楽の影響を受けて作ったかのような曲もあり、コンポーザーとしての手腕も発揮している。またジャズのコードの使用は、気を衒うことなくシンプルであり、メランコリックで落ち着いた抑制美の演出に成功している。と思えば最新作『Lemon The Moon』(2019年)においてビートメイカーのRejoicerをフィーチャリングし、ネオソウル的なキーボードワークを見せた。当日の演奏はおそらくアコースティック寄りで耽美的なアプローチになるかと予想されるが、意外とビートものも聴かせてくれるかもしれない。
南アフリカ生まれのカイル・シェパードは、アブドゥーラ・イブラヒムやダラー・ブランドなどを思わせる、ダイナミックで熱く、スペイシーな音楽も奏でることができることから、まだ30歳を少し超えたばかりの若さでありながらアフリカピアノの継承者との呼び声が高い。しかし旧来のアフリカ音楽のイメージばかりを想像するのは早急で、国際的な感覚が豊かな若者らしく、よりクラシカルなキース・ジャレットやエスビョルン・スヴェンソンにも影響を受けているのは当然として、アフリカ音楽にモダン的なアプローチをするリオーネル・ルエケらとの交流もあり、常に伝統のアップデートについて考えているとのことだ。また、ドラマーであるクロード・カズンスとのトリオ(例えば『Jubileejam』(2014年))では、洗練されたアフリカン・ジャズを聴かせていた。今回の来日ではそのクロード・カズンスと日本人ベース奏者の松永誠剛とのトリオとなるが、どのようなアプローチになるのか楽しみだ。
アメリカのペンシルヴァニア出身のゴールドムンドは、バークリー音楽大学で打楽器を学んだキース・ケニフによる、ピアノ・ソロがメインのプロジェクト。美しいピアノのタッチと、控えめな音数やアルペジオでハーモニーを彩ることに非常に長けており、そこへシンセや電子音響的なアプローチを最小限入れることでポスト・クラシカル的なプロダクション的な加工がなされている。本名名義のプロジェクトではすでにGoogleやAppleなどのCMで楽曲が使用されるのが納得できる力量を持っている。今回は、そんな彼の、ゴールドムンド名義での生演奏に触れるレアな機会となる。煌めくような明るさを持ちながら、どこから落ち着いた静謐の美の空間へと聴衆を誘うことだろう。
ポーランド人のハニャ・ラニは、北部のバルト海に面した湾都市グダンスクに生まれ育ち、現在はワルシャワと勉学のために住んだベルリンを行き来するという。初めはクラシック音楽から入り、やがて音楽学校でジャズや電子音楽にも興味を持ったという彼女は、〈ショパンやショスタコーヴィチを、デーヴ・ブルーベックや(電子音楽の)モデラートを混ぜ合わせる〉野心さと茶目っ気を持ち、さらにマックス・リヒター、ニルス・フラームも聴くという。『Biała flaga』(2015年)では、同世代のチェロ奏者ドブラヴァ・チョヘルとのデュオを結成、チェロを立ててあくまで音楽をトータルで捉える編曲家としての力量が光ったが、今年になってゴーゴー・ペンギン他を擁するUKのレーベルGondwanaよりリリースされた新作『Esja』は、繊細なテクスチャーで作られたピアノ・ソロ作品ながら、その変遷の仕方に時折ショパンを思わせる伝統的な重みと、アンビエント的な雰囲気が絶妙に混ざりあい、彼女が内面化してきた音楽の多層性が感じられるのが興味深い。
そして唯一日本人のピアニストとして選ばれ、連続4回の出場となるのが高木正勝。近年は第91回米アカデミー賞の長編アニメーション賞部門でノミネートされた「未来のミライ」など、多くの細田守作品の映画音楽などを手がけつつ、自然の里山での生活の中で、音楽を作る意味や、音楽と自然の中での関係性を日々捉え直しているようだ。ソロ作品の『Marginalia』(2018年)は、自然音とピアノの豊かな関係性を描くことを試みた作品だった。ここまで妥協せずに日々の生活の中で音楽に向かい合っている人もそう多くなく、国際性豊かなフェスティヴァルの中で、彼にしか表現できない日本の世界を見せてくれるだろう。
LIVE INFORMATION
ザ・ピアノエラ2019
2019年11月30日(土)
開場/開演:16:15/17:00
出演
アントニオ・ロウレイロ・トリオ:Antonio Loureiro(ピアノ、キーボード、ヴォーカル)、Frederico Heliodoro(ベース)、Felipe Continentino(ドラムス)/Brazil
ニタイ・ハーシュコヴィッツ:Nitai Hershkovits/Israel
カイル・シェパード “A Portrait of Home” :Kyle Shepherd(ピアノ)、Claude Cozens(ドラムス)、Seigo Matsunaga(コントラバス)/South Africa、Japan
2019年12月1日(日)
開場/開演:15:45/16:30
出演
ゴールドムンド:Goldmund/USA
ハニャ・ラニ:Hania Rani/Poland
高木正勝:Takagi Masakatsu/Japan
会場:めぐろパーシモンホール 大ホール
www.thepianoera.com