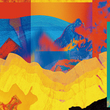世界中が不安で包まれ音楽活動もままならないなか、ロック・バンドはどうしたらいいのか。それぞれがヘヴィな課題を突きつけられるなか、ROTH BART BARONが出した答えが新作『極彩色の祝祭』だ。レコーディング直前にオリジナル・メンバーの中原鉄也(ドラムス)が脱退する、という重大な出来事に見舞われながら、岡田拓郎ら10名を超えるメンバーが最善の注意を払ってスタジオに集まって一緒に音を出す。そして、そこで生まれたエネルギーを彼ららしい物語性と美意識でまとめあげたアルバムは、バンドの新しい出発を告げるような素晴らしい作品に仕上がった。
コロナ禍のなかでも歩みを止めず、配信ライブや有観客と配信でツアーを開催するためのクラウドファンディングなど様々な働きかけをしてきた彼らは、どんな想いでアルバムを作り上げたのか。バンドのフロントマン、三船雅也(ヴォーカル/ギター/その他)に話を訊いた。
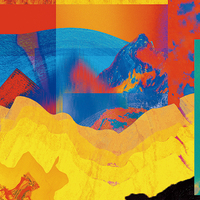
ライブができないからってミュージシャンが休んでいいのか?
――前作『けものたちの名前』(2019年)で取材した時に、三船君は「2020年は何か大きなことが起きそうな予感がする」と言ってましたが、まさにその通りになってしまいましたね。
「そうですね。この数年、日本だけじゃなくて、世界中でいろんなことが起こっていて、ちょっとしたことでドミノ倒しみたいに世界が崩壊してしまうかもしれない、そんな張り詰めた緊張感が漂うなかで音楽を作っていることは常に意識していたんです。でも、対立関係にある人間を両成敗するような、完璧な破壊者としてウィルスが登場するとは思ってもみなかった。街からトイレットペーパーが消え、映画館やライブハウスが危なくなり、近所の商店街の馴染みの居酒屋が閉店するのを見ると、さすがに明るい気持ちにはなれなかったですね」
――どんどん生活圏内にコロナの影響が及んできた。
「でも、居酒屋として店が開けないなら仕入れた野菜を店頭で売ろうとか、自粛要請が出ているなかで光を見出そうとしている人たちの姿を見て励まされたりもしていたんです。そんな風にいろんな人が頑張っているのに、〈ライブができないからってミュージシャンが休んでていいのか?〉って。自分は常に人類が危機的な状況に置かれても聴ける音楽を作ってきたつもりだったし」
――新しいアルバムを作らなくていい理由はない、ということですね。
「でも、人と会うことを禁じられているなかでセッションするのも難しいし、どうするかは悩みましたね。何が危険で何が安全なのか、データもあまりない状態だったし。だから、最初はリモートで作るというアイデアもあったんですけど、人がなかなか会えないいまだからこそ、同じ空間に人が集まって音を出すというプリミティヴなエネルギーを、アルバムに閉じ込めることができるんじゃないかと思ったんです」

at 札幌 芸森スタジオ

at 東京 DUTCH MAMA STUDIO
オリンピックも開催できない時代、人は何を祝うのか
――人が集まって音を出す、まさに〈祝祭〉ですね。
「例えばフェスってコアにあるものが何かわからないじゃないですか。みんな音に喜びを感じるのか、集まることに喜びを感じるのかわからないところがある」
――確かに人が集まるだけで興奮状態になりますよね。みんなが共鳴し合うというか。
「一人踊り出すとみんな踊り出す。その伝染力が祝祭のエネルギーを生み出していて、それってみんなが不安に駆られてトイレットペーパーを買い出すのと同じ作用が働いているんですよね。だからコロナにまつわるパニックも一種の祭りと言えるかもしれない。さらにオリンピック関連の動きや、新製品を買わせるための宣伝の煽りもそう。経済も祝祭の力を使っている。でも、コロナで経済活動がストップしてオリンピックも無くなってしまうかもしれない時に、人間は何を祝うんだろう?ということに興味があったんです」
――本来、祝祭はどういうものだったのか、という問いかけをしたかった?
「そうです。人間の喜びって、単に新しい商品を買うことじゃなかったはず。いまフェスは整った音響システムを通じて音楽を楽しむ集まりになっていますけど、本来はみんなで太鼓を叩いたり、歌ったりするだけで楽しかったんじゃないかって思うんです。そういう根源的な喜びを取り戻すことが、いま人類にとって必要なことなんじゃないかって、前作を作っている時に考えていました。それで〈祝祭〉という言葉が頭に浮かんで、紙に書いて家の壁に貼っていたんです。アルバムを作る時、〈祝祭〉という言葉はキーワードとしてバンド・メンバーのみんなと共有していました」
――祝祭の意味を考えるというのは、音楽の生まれた理由を考えることでもあるかもしれませんね。実際にみんなでスタジオに集まって音を出してみてどうでした?
「みんなと一緒に音を出すのは久しぶりだったので、初めてバンドを組んだ時の気持ちになりましたね。楽器を弾いて音を出す、というシンプルな喜びをみんな感じていた。これまで普通だと思っていたことが特別なことになったので、楽器を弾いたり、音を聴いたりする感覚が、これまで以上に研ぎ澄まされたなかでレコーディングしたんです。それぞれが出す音に、みんなが〈それ、すごくいい!〉って盛り上がって、〈大きな音って楽しいね〜〉って小学生みたいに無邪気に楽しんでましたね」