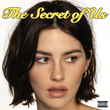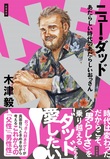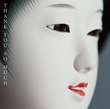村上春樹を愛読? 知的でポップなマット・バーニンガーの歌詞
――ザ・ナショナルは歌詞が高く評価されているバンドです。マットのリリシズムについてはいかがですか?
木津「僕は、2000年代半ばは『Michigan』(2003年)や『Illinois』(2005年)をリリースした頃のスフィアン・スティーヴンスに近い感覚で聴いていました。ラスト・ベルト※で生きる人々の悲哀とアメリカ文学的感性を接続させて、ロックでどう表現するかに挑んでいたのがスフィアンです。
一方ザ・ナショナルはといえば、地元オハイオの名を冠した“Bloodbuzz Ohio”(2010年)は〈NYに住んではみたものの、オハイオの保守的な感性が俺の血には流れているんだ〉というような歌だと僕は解釈しています。そこにザ・ナショナルがアメリカで成功した理由があると思うんですよね。つまり、アメリカという国で生きること、その引き裂かれた複雑な感情をロックで文学的に表現している。そういう文学性は初期作品では未完成なのですが、芽生えてはいますね」
岡村「ラスト・ベルト的感覚や文学性という点で、セカンドの収録曲“Murder Me Rachael”にはアメリカン・ゴシック的な田舎の陰鬱さや血生臭さ、ダークな死のにおいが表れていますよね。あの独特の情緒が米国内のある地域やある世代の人々にヒットするのは、よくわかります」
木津「ただおもしろいことに、歌詞を書いているマットは意外にも文学青年ではなかったそうです。その代わりに、ニック・ケイヴやボブ・ディラン、レナード・コーエン、R.E.M.のマイケル・スタイプの歌詞が好きで読み込んでいたのだとか」
岡村「奥さんのカリン・ベッサーがジャーナリストですし、適度な上昇志向とインテリっぽさがあるんですけど、それだけではないと」
木津「マットは知的だけど、アカデミックというよりはポップな感性の持ち主で、僕が取材したときは〈ハルキ・ムラカミ〉と名前を挙げていました。日本のジャーナリストへのサーヴィスもあったと思いますが、〈ああ、村上春樹を読むタイプ!〉って思ったんです(笑)。そこも彼のポップさに繋がっていますね」
――マットの歌詞はどこか大衆小説的というか、俗っぽいパルプ・フィクション的なムードがありますね。
岡村「最初から老成していた部分があって、いい意味でおっさんっぽいといいますか(笑)。その気取らない良さが、ザ・ナショナルが〈ダッド・ロック〉としても評価される理由ですね」
――マットはファーストをリリースした2001年の時点で30歳でしたし。
木津「セカンドでは歌詞に〈ハズバンド〉と〈ワイフ〉という言葉がたくさん出てくるように、マットのリリックって中年夫婦のすれちがいなどを描いているんです。でも、私小説的にはならずにフィクショナルに描く。フレッシュな恋愛ではなく、年を重ねた者どうしの関係性だからこそ抱え込む難しさを初期から描いていたのは、マットがバンドのスタート時から若くなかったがゆえでしょうね」
岡村「そういえば、木津くんと初めて会ったザ・ナショナルの初来日公演(2011年)で……」
木津「そうだ。初対面がザ・ナショナルのライブでしたね(笑)」
岡村「あのとき何がおもしろかったって、他のメンバーはみんなラフな格好なのに、マットだけ三つ揃いのスーツでキメていたこと(笑)。お酒が入ったグラスを手に持ってステージに出てきたんですよね。粋な男って感じで」
木津「“Bloodbuzz Ohio”のビデオのあのまんま(笑)。あれはアメリカのダンディーな男のパロディーではあるんですけど、マット本人もまんざらではないのでしょうね。僕のフェティシズムにヒットしたのは完全にそこで、彼が醸している中年男の悲哀です(笑)。それを、あれだけ丁寧な音楽性と高い文学性で見せてくれるバンドはそういません。
その哀愁はジョージ・W・ブッシュ政権下の時代精神を反映していましたし、オバマが“Fake Empire”を大統領選のキャンペーン・ソングに使ったのも、〈虚構の帝国〉という言葉が、当時のリベラルが置かれている状況と重なったからだと思うんですよ。そういった意味でも、ザ・ナショナルが2000年代後半以降に高く評価されたのは必然的でした。
また、2000年代後半はアメリカが閉塞していくなかでアメリカーナ系のアーティストたちが〈私たちはどこから来たのか〉を見つめ直していて、ザ・ナショナルはその動きともリンクしていたと思います」