Cuusheの復活劇は2020年の大きなサプライズだった。5年ぶりに届けられたニュー・アルバム『WAKEN』では、白昼夢のようにゆらめく音像に加えて、ビートが心を解き放つように力強く鳴っている。過去に縛られることなく、夢の世界に逃避するのでもなく、目の前の現実に立ち向かおうとする彼女の凛々しさ。勇気あるカムバックにあらためて拍手を送りたい。
2021年3月10日には『WAKEN』のリミックス集も発表された。音楽の消費スピードが加速し、1週間前のリリースを遠い昔の出来事みたいに錯覚しがちな時代だからこそ、特別な作品はしっかりと語り継いでいくべきだと思う。アーティストについても同様で、Cuusheという存在はもっと語られるべきだ。彼女みたいな音楽家は、世界中のどこを探しても他にいないのだから。
それにしても、Cuusheは不思議なミュージシャンである。京都出身の彼女は、パーソナルな音楽づくりの手段としてDTMを選び取り、シンガー・ソングライターとトラックメイカーの境界線を中和させながら夢見心地のサウンドを作り上げてきた。その才能は所属レーベルの〈flau〉と共に海外からも注目され、インタビューも数多く受けているはずなのに、いまだ謎多き存在だとも言える。そのミステリアスさが本人の世界観ともマッチしていたわけだが、『WAKEN』で新しいチャプターに突入したことを思えば、いまこそ彼女の歩みを振り返るべきタイミングなのかもしれない。
そこで今回は、彼女がどのようなミュージシャンで、どういった人生を歩んできたのか、今日までのパーソナル・ヒストリーを纏めることにした。よってこの記事は、これからCuusheの音楽と出会う人々のために、いつまでもCuusheの音楽を祝福し続ける人々のために、ウェブ上で長くアーカイヴされることを前提に制作されたものだ。本人へのメール・インタビューでは、僕自身も知らなかった話をたくさん教えてもらった。彼女の核心に触れるような内容になったと思う。
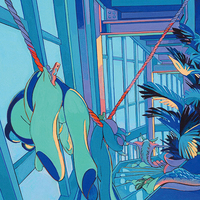
生い立ちと音楽の原体験
まずはCuusheが音楽を作りはじめるまでの話。家で流れていたのはクラシックやオールディーズ。幼稚園の頃からピアノも習っていたという彼女は、クリスチャンの母に連れられ、教会の日曜学校に通いながら賛美歌を歌っていたという。清らかで存在感のある歌声のルーツがここからも窺えるだろう。
――幼少期の音楽体験について振り返ってもらえますか。
「母が地域の公民館でやっているコーラス・グループに入っていたので、その練習や発表会で私も早くから歌に触れていました。私はとにかく歌うことが好きで、学校の休み時間や帰り道に歌を歌っているような子どもでした。京都の山の中で育ったんですが、当時ネバーランドというライブハウスで歌う機会があり、スタッフの方に〈いい声をしてるから歌を続けたほうがよい〉と褒められたのがすごく記憶に残っています」
――その後は?
「大学で入った軽音サークルになかなか癖のある人たちが多くて。そこで遠藤賢司や浅川マキ、ハービー・ハンコック、メデスキ・マーティン&ウッドやパット・メセニーといった音楽を教えてもらいました。特によく聴いていたのはブリジット・フォンテーヌ。サークルの同期にはモーモールルギャバンのメンバーや、『Red Rocket Telepathy』(2009年のファースト・アルバム)のリリース・パーティーでドラムを叩いてくれた城戸紘志くんなどがいました」
――そこから、エレクトロニック・ミュージックを手がけるようになったきっかけは?
「そういった音楽は、留学先のカナダでDJスプーキーを知ってから興味を持ちました。サークル内でバンドも組んでいたんですが、もともと人との意思疎通が苦手で、自分の思うようにできなくて。その頃にDTMというもので一人でも音楽を作れることを知って、機材を集めて宅録をするようになりました。そこが一つのターニング・ポイントですね。大阪のタワレコとかに通うようになり、竹村延和やボーズ・オブ・カナダを知ったのもその頃です」

Cuusheとして世に出るまでの物語
2008年頃からソロでの音楽製作をスタートさせたCuusheは、ロンドンで暮らしていた2009年に最初のアルバム『Red Rocket Telepathy』を発表。前述のボーズ・オブ・カナダやラルトラ、フィッシュマンズから影響を受けつつ、この頃から自分だけの個性を輝かせていた。彼女のドリーミーな世界観はどのように育まれたのか? ルーツをさらに掘り下げつつ、デビューまでの歩みを振り返ってもらった。
――〈Cuushe〉という名義は、いしいしんじの本「麦ふみクーツェ」が由来だと聞きました。
「大学時代に『ピーターラビット』のビアトリクス・ポターなどを学んでいたこともあり、児童文学に興味がありました。『麦ふみクーツェ』は大人のための児童文学のような小説で、社会とうまくつながれない存在の何か、この本では通奏低音のような一つの存在が主人公の〈ぼく〉を支えていく――かなりピュアな物語で、当時の自分にはしっくりきました。名前については『麦ふみクーツェ』もそうだし、クーシェはフランス語のcoucher(=眠る)みたいにも聞こえるから、それが決め手になりました」
――音楽以外の表現で、自分に影響を与えた作家や作品を挙げてもらえますか。
「リチャード・バックの『かもめのジョナサン』、サン=テグジュペリの『星の王子さま』、魚喃キリコの『Blue』、吉本ばなな、ミランダ・ジュライ、聖書」
――レーベルのflauからデビューすることになったきっかけは?
「関西から東京に出てきて、BULLET'S(西麻布のラウンジ・スペース、2018年に閉店)で初めてライブをしたとき、観に来てくれた方から〈Our Bubble Hour〉というイベントに誘われて。その方の知り合いだったflauのオーナーが誘ってくれてデビューすることになりました。その際にいくつかのレーベルからお誘いがあったんですが、flauの音源を聴いてみたらGeskiaさんがメチャクチャかっこよかったので、それで決めました」
――『Red Rocket Telepathy』の制作背景について教えてください。

「レーベルと契約した頃は(自作曲が)まだ3曲ぐらいしかなくて、そこからアルバムを作っていきました。1曲ピアノをスタジオ録音した以外はすべてホーム・レコーディング。イギリスで録音した音や、映画の音を取り込んで音階にしてみたり、フィールド・レコーディングをたくさん使用したりしました。DTMを知ったことで何でも一人で自由にできるけど、自分の音ってなんだろう、と思ったときにそういう工夫が必要でしたし、機材の使い方も全然わかっていなかったので、とにかくいろんな実験をしていました。
振り返るとこの頃は、〈ぼく〉と〈君〉だけの空想の世界が、現実に滲出していくようなものを作っていたんだと思います。いまもそうですが、音楽制作は現実からの逃避であり、ある種カタルシスのようなものです」
――2008~2009年にかけて、ロンドンで暮らしていたそうですね。
「母はイングリッシュ・ガーデンが好きで、イギリス映画もよく観せてもらってました。前述した通り大学でも英文学を学んでいたので、イギリスで暮らすことは一つの夢だったんです。残念ながら滞在時はほとんど家でカンヅメになって制作に没頭していましたが、テート・モダン(ロンドンの現代美術館)が近くにあったのでよく通っていました。その辺りでフィールド・レコーディングした音が、『Red Rocket Telepathy』ではたくさん使われています」






























