
ここに掲載するインタビューは、旧東ドイツ出身のピアニスト、ヘニング・シュミートが2021年9月にリリースしたピアノソロアルバム『Piano Diary』に合わせて、音楽ライターの小室敬幸が行ったものだ。ところが諸般の事情で発表タイミングでの公開ができず、この度『Piano Diary』の姉妹編的な作品『Piano Miniatures』の完成を機に、Mikiki編集部による追加の質問を加えた形で陽の目を見ることになった。
当初の予定より公開は遅れてしまったが、小室が丹念に訊き出したシュミートの音楽半生、エレクトロニックミュージックへの関心やポストクラシカルを含むクラシック音楽への批判的な眼差しなど、いま読んでも興味深い内容になっている。インタビューを通して、シュミートの哲学に触れていただきたい。そして、パンデミック下の静かな生活をエレガントな調べで描いた『Piano Diary』と子ども時代の思い出を音に映した『Piano Miniatures』に耳を傾けてほしい。 *Mikiki編集部

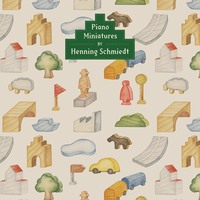
バッハ、ショスタコーヴィチ、キース・ジャレット――若きシュミートが感銘を受けた音楽家たち
――ヘニング・シュミートさんの音楽は特定のジャンルで括ることができないものですが、これまでにどんな音楽に魅せられ、影響を受けてきたのでしょうか?
「私は(チェコとの国境線に近い)ドイツのエルツ山地にある小さな町で、牧師の息子として育ちました。音楽文化に活気があったこの街には、巨大なオルガンを備えた結構大きな教会があって、ヨハン・セバスティアン・バッハのモテット、オラトリオ、カンタータなどを4歳から礼拝で聴いたり、7歳からは児童合唱団の一員として歌ったりしていました。同じ頃からピアノも弾くようになったので、徐々にいろんな曲を演奏しましたね。バッハの音楽はいつも私の周りにあったんです。
きっと私だけでなく、多くの音楽家がバッハの音楽に対して、精密さと数学的な必然性に魅了されているはずです。細部に至るまですべての声部が完璧に作り込まれたポリフォニー(多声音楽)の驚くべき複雑さには、目を見張るものがありますから。加えて、バッハの音楽がもつ曲がりくねったハーモニーや、彼のメロディーを動機(モチーフ)として理解することは、私にとって癒やしであり、健康によいのです。感情的に揺さぶられる、深くて崇高な自己像をもたらしてくれます。
特に好きなのは“平均律クラヴィーア曲集”や“ゴルトベルク変奏曲”(できればグレン・グールドの録音で……)、“クリスマス・オラトリオ”に“マタイ受難曲”、カンタータなら“主よ、人の望みの喜びよ”や“神の時こそいと良き時”など。あとは、オトマール・スイトナー指揮のベルリン・シュターツカペレで聴いた4つの管弦楽組曲や、6つのブランデンブルク協奏曲ですね」
――他にも若い頃、特に大きく心を震わせた音楽はありますか?
「12歳のときにとても感動したのがショスタコーヴィチの交響曲第7番“レニングラード”(1941年)です。第二次世界大戦のさなか、ドイツ軍に包囲されて飢餓の危機に陥ったこの大都市の運命が、音のドキュメントとして凝縮されています。スターリンの独裁政権下でルールを覆しながら生き延び、適応していった芸術家であるショスタコーヴィチに、私は常に魅了されてきました。
何故なら、私も人生の最初の20年間は鉄のカーテンの向こう側にあった独裁国家(東ドイツ)で生まれ育ったからです。その頃から私は平和運動に積極的で、共産主義の青年・準軍事組織への参加を拒否し、軍隊での兵役も拒否しました。当時は東西に分割されていたドイツ、どちらにも核兵器が配備されていて、冷戦が全世界にとって差し迫った脅威であると感じられる時代でした。
今でも私にとって音楽における自由や自己決定による創造性といった考えは、非常に重要なものなのです。そして、シェーンベルクの系譜を継ぐ無調音楽やセリエル(音列)音楽に対して、ショスタコーヴィチは調性音楽を書き続けた作曲家でもありました。私はメロディーや音楽の動機(モチーフ)が作曲家の本質であり、〈指紋〉になりえるものだと信じています。
あと、作曲家ではありませんが、偉大な指揮者でありヒューマニストであるクルト・マズア(1927〜2015年)は私の家族と親しく、音楽について多くのことを教えてくれました」
――クラシック音楽以外では、キース・ジャレットの音楽に若い頃から感銘を受けてきたそうですね。
「キース・ジャレットのサウンドがバッハと同じように私を感動させたのは、14歳の頃でした。彼の音楽からは、偉大で崇高な癒しの力が発せられていると思います。彼ほど、信じがたいほどに素晴らしい流れを持った演奏ができる人を知りません。音楽的視野は息を呑むほど広く、バッハのように複数の声部で即興演奏をすることができます。即興演奏では賛美歌、ゴスペル、ジャズ、バッハのフーガ風であったり、ジャンルとジャンルの間を難なく行き来することができますが、彼の音楽は常に均質で本物であると感じられるんです。アルバムでは『Bremen / Lausanne Concert』(73年)、『Belonging』(74年)、『My Song』(77年)、『Standards Vol. 1』(83年)、『Sun Bear Concerts』(76年)などが好きです」

ジャズやフュージョンの演奏を経て、クラシック/現代音楽の作曲家ミキス・テオドラキスと出会う
――その当時、10代半ばの頃は、ご自身の演奏・作曲活動としてはどんな経験をされていたんですか?
「80年、14歳ぐらいからバンド活動を始めたのですが、参加したバンドが持っていたARPやミニモーグなどのシンセサイザーを試すことができました。これらの楽器は希少で高価なものであり、闇市でさえ簡単に購入できません。というのも西側の楽器を買うための通貨(ドルやドイツマルクといった外国貨幣)を使うと法律違反になるため、危険だったんです。
そうでした、初めて自分のものとなったシンセサイザーは、CASIOのMT-31(81年発売)で、とてもチャーミングで、かわいいお供になってくれましたね。84年には西ドイツに住む祖父母がKORG POLY-61(82年発売/デジタル制御されたオシレーターを持つハイブリッドなアナログシンセサイザー)を送ってくれました。85年にFM音源のデジタルシンセサイザーであるYAMAHA DX7(83年発売)を手に入れたときは、何週間も夢中になって新しいサウンドをプログラムしましたよ。
当時の私はジャズがやりたかったので、85年に(ジャズギタリストである兄のヴォルフスブルクが先に加入していた)卒業したての音楽学生による〈East Berlin Guest Orchestra College〉というジャズ編成のオーケストラに加わりました。87年にベルギーのブリュッセルで国際フェスティバルの賞を獲得できたことで、奇跡的に諜報機関の承認がおり、私は海外旅行ができるようになりました。この頃は(80年代の)マイルス・デイヴィス・バンドやラウンジ・リザーズのようなスタイルで、私は主にシンセサイザーを弾いていたんです。だけどバンド活動をやめてからは、ライブでキーボードを演奏することはなくなってしまいましたね」
――ここまで聞かせてくださったように、もともとはジャズやフュージョン的な音楽を演奏していたシュミートさんですが、クラシックや現代音楽の世界で知られているギリシャの作曲家、ミキス・テオドラキスと共演するようになったのには、どのようなきっかけがあったのでしょうか?
「オリヴィエ・メシアンやピエール・ブーレーズ、イアニス・クセナキスにも師事していたテオドラキスは、独裁者に政治的抵抗をしたことや、映画『その男ゾルバ』(64年)の音楽を手掛けたことで有名です。ベルリンの壁崩壊(89年11月9日)のあと、彼は90年に東ベルリンにやってきて、スタジオでアルバム『Theodorakis Sings Theodorakis』をレコーディングしたのですが、このときに友人からセッションピアニストとして手伝ってくれないかと頼まれたんです。
熟練した指揮者であるミキスは、歌っているときにも指揮をする習慣があり、彼と一緒に演奏するのはとても自然で簡単でした。その3か月後、ミキスのヨーロッパツアーに参加しないかという電話がかかってきて、それから数年ほど海外ツアーのピアニストを務めました。当時、彼はギリシャで大臣を務めていたので、ボディーガードも付き添っていましたね。
95年にはミキスから未発表の自筆譜を渡されたんです。私はその旋律を編曲するだけでなく、アンサンブルのリハーサルを行ったり、レコーディングをしてくれるスタジオとレコード会社を探したりもしました。その後も、彼のためにたくさんのアレンジやアルバムでの演奏をさせてもらいましたね」

――シュミートさんは彼の音楽のどんなところに惹かれ、影響を受けたのでしょう?
「私の見解では、おそらくテオドラキスこそが20世紀で最も重要なメロディスト(旋律作家)なのです。交響曲、オペラ、オラトリオ、たくさんの歌曲、劇場音楽、映画音楽、フォークミュージック、更には電子音楽まで……。想像しうるあらゆる分野に彼は音楽を残しているのですが、それらの音楽は、古典的なヨーロッパの交響楽、古代ビザンチンの音階、活き活きとしたギリシャの民謡などが源泉になっていました。
彼と一緒に仕事をしてみると、旋律と歌詞に手を入れることは絶対に許されないのですが――それはテオドラキスの音楽において不変の真髄なのです――、それ以外はまったく禁止事項がなくて、彼の心の広さとどこまでも任せてくれることに心を奪われました。このコラボレーションの好例といえるのが、ミキスが最初の若書き作品をみずから歌ったアルバム『First Songs』(2005年)で、彼の連作歌曲を私がピアノとチェロのために編曲したアルバム『East Of The Aegean』(2008年)でも同じことがいえます」































