
SIMON SAYS
ツアー活動から引退しているポール・サイモンがステイホーム期に生み出した待望のニュー・アルバムは、7つの楽章で構成された『Seven Psalms』。全曲を作り手の意図通りに聴くことでそこに浮かび上がってくる光景とは……?
2018年のワールド・ツアー〈Homeward Bound -The Farewell Tour〉をもってツアー活動から引退したポール・サイモン。その終了と同時に発表されたアルバム『In The Blue Light』は室内楽のアプローチ中心に過去の自身の楽曲をセルフ・カヴァーした作品で、その揺るぎない美しさはキャリアの最終章に向かうレジェンドの穏やかな表情を窺わせるものでもあった。それから5年の歳月を経て届いた通算15作目となるソロ・アルバムがこのたびの『Seven Psalms』である。新約聖書の〈七つの詩篇〉に着想を得た内容はタイトルが示す通りで、昨年ニック・ケイヴが同名のスポークン・ワード作品を出していたものだが、今回のポールは全7つの楽章を1トラックに収め、トータル33分を曲順通りにひとつの組曲として聴いてほしいという意図を押し出している。いわば『Lovesexy』仕様(?)の構成となっているわけだが、歌とギターの素朴な連なりやメロディーの移ろいに耳を傾けているうちに知らず知らず聴き通せてしまうシームレスな雰囲気の作品になっているので、その部分に特段の面倒さを感じる必要はまるでない。
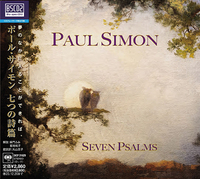
本人の〈この作品は信仰に関する私自身との対話でもある〉というコメントも出されているように、〈七つの詩篇〉というタイトルは新約聖書から単に形を借りただけではない。オープニングを飾る楽章で随所に登場してくる“The Lord”では彼なりの主(神)の姿が万物に宿るものとしてさまざまに歌われている。ただ、なかには〈コロナウイルス〉や〈波立つ海〉〈振り下ろされる剣〉も主であると見なすなど、当然ながら一面的に神を善きものとして賛美しているわけではなさそうだ。その楽章では冒頭から20世紀初頭の黒人の大移動が歌われるなど、パンデミック期の混乱の日々を経て改めて〈アメリカ〉を見つめ直すあたりも実にポールらしいと言えるのではないだろうか。そんな印象的なフレーズたちで幕を開けて以降の楽章も、基本的にはポールの訥々とした歌唱と、独力によるアコースティック楽器の演奏だけで構成されている(アコギはもちろん、ドブロやグロッケンシュピール、バス・ハーモニカ、クロメロデオン、種々のパーカッション類などがポールの演奏でクレジット)。プロデュースを手掛けたのはポール自身と、エンジニアも務めるカイル・クラシャム。そのクラシャムはオースティンを拠点にベン・ハーパーらを手掛けてきたプロデューサー/エンジニアで、近年は(ポールの妻エディが率いる)エディ・ブリケル&ニュー・ボヘミアンズの『Hunter And The Dog Star』(2021年)も手掛けていたため、恐らくはその縁からの起用なのだろう。
そんな制作環境を想像させるように、エディは“The Sacred Harp”と“Wait”で声を重ねていて、素朴な作風のなかにそっと別の声が入り込んでくる親密な雰囲気はなかなか微笑ましくも思えてくる。客演という意味ではパーカッション奏者のジェイムズ・ハデッド、前作『In The Blue Light』にも貢献していたワイミュージックの演奏家たちも参加。さらに“Your Forgiveness”“Trail Of Volcanoes”などの楽章には英国の人気アカペラ・グループであるヴォーチェス8も控えめに参加していて、ホーリーな雰囲気作りに寄与している。いずれにせよ、起伏の少ない素朴な組曲ながらも聴後感は実に温かいもので、この不思議な穏やかさこそが現在のポールが辿り着いた境地なのかもしれない。
左から、ポール・サイモンの2018年作『In The Blue Light』(Legacy)、エディ・ブリケル&ニュー・ボヘミアンズの2021年作『Hunter And The Dog Star』(Shuffle/Thirty Tigers)、ワイミュージックの2020年作『Ecstatic Science』(New Amsterdam)、エリック・ウィテカー&ヴォーチェス8の2023年作『Home』(Decca)


































