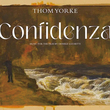3人の演奏から生まれる昂揚感
アルバムの後半は、ジョニーがアレンジしたストリングスの役割が大きくなっていく。ピアノが穏やかなメロディーを奏でる“Friend Of A Friend”は曲の区切りごとにストリングスが爆発寸前まで高まって、ビートルズ“A Day In The Life”を思わせるアレンジだ。続く“I Quit”はエレクトロニックなビートにアコースティック・ギターが寄り添う曲だが、途中でストリングスが登場。トムの呟くような歌声とは対照的に力強く優美な音色を聴かせていて、コントラストの付け方が鮮やか。そして、ストリングスのアレンジ、曲のクォリティー共に本作で屈指の出来栄えなのが、収録曲中、最長の8分に及ぶ“Bending Hectic”だ。
奇妙な音程で爪弾かれるエレキ・ギター。ドラムは複雑なリズムを刻んで緊張感を孕んだ〈場〉を生み出していく。そんななか、曲の核になるのは表情豊かで荘厳な響きを持ったオーケストラ・サウンドだ。前半はスピリチュアル・ジャズのような雰囲気を漂わせているが、後半にはギター・ノイズの混沌が持ち受けている。その変化のきっかけになるのが悲鳴をあげるようなストリングスの爆発だ。この曲の歌詞は、車を運転している主人公がヘアピンカーブに差し掛かるところで事故を起こす瞬間を描いているが、バンドは生と死の境界を確かな構成力と緊張感に貫かれた演奏で表現している。
ジャズ、クラシック、エレクトロニカなどさまざまな音楽性を取り入れた高度な演奏をスタジオワークで融合させる。そんなポスト・ロック的手法を推し進めた『Wall Of Eyes』は、トムの別バンドであるアトムス・フォー・ピース以上にレディオヘッドの〈血〉を感じさせる。そこで印象的なのが、3人というミニマムな編成だからこその親密さが曲に反映されていることだ。3人の演奏の息遣い(おそらく即興演奏がベースになっているのだろう)は伝わってくるし、そこで生まれる空気感を肉付けするために音が加工されている。典型的なロックンロールとは違ったアプローチで、どんなふうに曲を変化させていくのか。どうやって感情を表現するのかを探求しながら、彼らが音楽で描き出すのはパンデミックや戦争が続く不穏な世界で生きる個人の心象風景だ。映画監督のポール・トーマス・アンダーソンが手掛けた“Wall Of Eyes”のMVでは、歌詞に書かれた〈虚ろな目〉をしたトムが群衆のなかで孤立してこちらを見つめている。
その一方で、本作からは困難な時代に生きるプレッシャーを、音楽に昇華させようとする強い意思も感じさせる。曲には重い雲が垂れ込めているような陰鬱さが漂いながらも、必ず美しい瞬間、あるいはエモーショナルな昂揚感が訪れて、アルバムを聴き終わった後には開放感がある。こういう世の中だからこそ自分たちは音楽を作る。『Wall Of Eyes』は、そんなアティテュードに貫かれたアルバムだ。もしもいま、レディオヘッドが新作を出したら、という想像をせずにはいられないが、同時にこの3人だからこそ出せる音が本作には詰まっている。
ザ・スマイルの過去作を紹介。
左から、2022年作『A Light For Attracting Attention』(XL)、日本独自企画のライヴ盤『Europe Live Recordings 2022 / Live At Montreux Jazz Festival, July 2022』(BEAT)
メンバーの作品を一部紹介。
左から、ドゥドゥ・タッサ&ジョニー・グリーンウッドの2023年作『Jarak Qaribak』(World Circuit/BMG)、ハロー・スキニーの2017年作『Watermelon Sun』(Brownswood)