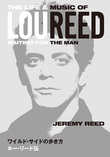アンダーグラウンドのカリスマは、いまも尖り続けている! 強烈なノイズやドローンとエレクトロニック・ビートが絡み合うフリーキーな新作が示す、創造性に溢れた現在地
「ラップ・ミュージックはトラウマを癒すのにとても適している」。サーストン・ムーアとの破局直後のインタヴューでキム・ゴードンはそのように語っていたらしい。ソニック・ユースのメンバーとしてロック・シーンの最前線を牽引し続けて30年。バンドの休止以降(2011年~)もボディ/ヘッドやグリッターバストといったプロジェクトでアクティヴに活動してきたゴードンだが、しかしキャリア/人生の岐路を迎えた彼女が〈本当にやりたかった〉ことのヒントはそこにあった――ということなのかもしれない。
事実、ゴードンにとって初のソロ・アルバムとなった『No Home Record』(2019年)は、冒頭のコメントを物語るように彼女のラップ/ヒップホップへの興味やシンパシーを色濃く滲ませた作品だった。プロデューサーのジャスティン・ライセン(イヴ・トゥモア、チャーリーXCX、リル・ヨッティ)とリズム/ビートを起点に制作され、さまざまなパートや音の断片を寄せ集めてコラージュしたようなノイジーでエレクトロニックなトラック。そしてそこにゴードンがフリーフォームに言葉を乗せていく様は、〈非シンガー〉的だった彼女を解き放ち、ムーア・マザーやバックエックスウォッシュと重なる場面もあったように思う。過去にソニック・ユースの『The Whitey Album』(88年)やフリー・キトゥンなどのプロジェクトでもラップ/ヒップホップ的なアプローチを垣間見せてきたゴードンだが、DJラシャドやRP・ブーなのどフットワークのレコードを聴いたりドラムマシーンを弄ったりして着想が練られたという『No Home Record』のプロセスは、ロックやアヴァンギャルドのマナーに親しんだ彼女にとって文字通りリフレッシュをもたらす刺激に満ちた経験だったに違いない。
そんな『No Home Record』が披露したゴードンの新たなスタイルは、続くこの2作目のソロ・アルバム『The Collective』でさらに大きく推し進められている。〈キム・ゴードンがレイジ!?〉と度肝を抜いた“BYE BYE”をはじめ、タフなビートと強烈なエディットが際立つサウンド・プロダクションはふたたびコンビを組んだジャスティン・ライセンとの共作によるもの。“The Candy House”ではピント/ヴォリュームを乱すエフェクトが三半規管を狂わせ、“It’s Dark Inside”では重く鋭利なギター・ノイズ/リフが、カットアップ的に進行するカコフォニックなサウンドスケープを切り裂く。とりわけ今作で耳を引くのはインダストリアルなトーンで、割れたブレイクビーツに金属音的なシンセが絡みつく“I Don’t Miss My Mind”や、メタル・パーカッションのようなドラム・プログラミングがギター・ドローンやアンビエントな音響と対比を成す“The Believers”は出色。また“Tree House”など数曲で、プロトマーターの最新作にも関わったサラ・レジスター(元トーク・ノーマル)がゴードンと共にギターを弾いているのも注目だ。
前作『No Home Record』では僅かにとどめられていたロック的なナンバーも今作では跡形なく姿を消している。ノイジーでインダストリアルでビート・コンシャスなサウンドは、しかし例えばデス・グリップスやクリッピングのようなものとも異なり、ゴードンのヴォーカルもラップとポエトリーとスポークンワードの間にある〈何か〉を表現しようとしているようでますますアブストラクトでフリーキーだ。タイトルの如くサイケデリックな音像が突如立ち現れ、エモーショナルなメロディーが溢れ出すなか吐息を漏らすように言葉を吐く“Psychedelic Orgasm”。かたやラストの“Dream Dollar”でゴードンは、ギター・ノイズと併走する高速のリズムボックスに乗せてスーサイドのように身体を振動させている。
リズムとテクスチャー、空間とダイナミクスを操りビルドアップされたブルータルでラディカルなサウンド・アート。〈私は音楽を作るヴィジュアル・アーティスト〉――常々そう謳ってきたキム・ゴードンだが、その尖り続ける創作精神はいまだもって行き着く先が見えない 。
キム・ゴードンの過去作と関連作。
左から、2019年作『No Home Record』(Matador)、ボディ/ヘッドとアーロン・ディロウェイによる2021年作『Body/Dilloway/Head』(Three Lobed)、ソニック・ユースのライヴ盤『Live In Brooklyn 2011』(Silver Current)