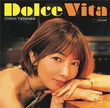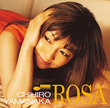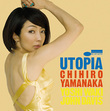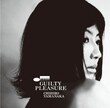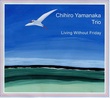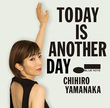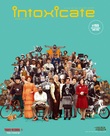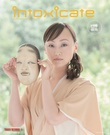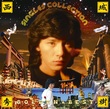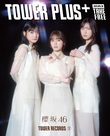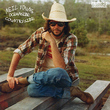政治や社会の変化を反映させたヘンリー・マンシーニの選曲
――そこまでバド・パウエルへの思いが強いなら、彼の曲だけで1枚作ってしまおうとは思いませんでしたか。
「2024年は政治的な変化の多い年でした。ジャズは社会的なムーブメントにすごく影響を受けやすい音楽だと私は思っています。そして、時代時代でジャズのアーティストが社会的な問題に向き合ってきたということにも鑑み、バド・パウエルと同時に今の自分が感じたもの、この時代の空気感を入れたくなりました」
――それは、山中さんのオリジナルも入れたということですね。
「そうです。オリジナルとか、あと坂本龍一さんの曲(“Ai Shiteru, Ai Shitenai”)もそう。やはり坂本さんの音楽の根底にはジャズのスピリットに通ずる何かがあると考え、収録しました」
――教授の曲は前作でもやっていますけど、その『Dolce Vita』は2023年3月にお亡くなりになったウェイン・ショーターと坂本龍一へ捧げたアルバムでした。そして、今作はバド・パウエルとヘンリー・マンシーニの組み合わせです。音楽的には整合性はないですよね。そんな人たちを括ってしまうのは、お茶目な山中さんらしい所作であるとぼくは思ってしまうんですが。
「(笑)。ありがとうございます、好意的に取っていただいて。
マンシーニの方は、映画音楽の曲を2つ選びました。どうしてその2曲かというと、“Sunflower”は『ひまわり』という戦争映画のテーマ曲。あの映画の黄色と水色が印象的なひまわり畑はウクライナで撮影されました。それから“Moon River”ですが……」
――映画「ティファニーで朝食を」の挿入歌ですよね。
「“Moon River”って、実はミシシッピ川の歌なんですよ。その歌詞の意味を知ったときに、今すごく大きな川を渡っている時期なんじゃないかなと思ったんです。原曲はとてもロマンティックな曲だけれど、そのためここでは大胆にアレンジしました。夢見心地な原曲とは違い、自分が目の前の川を渡っていくんだという強い気持ちを込めるようなアレンジにしてみたんです。
バド・パウエルの楽曲は、曲名からも触発されています。“Tempus Fugit”はラテン語で〈光陰矢の如し〉という意味です。“Hallucinations”は、それこそ〈妄想〉。それから“Oblivion”というのは〈忘却〉であり、“Un Poco Loco”はスペイン語で〈ちょっとクレイジー〉という意味です」
――そして、限定盤にはボーナストラックで、細野晴臣さんの“Kanashimi No Lucky Star”(“悲しみのラッキースター”)も入れられています。
「〈もしかして きみはラッキースター/ねえ 今までどこにいたの〉という歌詞があるんですけど、希望のラッキースターがきっといるだろうという細野さんの歌詞に共感しました。
私、青葉市子さんが大好きで、これは細野さんと青葉市子さんがやっているバージョンをけっこう忠実にやったんです。けれど、ピアノは歌じゃないので、〈そのまま弾くよりは〉と思い、7拍子にさせていただきました」
明るい方に向かう時代が続いてほしいという願い
――ようはどの時代の曲であっても、今の時代の空気感なり、山中さんの現況に対する心持ちを表せる曲を選んだということですね。
「はい、そうですね。時代の変わり目にある今の空気感をいろんな曲に込めるために、こういう選曲になりました」
――生誕100周年となる2人の楽曲や音楽性を借りて、月日や世界の流れに対する山中さんの見解をアルバムに持ち込みたいという意図もあったのでしょうか。
「この100年ってアメリカで言ったら、黒人差別だったり性差別だったりがありました。もちろんそれらをまだ乗り越えてきれてはいないですけど、明るい方向に向かう前向きな時代が続いてほしい……。そういう意味を込めたいとはすごく思いました。バド・パウエルとヘンリー・マンシーニが同じ100周年って面白くないですか?」
――驚きました。どっちが年上とかあまり考えたことはないんですが、全然違う時代を生きていたように思っていました。
「そうなんですよ。多様性や豊かさへの念を覚えますよね。ジャズと映画音楽というアメリカから出た2つの異なる属性を抱えた音楽が同じ時代に並行して走り、それが100年の間に人々に愛されているという事実は、この100年がとてもいい時代であったように思わせます」
――20世紀はジャズの世紀でもあり、ハリウッド映画の世紀でもありました。そして、ニューヨークに住む異邦人である山中さんが、自分なりに今をたっぷり呼吸をしながらその事実を編み上げ直すというのは興味深いですし、それは一つの批評だと思います。
「ありがとうございます。やっぱりアメリカの最高の芸術形態としてのジャズと映画が一つの場所で出会う、その面白さは表現したかったです。
ただ、聴く方にはそこまで言葉で説明する必要はないと思っています。でも、Mikikiを読まれるような方にはそういうことをお話ししてもいいかなと思って、今日はお話ししました」