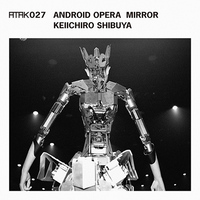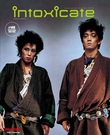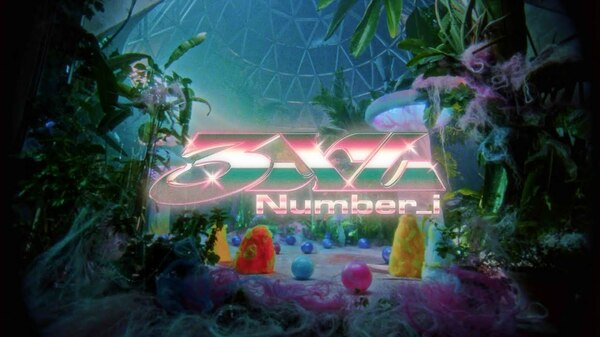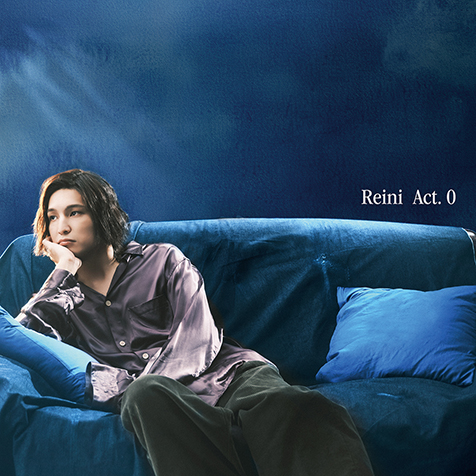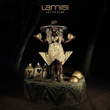人間と機械の脱構築――アンドロイド・オペラが初のアルバム化
近年、渋谷慶一郎の活動の主軸を成してきたアンドロイド・オペラの、初の音盤化作品が完成した。もともと2017年のプロトタイプ公演から始まった一連の実践を経て、2022年、アンドロイド、西洋のオーケストラ、仏教音楽の声明を組み合わせた「MIRROR」をドバイ万博で初演し、同年に誕生した新たなアンドロイド=オルタ4を迎えて翌2023年、パリ・シャトレ座で同作の完全版が披露された。
本盤にはこの「MIRROR」が音として収録されている――のだが、そこには小さくない違いがある。一つはオーケストラの響きが人間の演奏ではなくソフトウェアのシミュレーションを用いて構築されていること。もう一つは公演バージョンのコンセプトの核の一端を担っていた声明の不在である。そしてそのため、公演で見どころの一つとなっていたアンドロイドと僧侶の即興的掛け合いもここにはない。とはいえそれは何がしかの欠落を意味するのではなく、むしろ、「MIRROR」を録音作品として仕上げるにあたって半ば必然的に行き着いた地点だったように思う。
アンドロイド・オペラの前段であるボーカロイド・オペラが、その主役である初音ミクが本来的に声=音であったのに対し、アンドロイドは音に還元し難い存在、というより、現に物体として存在している。ボーカロイドの「THE END」とアンドロイドの「MIRROR」ではアルバムの意味合いが異なるのだ。加えて声明が醸す儀式性も、アンドロイドに導かれるオーケストラの人間性も、あるいは一回的な即興性も、公演という祝祭的空間の中でこそ強く意味を放っていた。記録ではなく作品として音盤化する以上、これらの要素は一度解体され再び構築し直される必要があった。
結果としてありありと姿を現すのはアンドロイド=オルタ4の特有の〈歌声〉である。性別も年齢も判別し難い、ざらついたような透き通ったような、張り上げるような囁くような、複数の声が束ねられたオルタ4のそれは、人間の声とはまるで別の次元で個性的に聴こえる。現在の生成AIの技術からすれば人間を模したリアルな声を作ることも可能だっただろうが、だからこそ、あえて機械的な声としてデザインされたことは重要である。その独特の〈声〉が、渋谷による苛烈な響きを纏いながらもエモーショナルな楽曲のメロディーを歌い上げる。
本盤に収められた音の中で唯一の人間による演奏は渋谷慶一郎が弾くピアノである。彼は人工的に生成された響きに〈最後の人間〉として対峙している。だが実のところ、アルバムを聴くわたしたちにとっては、渋谷のピアノもまた人工的に生成された響きと区別し得るものではない――ピアノはオーケストラやアンドロイドとともに音盤の同一平面上にデジタルに刻まれている。ここではむしろ、わたしたちのアナログな耳が〈最後の人間〉となって、鼓膜を鏡面とするように対峙しながら反射する響きを聴き取ることになるのだ*。