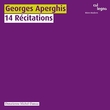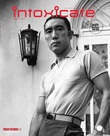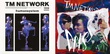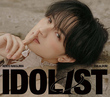「演奏者と親しい友人になって、その友人に手紙を書くように作曲をするのが好き」というアペルギスに、サントリーホール サマーフェスティバルへの思いを聞く
今年も、サントリーホール サマーフェスティバルの時期が近づいてきた。2025年のテーマ作曲家はジョルジュ・アペルギス。若くして、ギリシャから作曲を学ぶためにパリに来たアペルギスは、クセナキスのようにそのままフランスにとどまり、世界に知られる作曲家になった。特に、フランスでミュージック・シアターというジャンルを切り開いた。今回は、早口言葉の超絶技巧とも言える、声のための代表作“レシタシオン”を初め、器楽奏者のジェスチャーや声を交えたユニークな室内楽作品、彼のまた別の顔が見られる管弦楽曲といった多彩なプログラムが展開される。
初めてのサントリーホールを楽しみにしているアペルギス氏に注目される作品について伺った。
――今回、大管弦楽のための“エチュード”のVI、VII、VIIIが日本初演されますが、シリーズとしては2012年から作曲を始められましたね。作品カタログの中で管弦楽曲はとても数が少なく、長年遠ざかっていたのに作曲することになったのは何故でしょうか。
「もともと、以前からケルンWDR交響楽団に管弦楽作品を書くよう依頼されていました。それで、WDRかバイエルン放送交響楽団のどちらかで、エミリオ・ポマリコが指揮をするなら可能だと考えました。エミリオとはとても親しくしていて、私の音楽をすぐにわかってくれます。それに彼はとても優れた指揮者です。
そして、もう1つの条件は短い楽曲ということでした。ロマン派的な管弦楽の〈ドラマトゥルギー〉を避けたかったからです。そのため、各エチュードは短く、それぞれ1つのアイデアによって作られています。
こういった条件がそろったので“エチュード”を作曲することになったのです」
――サントリーホール委嘱新作であるVIIIも同様の手法で書かれたのでしょうか。
「そうです。8曲とも同じ素材を異なるアイデアで用いています。変奏曲のようにその都度、異なる行程をたどります」
――具体的にはどのように?
「ある種の和音が他の形で、つまり変化して再び使われるとか。また、曲ごとにポリフォニーの作りが異なっています。なので、音響のテクスチャーも毎回違います。例えば、アイデアの1つに、和声が音色を決めるというのがあります。楽器の演奏の仕方によって音色を変えるのではなく、和声とテクスチャーによって音色が変わるというものです」
――以前、ご自身のアンサンブルのための作品について「それぞれの楽器が発言をするような形で小さい社会をなしている」、「純粋なクラシックの器楽作品にさえも演劇性はある」と言われましたが、この19世紀的なドラマトゥルギーを避けた管弦楽曲ではいかがでしょうか。
「“エチュード”では、もちろん音楽的なコントラストはあって、それがドラマティックになってしまうことはあり得るけれど、演劇性は意図していないです」
――そういう意味で、この管弦楽曲はアペルギスさんのアンサンブルのための作品とは全然違うわけですね。
「そうです」
――なるほど。それでは、同時に日本初演される“アコーディオン協奏曲”についてはいかがでしょうか。「アコーディオンとパイプオルガンの関係は、ドン・ジョヴァンニのレポレッロやドン・キホーテのサンチョ・パンサ」と言われていたのを耳にしたのですが。
「“アコーディオン協奏曲”では、オルガンが、アコーディオンとオーケストラの橋渡しの役をします。アコーディオンのアシスタントとして、オーケストラと肩を並べられるように手助けをするのです。それは、2つの楽器が兄弟関係にあるからできることです。また、オルガンが大音量で演奏されると、それに支えられたオーケストラは、まるでふいごのある巨大なアコーディオンのようにもなります。と言っても、そこに演劇性はなく、音楽的にアシストしているということです」
――いわゆるオーケストラと独奏楽器のための協奏曲は、この“アコーディオン協奏曲”しか作曲していませんが、それは楽器への思い入れ、あるいは演奏家との関係によって、でしょうか。
「私はアコーディオンのために数々の作品を書いています。アコーディオン、声、ツィンバロムのための三重奏曲や2つの独奏曲もありますし、複数のアンサンブル作品にアコーディオンが使われています。私はこの楽器がとても好きなのです。
アコーディオンが入ると大衆音楽風になるようでいて、クラシック、または教会音楽のようにも響く、その微妙な感じもいいですね」