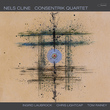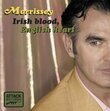今年6月3日に新作『paradise lost, it begins』を発表した吉田ヨウヘイgroup(以下YYG)による新連載がスタート! リーダーの吉田ヨウヘイとバンドの仲間たちが、毎回異なるゲストにインタヴューを敢行。YYGの豊かな音楽性を支える〈Music, you all〉なリスナー気質を活かし、その人や音楽の魅力をディープに掘り下げていきます。記念すべき第1回は、YYG一同が憧れる大物ギタリストのネルス・クラインが登場。自身のバンドであるネルス・クライン・シンガーズ(以下シンガーズ)を率いて来日を果たした彼に、吉田ヨウヘイと西田修大(ギター)の2人で話を聞いてきました。

〈話を聞くまえに〉
ネルス・クラインと吉田ヨウヘイgroupの関係をおさらい
ネルス・クラインといえば近年はウィルコの一員として有名ですが、もともとは即興音楽の世界で名を馳せたギタリスト。「シンガーズ、ウィルコ、ジュリアン・レイジとのデュオなど、ネルスがやっている活動はどれも好きです。ギタリストとして、〈世界一かっこいいよね〉という話を西田ともよくしています」と吉田が語るように、ジャズにロック、カントリーからアヴァンギャルドまで、様々なフィールドで活躍するこの鬼才はYYGに多大な影響を与えています。憧れが高じたあまり、西田はネルスと同じジャズマスターを最近愛用するばかりでなく、ブリッジというパーツも同じメーカーのものに交換、ピックまで同じものを使用しているんだとか。
尊敬のまなざしはテクニカルで音楽的な部分はもちろん、音楽家としてのスタンスにも向けられているようです。「例えばネルスがウィルコに加入した際には、前衛的なことをやっていたトップ・プレイヤーが、そのスタイルを生かして世界的なロック・バンドに加入する、ということ自体にすごく感動しました」とも吉田は語っていますが、先鋭的なアプローチをポップなフォーマットに落とし込む、というのはYYGの作風にも通じるところでしょう。吉田は昨年、新世代のジャズを取り上げた音楽ムック「Jazz The New Chapter 2(以下JTNC2)」でネルスにメール・インタヴューをしており、そのなかでネルスが「私にとって〈研究する〉とは、彼らの演奏をコピーすることではなく、ただ何回も何回も聴き込む、ということ」だと答えていたのも印象的でした。こちらのインタヴューも参照のとおり、幅広いリスニングからヒントを得て、多種多様な音楽家のアプローチを自分たちの音楽に取り入れているYYGですが、それらをただマネ(サンプリング)するのではなく、自分たちの文法にトレースして血肉化し、生身の演奏でアウトプットする彼らのスタイルは、先ほどのネルスの回答とも重なる部分がありそうです。
そして、シンガーズの来日公演が6月初頭にブルーノート東京にて開催された折り、今回の対面取材も実現。その前日にライヴを観て大興奮の吉田&西田は、ドキドキしながら2人でたくさん質問を考えて取材に臨みました。その真っ直ぐな姿勢に心打たれたのか、ネルスも親切丁寧に回答してくれたばかりでなく、嬉しいサプライズも実現しましたよ!
吉田ヨウヘイが見たシンガーズの魅力、ネルスが語るギターとサウンドの美学
「音のなかに消えて、誰にも見えないような存在でいるほうがベターなんだ」
――(吉田と西田の)2人はライヴを観て、とても感激したそうです。
ネルス「どうもありがとう。なるべくそう感じてもらえるように頑張ったよ」
吉田「ネルスさんのギター・プレイはもちろん、バックを務める3人の演奏にも感動しました。ベース、ドラム、パーカッションのいずれも素晴らしくて、バンドのまとまりもすごい。ご自身ではいまのバンド(シンガーズ)の状態をどのように捉えていますか?」
ネルス「そうだね、幸運なことにコンディションは最高だと思うよ。スコット・アメンドラ(ドラムス)とはシンガーズで15年間一緒にやっているけど、その前からもインプロヴィゼーション(即興)のグループでお互いに参加し合っているし、繋がりも深い。シンガーズとしての活動をはじめたとき、ドラムにエレクトロニクスの要素を持ち込みたいのに、誰もライヴでそういうことをさせてくれないんだってスコットがこぼしてたから、〈ぜひそれをやろう!〉って誘ったのさ(笑)。以前やってたネルス・クライン・トリオ※に代わる新しいトリオでは、エレクトロニクスを取り入れるとは思っていなかったけど、ずいぶんとプラスに働いているし、彼も年月を経てますます磨きをかけているね」
※ネルス・クライン・トリオ
ネルスが90年代に率いたフリー・ジャズ・トリオ。2000年代以降はスコット・アメンドラとデヴィン・ハフ(ベース)の新編成で、~シンガーズと名義を改めて活動中。

(Photo by Tsuneo Koga)
ネルス「トレヴァー・ダン(ベース)とは、(前任ベーシストの)デヴィン・ハフと代わってから3年間一緒にやっている。彼とは数年前に、毎週月曜日の夜に僕がフィリップ・グリーンリフというサックス奏者と一緒にやっているコンサートのシリーズで出会って、そこではじめてスコットと3人一緒に演奏したんだ。長い時間を共有してきたことで、いまではとても良好な繋がりを築けている。トレヴァーとシロ・バティスタ(パーカッション)はジョン・ゾーンのエレクトリック・マサダで一緒にプレイしていた仲でね。シロは非常に有名なプレイヤーで、こうしてシンガーズで一緒に演奏しているのもとてもラッキーだと思っている。あまりにも有名すぎるので、僕が一緒にやりたいと誘っても無理なんじゃないかという不安もあった。ライヴでも演奏にたくさんのカラーを足してくれるし、こちらの要望に順応したプレイもしてくれる。一緒にプレイすることが出来て本当に嬉しく思うよ」
トレヴァー・ダンとシロ・バティスタが参加している

吉田「去年させていただいたインタヴューのなかで、(シンガーズの2014年作)『Macroscope』について伺ったときに〈自分のアルバムの主体が僕自身のギター・ソロである、という形を変えたくなってきている〉と仰ってましたよね。それもあって〈今回のライヴではギターはそれほど弾かないのかな?〉と思っていたんですけど、実際にはずっとギターを弾き続けていて、それにも関わらずギターが中心というよりは、バンド全体として聴いたことのない音楽が構築されている印象でした。『Macroscope』を制作していた頃と比べて、ネルスさんが描きたいサウンドスケープはまた変わってきているのでしょうか?」
ネルス「ギター・ソロに対するアプローチや感覚は常に変化し続けていて、いまはもっと押し出してもいいのかなと考えるようになった。〈ソロを打ち出してもいいんだ〉と自分に言い聞かせている部分もあるし、その一方で内心どこかで不安に思ったり、〈これでいいのか?〉と葛藤しながら取り組んでいたりもする。今年のはじめに3週間ほどヨーロッパでツアーをやったんだけど、そこで自分が前に出ていっていい、ソロを弾くことに対してそんな神経質になる必要はないって気持ちになれたんだ。もっとも、明日起きたらどうなっているかわからないけどね(笑)」
マーク・アイシャム〈The Silent Way Project〉コンサートでのパフォーマンス動画
吉田「ギター・ソロ主体になっているのは、バランスとして本当にいいですよね。何よりメンバーがその音楽性を理解していて、ギターに劣らない演奏をしていたというか、4人で1つの演奏をしていたので、ギターが目立ちすぎている印象も一切なかったですし」
ネルス「僕のほうでも、メンバーにスペースというか余裕を与えるように意識している。自分ばっかりが目立ってとか、みんなの声(演奏)が一斉に同じ大きさになるとかではなくて、それぞれがどこかで見せ場をもてるように、自分ばっかりの演奏が聴こえないように気をつけているよ」
吉田「サウンド面で特に感動したのが、ドラムとパーカッションの絡み方で。普通ドラムとパーカッションがあると、それぞれの音が独立して聴こえる演奏が多いというか、それしか聴いたことがなかったんですけど、昨日は2つの演奏がピッタリ合っていましたよね。実際のステージを観ずに、音だけを聴いたらドラマーがひとりでやっているんじゃないかと錯覚しそうなくらいに感じました。パーカッションの役割が、ギターでいったらリバーブみたいというか、ドラムに陰影をつけるような繊細な役割をしていたように感じて。それがすごく新しいと思ったんですけど、あれはネルスさんがディレクションされたんですか? それとも、演奏していくうちに自然にそうなった?」
ネルス「僕がシロに出した指示があったとしたら〈好きなようにやってくれ〉、これだけだ。僕のほうから何か特別に指示したことはなくて、逆に〈自分のしたいように演奏してほしい〉と伝えたら、向こうが本当に好きなように作ってきて、〈気に入った?〉と訊いてきて。それを僕は大体気に入るってかんじ。スコットとシロの組み合わせは今年の初めくらいからなのに、友情も芽生えているし、もうバッチリ息が合っているよね。彼のブラジリアン・パーカッションは信じられない旋律を生み出して、音楽に色付けをしてくれる。初期のウェザー・リポートやマイルス・デイヴィス、マッコイ・タイナー、ギュメ・フランコ等を聴いて僕は育ってきたんだけど、シロはそのレベルに加わるべきアーティストだと思うんだ」
吉田「本当にそのとおりだと思います」

ウィントン・マルサリスやスティング、デヴィッド・バーンや
アート・リンゼイら錚々たる共演歴を誇る(Photo by Tsuneo Koga)
ネルス「シロは僕に〈声を使ってみないか?〉とアドバイスをくれた。僕はそんなに優れたシンガーではないし、音の高低差をつけるのも難しい。(歌ったとしても)静かに歌う傾向があるので、難しいと思っていた。一度YouTubeで自分が歌っているクリップを観たときも、モニターの音がうまく聴こえていなくて、音を外しまくりでそれ以来絶対に(歌うのは)嫌だと言っていたんだよ。けれど、シロが〈絶対に歌わなきゃダメだ〉って。〈ブラジリアン・パーカッションが入っている曲で自分が気に入っているものがあるから、そこで絶対に歌ってほしい〉と。〈そんなに嫌なら一緒に歌おうか〉とまで言われたから、いまはステージで一緒に歌っている。それがもう本当に上手くハマっていて、自分でも気に入ってるんだ」
吉田「昨日のライヴでは“Cause For Concern”もプレイしてましたよね。(シンガーズの2002年作)『Instrumentals』に収録されている、個人的にすごく好きな曲ですけど、そのアルバムの録音と昨日の演奏は、同じ曲なのに印象はかなり違いました。アルバムだとネルスさんが前のめりにギターを弾くような感じで、それにドラムのスコットさんもついていくような演奏でしたが、ライヴではネルスさんは割と同じように前のめりになりつつ、一方でスコットさんはがっちり真ん中にいてリズムを支えるような印象でした。僕は昨日の演奏により感銘を受けましたが、同じ曲に対してもアプローチがどんどん変わってきているのは意識的に取り組んでいるのでしょうか?」
ネルス「あの曲に関しては、まだシロと一緒にやったことがなかったんだよね。元々ライヴでどう演奏しようか決めかねていて、ちょっとフラストレーションを感じていたところもあって。でも昨日はやってみることにした。スコットがラテン系の要素を入れた時にどういう演奏が出来るのか見てみたかったし、シロがそれを気に入るかも気になっていたからね。それで出演の間際に〈じゃあやるか〉って決まったんだ。僕としては体力的に少ししんどかったし、テクニック的にもいまいち納得はいっていないけれど、新しいグルーヴが生まれたんじゃないかとは思っている」
――西田くんはギタリストとして、ネルスのどういう部分が好きなんですか?
西田「すごく難しいな……全部好きなんですよ、音とか弾き方とか。ギターのカッコよさを打ち出すプレイヤーが最近そんなにいないイメージだけど、(ネルスは)ギターのカッコよさというのをガッと打ち出しながら、プレイが(バンド・アンサンブルのなかで)核にならないときでもそのカッコよさを発揮できるというか。〈どんな音楽にでもこのカッコよさを突っ込めるだろうな〉っていう凄さ。僕がはじめてネルスさんを好きになったのはウィルコでの演奏で、シンガーズのライヴを観ていたときも思ったけど、ギターを中心に置いた(典型的な)ロック以外でもそのカッコよさを発揮できるじゃないですか。いまの時代のギタリストにとって、それが一番憧れになるようなことだと思うので、僕は本当に一番尊敬しています」
ネルス「(日本語で)アリガトウ! ギターはもちろん大好きだ。若い頃から演奏している楽器だし、これからも愛し続けるだろうね。でも、もっと根本的には〈サウンド〉が大好きなんだ。自分がやりたいのはサウンドに敬意を払ってクリエイトして、そのパワーや美しさをシェアして共感してもらうこと。自分がギターを弾こうと思った最初のきっかけもサウンドの美しさに惹かれたからだし、そこはこれからも追求していきたい。テクニックを究めるのも楽しいしエキサイティングだけれども、それだけになってしまうとやっぱり冷淡にも思えてしまうよね。それはハーモニーとかテンションとかリリースとかリズムとか、そういった要素のコンビネーションがもたらす美しさには到底敵わないよ。僕は、ただサウンドがエキサイティングで、かつ自分にとって意味があるようなところに適応しているだけ」
ネルス、スコット、トレヴァーの3人に加え、本田ゆか(チボ・マット)も参加
1分40秒辺りから加速するネルスのギター・プレイが凄まじい
ネルス「だから、たまたま自分はギターを使ってサウンドを生み出しているというだけの話で、例えばエレクトロニックの要素を持ち込む(エフェクトをかける)ことによって新しい音を作ったり、あるいはスタジオ録音のような音にしたり、サイケデリックな影響を受けたような音にしたり、モートン・フェルドマンっぽい音にしたりと、ある特定の聴こえ方を試みたりする場合もある。そういう音を全面的に追求できるのならギターじゃなくても別にいいんだけど、一方でそれはまたギターができることのひとつでもあると僕は考えているし、だからこそ美しい楽器なんだ。あと幸いなことに、みんな(僕が弾くのを)気に入ってくれてるし(笑)。僕は(ギターは弾けるけど)フレンチ・ホルンを吹くことはできないからさ。フレンチ・ホルンの音は大好きだけど、そっちをやろうとしたら(ギターを弾いている)いまよりずっと苦しい人生になっていたよ(笑)。もちろん(演奏する姿が)カッコよく映ったりだとか、ステージで前面に立つ姿を見られるのもいいんだけど、自分としては音のなかに消えて、誰にも見えないような存在でいるほうがベターなんだ。音にかき消されるというか、その中に埋もれている。それで、みんながサウンドを共有しているというのが僕にとっての理想だ」
吉田・西田「カッコいい……! 」
〈Tiny Desk Concert〉出演時の模様。メンバー編成は一つ上の動画と同じで、
アコースティック演奏によってネルスの語るアンサンブルへの意識が一層伝わりやすくなっている