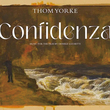照沼健太
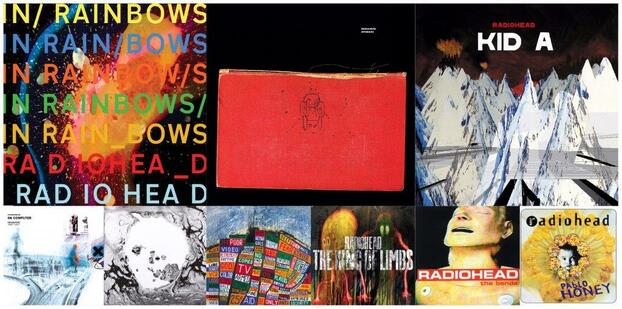
1. In Rainbows(2007)
2. Amnesiac(2001)
3. Kid A(2000)
4. OK Computer(1997)
5. A Moon Shaped Pool(2016)
6. Hail To The Thief(2003)
7. The King Of Limbs(2011)
8. The Bends(1995)
9. Pablo Honey(1993)
〈ロックを延命させた〉バンドである
2017年に振り返るレディオヘッドとは〈ロックを延命させた〉バンドである……いきなり某R誌ふうでおちょくっているようだが、紛れもなく本音だ。それは何もいま始まったことではないが、ロックよりもヒップホップ/R&Bが人気ジャンルになったという2017年にこそより意味を持って感じられるだろう。
ロックの歴史は基本的に複雑化(例:プログレ)と、その揺り戻しによる単純化(例:パンク)の繰り返しによって前進してきたのはご存じのことと思うが、レディオヘッドが“Creep”でデビューした92年は、何度目かの単純/統合化であるグランジが大きな影響力を持っていた年だった。スコット・ウォーカー的なシンプルなコード進行とヴァースとコーラスの強弱により最短距離で高揚と沈鬱を表現した同曲は、断片的なイメージを連ねたリリックではぐらかすニルヴァーナ“Smells Like Teen Spirit”よりもストレートに〈単純化〉の波に乗ったアンセムだったかもしれないし、その後のヘヴィー・ロックやポスト・ロック、UKロック(と、もしかしたらJ-Rock)への影響を鑑みればその影響力は計りしれないし、〈(なんとなくのつらさがあるな〜)→(本当に悩んでる気がしてきた)→(つれえ……)→ウァワワワアアァァァァァッッッッッッッオーー!!!〉という〈ファッショントラウマ〉や、強引な感情の爆発を商品化したような音楽の増加の一助になってしまった部分は否めない。
そして、そんな誤ったフォロワーの音楽が隆盛を誇るようになった97年~2001年、当のレディオヘッドは同曲を封印すると同時に、トリップホップ、IDM、現代音楽、ジャズやブルーズといった〈外側〉を参照することにより、2拍目と4拍目のスネアやエモーショナルなヴォーカルなどロック的な記号と距離を置くようになる。だが、なにもロックを捨て去ったわけではなく、2003年の『Hail To The Thief』以降は、2000年の『Kid A』、2001年の『Amnesiac』で見た〈外側〉の可能性を時代の空気感とともにロック音楽にいかに落とし込んでいくか=ロックをいかに形骸化させないかということに挑み続けているとも言えるだろう。その一つの結実が、シンプルな楽曲形式とバンドアンサンブルの中に〈外側〉のアイデアをまとめ上げた2007年の『In Rainbows』である。そしてそのベースとなった骨格こそが、初めて〈外側〉を明確に取り入れた97年の『OK Computer』なのだ。
また2017年にレディオヘッドを振り返るにあたっては、音楽業界のシステムと音楽のあり方それ自体へのアプローチも欠かせない。オリジナル・アナログ盤を10インチ2枚組という変則形式とした『Kid A』『Amnesiac』『The King Of Limbs』、そして、iTunes/iPod以降の〈曲単位リスニング〉の影響濃厚な長大作『Hail To The Thief』における、使い古された〈アルバム〉というフォーマットへのオルタナティヴな提案。『In Rainbows』での、リスナーが作品の値段を決める〈Name Your Price〉方式の採用による、業界の慣習や音楽のあり方へと投げかけた問題提起は、間違いなく彼ら最大の功績だろう。
ロックを軸としたポップ・ミュージックの可能性、そして音楽業界のシステムへの挑戦を続けたレディオヘッドの道程は、もしここで彼らのキャリアが終わったとしても、今後ロックと呼ばれる音楽が消えてなくなったとしても、後世のあらゆるジャンルのミュージシャンの冒険心に宿る、確かな心の灯となるはずだ。
近藤真弥
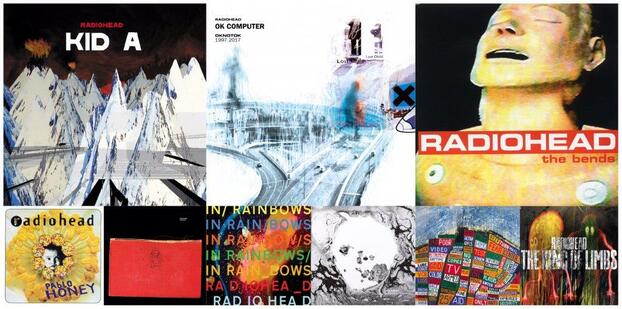
1. Kid A(2000)
2. OK Computer(1997)
3. The Bends(1995)
4. Pablo Honey(1993)
5. Amnesiac(2001)
6. In Rainbows(2007)
7. A Moon Shaped Pool(2016)
8. Hail To The Thief(2003)
9. The King Of Limbs(2011)
ロックがロックを葬ったような衝撃を与えた『Kid A』
クォリティーとポップ・ミュージックへの影響力を基準に、順位を決めました。『OK Computer』までのレディオヘッドは、内に秘めた心情を爆発させ、それをひとつの世界観なり価値観で表現するというロックのクリシェを体現するバンドでした。
しかし『Kid A』で彼らは、バラバラの世界観や価値観をそのまま表現してみせた。このアルバムでは、感情や呼気といった人間的な要素は排除され、全体を覆いつくす無機質で冷ややかな電子音はロックのフォーマットからかけ離れたものでした。こうした作品が、ロックを代表するバンドのひとつであった彼らによって投下されたことは、衝撃的だった。なぜなら、ロックがロックを葬ったようなものだったからです。音自体は、オウテカなどの急進的なエレクトロニック・サウンドに影響されたもので、彼ら独自のとは言えませんが、その影響をロックの文脈で見事に機能させたところに『Kid A』のすごさがあり、だからこそ彼らのディスコグラフィーのなかでも孤高の存在感を放っている。もちろん、他の作品にも興味深い曲はたくさんありますが、アルバムとしての完成度では『Kid A』ほどの驚きや鋭い批評性には達していないというのが正直なところです。なので、今回の順位にしても、1位がダントツで、2位以下は拮抗しているイメージで選びました。強いて言えば、『Kid A』にたどり着くまでの彼らがいちばんおもしろかった時期だと思うので、『Kid A』以前の作品群を上位4つに入れています。
また、5位以下の順位づけは非常に悩みました。『Kid A』以降の作品群には、一長一短が目立つように思えるからです。そのうえで『Amnesiac』を5位に選んだのは、『Kid A』と同様、彼らなりに電子音の可能性を追究した跡が明確だから。とはいえ、物悲しいマイナーコードの響きが印象的な“Knives Out”など、『OK Computer』以前のサウンドが随所で聞こえる点は、『Kid A』の先鋭さと比べると少々生ぬるいと思います。
そんな彼らを現在の視点から見ると、時代を切り開いてきた開拓者だと感じます。たとえば『In Rainbows』では、リスナーに価格の決定権を与えるなど、リリース方法自体がコンセプトになっていました。いまでこそ、ヴィジュアル・アルバムとして発表されたフランク・オーシャンの『Endless』(2016年)など、リリース方法が表現の一部になっている作品は多く生まれていますが、そうした流れに先鞭をつけた存在のひとつとして彼らの名は欠かせない。もし、『In Rainbows』における彼らの試みがなければ、無料ダウンロードと言われると逆に聴かないとなるリスナーも少なくないなかで、音楽を販売しないチャンス・ザ・ラッパーが第59回グラミー賞で3冠に輝くことはなかったかもしれない。そう考えると彼らは、音楽面のみならず、その音楽を発表する方法論にも影響を与えたと言えるでしょう。