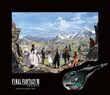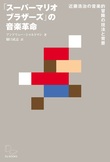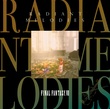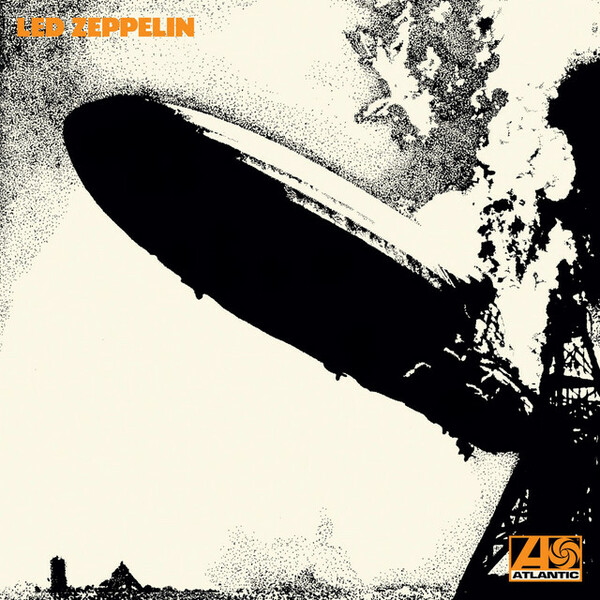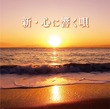ゲーム音楽は輪廻転生していくもの
hally「ゲーム音楽の作曲家は映像をすごく大事にしながら音楽を作っていますよね」
中潟「そうだね。ゲーム音楽って音楽として一本立ちするようなものではなく演出としてあるものなので、目立ちすぎちゃいけない。〈ゲームのシチュエーションをプレイヤーにいかに伝えるか〉がメイン。だから、音楽を作るうえで気を遣う部分はすごく多いんです。
僕が曲を作るうえで大事にしていた部分は、ファミコンの頃は〈いかに印象に残るフレーズやメロディーを作るか〉、アーケードの頃は〈いかに騒音のなかで通る音を作るか〉ということです。そういった命題がありつつ、ゲームの世界観も大事にしなければいけない。さまざまなしがらみのなかで音楽を作っていくことが当たり前でした」

hally「そうやって作られた音楽を、新しい世代がゲームや映像から切り離してしまった(笑)。ある意味、失礼な行為ではあるのですが。でも、音楽の聴き方が変われば、新しい価値観も生まれてくるのかなと。ゲーム音楽はそうやって輪廻転生していくものなのだと思わされます。環境が変われば、いくらでも再生して生まれ変わっていけるんですよね」
中潟「そうですよね。Quarta 330さんは今後、どういう音楽をやっていこうと思っているんですか?」
Quarta 330「チップチューンは〈この音源を使って、どれだけみんなを驚かせられるのか〉というスポーツっぽいところがありますからね。既存の音楽ジャンルを踏襲するスタイルを採ると、ちょっとダブルスタンダード的かもしれません。でも、チップチューンの一番の魅力は、その音色にあるんですよね」
hally「Quarta 330くんのいまの音楽は、チップの音とそうじゃない音をバランス良く取り混ぜているので、それはひとつの解答なのかなと思います」
Quarta 330「ありがとうございます。ここ最近はチップの音とそれ以外の音の比率が逆転して、クラブ・ミュージックにゲーム音楽の要素が足されている感じですね」
中潟「ゲーム機からの音源にはこだわらない?」
Quarta 330「こだわらなくなってきました。チップチューンを前提として作りはじめると、他の要素が入ってくるときに〈これは違うかもしれない〉と感じてしまうんです。(チップチューンとしての)純度が薄まる怖さがあって。ここ最近は、ようやく他の要素も入れられるようになってきました」
hally「チップチューンというカテゴリーがしっかりと成熟してしまったので、そこからはみ出すのが難しくなってきている感があります。そんななか、アーティストが試行錯誤している」
Quarta 330「最近のチップチューンは、〈音楽的にはリミットまで来たんじゃないか〉と感じてしまうほど成熟しているように感じます。それをどう見せるかという、これまでとは違う方向へ進化をしている。たとえば、単純にライヴ・パフォーマンスとしての見せ方にこだわるようになったり、より劇場型的な方向性に行ってみたり。完全にクラブ・ミュージックとしてシリアスな方向に行く人もいます」
hally「ゲームとは別の映像中心の世界に行く人もいますね」
Quarta 330「また〈映像のための音楽〉に戻っていくのかもしれませんね」
正直、ファミコンの音の作り方を忘れていたんです(笑)
hally「『Diggin In The Carts』がリリースされるタイミングで中潟さんも『NEO平安京エイリアン』というファミコンのソフトを出すというのはおもしろいですよね」
中潟「偶然だよね。正直に言って、ファミコンの音の作り方を忘れていたんですよ(笑)。でも、やりはじめると〈ああ、そうだった!〉と思い出して楽しめました」
Quarta 330「『NEO平安京エイリアン』の音楽はどうやって作ったんですか?」
中潟「MML※1ベースです。MIDI変換で一発でうまくいくというわけではないので、シミュレーターを使ったりもしています。
あとは弟子の塩田信之※2くんが手伝ってくれて(笑)。彼は『ブライファイター』を作っていた頃に新人として入社して、僕がファミコンの音の作りかたを教えてあげたんです。でも、今じゃもう、塩田くんのほうが(音楽制作では)数段上。逆に僕が塩田くんに教えてもらうという(笑)」
※2 作曲家。代表作に「サマーカーニバル'92 烈火」や「オリビアのミステリー」など
hally「実は、塩田さんをチップチューンの世界に引きずり込んだのは僕なんです(笑)。もともと塩田さんの大ファンで、東京に出て来たとき真っ先に塩田さんに〈お会いできませんか?〉と連絡をしたくらいだったんです。それと前後して〈チップチューンおもしろいですよ、やりませんか?〉と言っていたら、本当にやってくださった。そこからこうやって中潟さんにまで繋がるとは夢にも思いませんでしたけどね(笑)」
中潟「それはびっくりだなあ。今回、『NEO平安京エイリアン BGM ReMIX』という『NEO平安京エイリアン』の音楽のリミックスCDも作ったんです。塩田くんは8ビットで来るのかと思ったら、意外にもクラシック・アレンジ。他にもナムコで一緒だった川田くん、細江くん、それからTECHNOuchiくん、ヨナオケイシくん、WING☆くん、BUNくん、杉山和彦くん、それと『女神転生』シリーズの増子津可燦くんといった友達に参加してもらいました。みんなおもしろい曲を作ってくれて、非常にヴァラエティー豊かな作品集になりました」
常に新しい音楽を作っていた冨田勲先生に習うところは大きいですね
hally「今回の『Diggin In The Carts』で興味深いのは、ゲーム音楽の音楽だけに焦点があるということなんですね。〈古今東西のエレクトロニック・ミュージックを知っている人が、昔のゲーム音楽を聴いたときにおもしろく聴こえるもの〉という視点で編んでいる。
中潟さんがプロジェクトの一部として作っていた音楽が単体として取り出され、こうやってコンパイルされるというのは想像だにしなかったことなのではないかと(笑)」
中潟「ええ。まさかこういった聴かれ方をするとは思ってもみませんでした。ゲームの基板から出ている音自体に着目して、それがチップチューンという形で発展し、Quarta 330さんのようなミュージシャンがそれをさらに広げていったことは新鮮な驚きがあります。
自分自身でもチップチューンの音を聴きながら、今後自分の音楽性のなかでどのようにこうした要素を取り入れるべきか、模索しているところでもあります」
Quarta 330「音楽家としてまだまだ伸びしろがあるわけですね!」

中潟「いやいや(笑)。好奇心ですね。AQUA POLISでもまた活動をしているのですが、それとは別にQuarta 330さんやhallyさんたちのようなチップチューン的な方向性のものも、いずれチャレンジしてみたいですね」
hally「そうですね。僕らは大先輩と一緒にできる貴重な機会が与えられるということで(笑)。本当にこんな時代が来るなんて、思ってもいなかったです。中潟さんはご自身の会社を経営されているからこそ下の世代が気になるというのもあるのかなと思います」
中潟「常に好奇心があるんです。尊敬する冨田勲先生も、亡くなる直前の作品で初音ミクを起用されていました。いつの時代でも最先端を意識して、新しい音楽を作っていた冨田先生に習うところは大きいですね。
しかし、こうやってゲーム音楽が脈々と受け継がれていき、世代を超えてこんなところまで来たんだなと改めて思いました。僕がこの業界に入って、もう30数年ですから、歳も取るわけだよね(笑)」
hally「いやいや(笑)。シンセにしろゲーム音楽にしろ、どんどんリアルに、グレードが上がっていく流れに見えて、気が付いたらもう一度チープな音に帰ってきている。そういったなかで、それぞれ世代が違うのに繋がっていくものがあるというのは、すごくおもしろい。『Diggin In The Carts』はそういう流れの果てにあるものだなあと感じますね」
中潟「そうだね。時代が一回転し、温故知新の中から新たなものが再生していく、そんな現場に立っているんだね、いまの僕たちは」