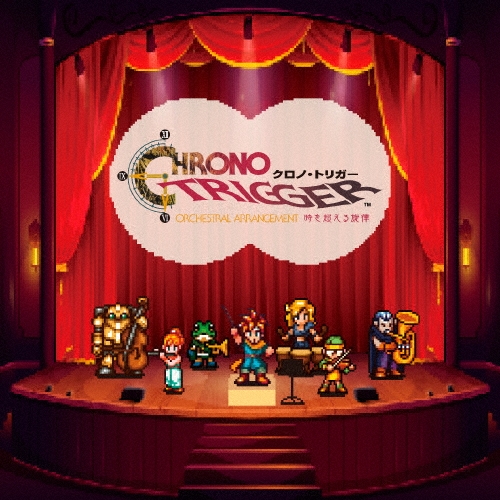初々しくて外向き、街の壁に描くようなフィーリング
――フレッシュと言えば、一曲目に収録された“逃亡前夜”はハウス・ミュージック・フィールを醸していて新鮮でした。ただ、具体的にどういったハウスを参照にしたのかは見えてこない感じで。
夏目「フフフ(笑)。それはむしろ正解」
藤村「実は特にハウスを落とし込んではない。ハイハットの入り方とかも、ミニマルなパターンではなくてわりとランダムというか、ちょっと手癖が入ったり入っていなかったり。だから、整理されてなくて結構人間臭いところがあると思う」
夏目「モザイカっていうテクノ系のアーティストがいて、“逃亡前夜”のタンバリンや固いビブラスラップの音とかは、ほぼ彼の楽曲をモティーフにしたと言っていい。つまり、ビートはダンス・ミュージックから持っていきつつ、アコギを鳴らして歌を入れるという実験をした。で、ミックスを仕上げるにあたっては、僕が聴いているテクノのノリや音の配置にしたかったんですよ。
ただ、エンジニアの日向さんがやってくれたミックスは結構ロックな印象で、〈これハウスなんですよ、テクノなんですよ〉という仕上がりにするのであれば、少し違和感があった。最初は、うーんと思ったんですけど、次第にいま俺らがやるのであれば、いちばん良いのかもなという気もしてきた。そうなってからの僕のイメージとしては、(デヴィッド・)ボウイの“Young Americans”や“Let’s Dance”とか、ああいうグルーヴィーなロックに寄ったイメージなのかなと思っている」
――ブルーアイド・ソウルというかね。この曲は間奏のギターもすごくロッキッシュでカッコイイですね。
菅原「あれね。でも、実はあのフレーズを考えたのは俺じゃなくて、バンビなんです。なので、俺はこの曲に関しては、何もやってないと言っていい」
一同「いやいや(笑)」
菅原「今回、実務的な面でも作曲に関しては、俺と夏目でパキッと分かれていて、お互いの曲にあんまり干渉しないって感じにはなってるね。そういう意味では、ぜんぜんバンドっぽくない感じがする作品なのかもしれない。だけど、不思議なことに、アルバムを通して聴くとすごくシャムキャッツになっている。それは前作でカチッとしたフォーマットを作りこめたからこそ、ここに到着できたのかなとも思うな」
夏目「ロック・バンドってクセで作っちゃうと前と似たような音になるんだよね。だから、ちょっとプロダクション面を変えたいという気持ちはあった。で、そのアプローチとして、これまではドラムとベースを録ってギター、それから歌という順番だったけど、今回は、まず声をどこに置くのかを念頭に、周りの音をいかに配置していくのかをイメージした。なので、メロディーや歌詞に引っ張られて、それぞれの楽器の演奏もいままででいちばん変化していると思う」
――プロダクション重視のロック・アルバムと言うと、最近ではアラバマ・シェイクスやスプーンといったバンドの作品を指すことが多いと思いますが、自分は今作にスーパー・ファーリー・アニマルズを感じたんですよ。サイケデリックでありフォーキーでもありつつ、プロダクションにはエレクトロニック・ミュージック的な意匠もあって。
藤村「確かにスーファリっぽいかも」
夏目「それは合っていると思うな。UK感って言うかね。僕から言わせると、イギリスのサイケの魅力は、アメリカにはない軽さだと思っていて、こう綿菓子みたいなサウンドっていうか。ビートとかの土臭さに関してはアメリカのほうが好きなんだけど、綿菓子というか麩菓子みたいな感じはイギリスの音楽特有だし好きなんだよね」
菅原「それは〈浦安感〉ってところでもあると思うな」
夏目「すべてが偽物という感覚っていうか。でも、そういう紛い物だと引き受けた音を鳴らすことが、日本でロック・バンドをやるうえでは、いちばんの正統なやり方だと思うんですよね」
――その浦安感、本物になれてないというニュアンスをふまえつつ、楽曲ごとの個性がバラバラな本作は、初作『はしけ』を9年越しでヴァージョン・アップしたような印象もありました。
夏目「僕もね、『はしけ』っぽいなと録音が終わって、曲を並べたあとに思ったな。ただ、『はしけ』はかなり箱庭的な作品――同じ街に住んでいる奴らが同じ感性のもと、あーだこーだ言いながら作った、内側で完結している作品だと思っていて。それと比べると、今回の作品は外に出ている感じがすごくするんだよね。街に出て何かをするんだという意思を自分としてはすごく感じていて、その初々しくて外向き、街の壁に描くようなフィーリングが 『Virgin Graffiti』というタイトルにも繋がったんだよね」
――今作は、ロック・バンドがいかに聴き手を日常のしがらやみや抑圧から、外側に連れて行くかということに視点を置いた作品ですよね。そのありようとして、自分は初期の曽我部恵一BANDを思い出しもしたんですよ。ただ、ソカバンがいわゆるロックの熱量みたいなものにこだわっていたのに対し、今回のシャムキャッツはむしろロックというフォーマットから逸脱することで、同じロマンを提示しようとしたところがおもしろい。
夏目「うん、わかる。ロックって、ソカバンが持っていたパワーというか、MC5的な上がりが興奮としてはいちばん強いと思うんです。でも、ダンス・ミュージックって熱量のある音を入れて、それで上がらせるという世界ではないですよね? むしろテクノとかって音の粒自体が良いのか悪いのかってシビアな世界だし、その抜き差しや揺らぎ、繋がりや展開とかでなだらかに気持ちを昂揚させていく。僕は、そっちの昂揚のほうが、人間に対する感動のさせ方として、強いんじゃないかといまは感じていて。だから、バンドでロックをやるときも、バスドラ、スネア、ベース、ギター……それぞれをどういうふうに鳴らせているのかが、人の感動に直結していると考えているんですよ。曲に対して、適切な音、位置、おもしろさを足していくというアプローチで作りました」
――ただ、そういったディテールにおける方法論は把握しつつも、アルバムとして一枚にまとまったときの全体像みたいなものは、なかなか見えてこなかった?
一同「うん」
夏目「まったく見えなかった」
菅原「今回は最後までわからなかったね。タイトルが付いて、ちょっとわかった気がしたくらい」
夏目「どうなるかと思っていたよね。日向さんだけが、〈これは良いアルバムになる〉と断言していたな。粒が揃っているから、もう大丈夫、曲の種類はバラバラだけど並び方を間違えなければ名盤になるとずっと言っていたんです。正直、僕らは不安だったんですよ」
ホントの強さとは、隣の人に対して優しくすること
――とはいえ、各曲のアレンジやサウンドはバラバラなのに、作品が訴えかけるテーマとしては……
藤村「いままでで、いちばん統一感があるんだよね」
夏目「そうなんだよ」
菅原「やっぱり山口さんがデカかったのかな」
――苦楽を共にしてきた盟友との別れが、今作に深く影響を及ぼしたのは間違いないにしても、バンド内ストーリーを綴っただけのアルバムではないですよね。体調を崩してしまい、ある意味では夢半ばでバンドを離れてしまったスタッフをモデルケースにしたうえで、現代社会に生きる人が何に苦しめられているかを見つめつつ、そこから逃げてもいいんだよ、と伝える作品でもある。
夏目「そう! まさしく」
藤村「俺らや彼に起きたことは、いまの社会では誰もがそうなってしまう可能性があると思ったんだよね」
どこかであんしんとか/いつかはまんぞくとか
もういんだって/もういいんだって
きみはきみだけみてればいい
“もういいよ”
――シャムキャッツを聴くリスナーやライヴに来るオーティエンスは、比較的若い世代が多いと思うんですけど、みなさんから見て、彼らを苦しめている強迫観念ってなんだと思います?
菅原「うひゃー、難しいな」
夏目「僕はやっぱり同調ってことかなと思う。圧力とまでは行かないけれど、なんか同調しなきゃって感覚はすごくある気がするな」
――具体的な事象をあげてもらうとすれば?
夏目「うんとねー、この前、友達が……そいつも音楽関係の仕事をしてるので、SNSでバンド名を検索したりするらしいんですけど、その際に〈あのバンドのチケットは、みんなが行くからとった!〉みたいな投稿を見たらしいんです。逆に〈このバンド、好きなんだけど、誰も行かないしライヴには行かない〉みたいな発言もあったらしくて。でも、そういうことじゃないなっていうか。すごく日本人的な感覚だと思うけど、それは悲しいことだよね」
菅原「孤独であることに対して、過剰に恐れを持っている人が多いなと思う」
夏目「SNSの誕生以降、若者たちが孤独を標準装備するようになったとは言われてるんだよね。昔は、孤独ってのは結構特殊というか、あるタイミングがこないと感じないものだったけど、いまの子たちってのは、もちろん僕も、最初から自分のなかに孤独がある」
――シャムキャッツの音楽は、孤独を消すため、仲間づくりをするためのツールではない?
菅原「極論を言えば、ライヴなんて別に来なくていいんだよね(笑)。家で1人で聴くのでいいし、そのために俺らはレコードを作っているわけで」
夏目「でも1人だからこそ、いっぱい人がいるところに行くとやっぱり安心はするんだよ。同調ではなくて、ある一つのアーティストの音楽をみんなが聴いている場所に行って、自分は1人でいるって状態が、僕はすごく安心するね。みんながキラキラしていて踊っていて、輪のなかに自分がいるわけではないし、別に友達もいないけど、大きな音が流れてる――その場にいるってのが僕にとっては逃避や離別でもある。だから、そういう解放の場としてライヴがあるから、来てほしいな、来ればいいじゃん?とは思ってるかな」
――リスナーに逃げたっていいんだよ、と声を掛けられるのは、シャムキャッツ自体がポップ産業のレールの上から〈いちぬけた〉できたからだとも思うんです。それは、自分たちのレーベル、TETRAの設立/運営や、アジア・ツアーをすることによって日本を客観視できたこと、さらには大きな別れなどを経て、バンドがオルタナだと自称しつつも片足はずっとかけていた、いわゆる〈ロックンロール・ドリームの成就〉みたいなものから解き放たれたことも関係しているのかなって。
夏目「あー、そのとおりだと思うな」
大塚「『Friends Again』のときは、まだポップ・シーンでの成功を意識していた?」
夏目「いや、そういう意識はなかったね。『Friends Again』のときは、意固地に〈今日的、日本的ポップシーンでの成功? そっちにはいきません!〉というスタンスでやってたと思う。サビのある曲を書かなかったりとか。ただ、意地になって地味な方へと向かって行ってた感じもする。だけど、いまはもう反抗すらしてないんだよね」
――ええ。
夏目「音楽って、すごく芸術的な純粋性の部分と、時代との距離感をどうとるかというゲーム性の部分、双方があると思う。で、ポップスは後者の面が強くて、こういうものが流行っているからそれに乗るとか逆を行くとか、そういうのがおもしろい。
でも、僕の意識としては、今作は日本特有のルールというかゲーム性は完全に無視したんだよね。それが自分の創作にすごい良い影響を及ぼしたし、アジア圏で活動しようと思うのであれば、そういう意識を持つのは良いことだと自分では思っている。まぁ、この国でどう受け入れられるか、ほかの国でどう受け止められるかは、まだわからないけれど、自分としては、これまででいちばん気に入っているアルバムにはなった。自分の理想にはもっとも近いかな」
同じようなことで気を病んだらその時考えよう
パッと気が晴れる場所へ出かけて踊ろう
“逃亡前夜”
――いや、夏目くんが言っていたストーリーをふまえても、このアルバムは最高傑作なんじゃないですかね。ロック・バンドが、この2018年にどんなロマンをリスナーに示せるのか、大きな言葉で言えば、いかに音楽によって救われた気持ちをもたらすことができるかを、魂として中心に据えた作品だと思います。
夏目「みんなを踊らせたい、明るい気持ちにさせたい、となったタイミングで、山口さんの一件があったから、自分たちが共通して持てるテーマは離別や別れ、逃避にはなっていったんだけど、とにかく暗い作品にはしたくないという気持ちではあったんですよ。まぁそのエールじゃないですけど、はなればなれになったあとも、それぞれの人生は続いていくわけで。なので、大きな別れと、その先にあるもっと大きな出会いみたいなものを表現したかった」
――菅原くんも作曲のうえでエールのニュアンスを落とし込もうという意識はあった?
菅原「めっちゃありましたね。だいたいの曲をそういう気持ちで作っていたと思う。ただ、俺は結構暗い気持ちだったな。にもかかわらず曲を書いて、その曲をバンドで表現すると、いま夏目が言ったような感じの方向に変わることには、自分でもびっくりした。便所の落書きを書いているんじゃなくて、やっぱりそれを人に届けようと思っているんだなって。俺は、誰しものなかにいる山口さんへと曲を書いたな」
――ちょっと泣ける言い方ですね。
菅原「ホントに強いものは、剣や刀を持つことではなくて、隣の人に対して優しくするとか、そういうことだと思うんですけど、そういうことがやっとできるようになったな、シャムキャッツ」
ここに何か付け足すならば
はぐれた仲間の声を
ステージに運んでちょうだい
“完熟宣言”