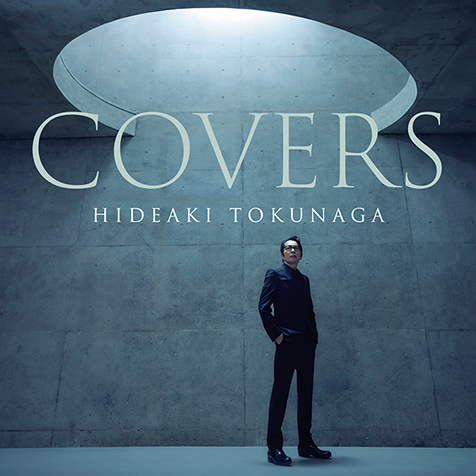1954 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
戦慄の律動――ゴジラという恐怖の調べ
祝! 生誕100年&公開60年
「やはり、あの、日本がアメリカのテクノロジー、って言うんですか、それで負けたっていう感じがあったのに、ゴジラと言う生物が出てきて、その近代のテクノロジーをものともしないで壊していきますね、それに対する爽快さと言うか共感と言うか、そういうものもあって必要以上に興味を持ったんですけどね」
伊福部昭が、自身の映画音楽や演奏会用作品の創作活動について語った多くの言葉は、現在の私たちにとっての大いなる示唆に富んでいる。子供の頃から、「ゴジラ」シリーズや「座頭市」シリーズをはじめとする数々の映画のスクリーンを通じて聴いていた伊福部昭による映画音楽を、彼の言葉とともに追体験することは、伊福部作品の持つ根源的な魅力の秘密に触れるようで楽しい。上記の言葉も、今回リマスターされた1954年版の「ゴジラ」記念すべき第一作目のブルーレイ・ディスクに、従来のDVDからそのまま引き継がれた特典映像のなかで語られている。
北海道、釧路町に生まれ、木材の研究を北海道大学で修めた伊福部昭は、牡蠣の産地として有名な厚岸の森林事務所に勤務、その間、日本の作曲家を発掘すべくパリでタンスマン、ルーセルらを始め錚々たる審査員によって選考されたチェレプニン賞を“日本狂詩曲”によって獲得し、訪日したチェレプニンの薫陶を受ける。森林官を辞して札幌に移った後、第二次世界大戦中は、軍事物資としての木材と林業試験に関わった。
「太平洋戦争時、私は戦時科学研究員という身分で木材製飛行機を開発するにあたっての強化木の研究にたずさわっていました。8月15日には敗戦を迎えましたが、私はその2週間後の28日に血を吐いて倒れてしまったんです。圧縮木材のレントゲン撮影を繰り返すうちに放射能を浴びてしまって。」
(「伊福部昭語る—伊福部昭 映画音楽回顧録—」 伊福部昭 述 小林淳 編 ワイズ出版 より引用)
終戦後に豊かな物資とともに傾れ込んできたアメリカ軍の豊かさに茫然としながらも、古来の日本の、自然との共存や森羅万象への畏敬を失ってはいなかった。伊福部家は代々、因幡の国(現在は鳥取県)の宇倍神社の神官を勤めてきた。故郷には豪族の娘であった伊福吉部徳足比売(いふくべのとこたりひめ)の古墳があり、数えて67代目が伊福部昭であった。子供の頃から、家族の由来を繰り返し聞いて育ってきた伊福部昭は、音楽に投影する自己の作風の中にも、日本であるもの、アジアから日本に流れ込んできたものを、最大限に活用しようと考えた。父が赴任した北海道で出逢ったアイヌの人々も、決定的な影響をもたらした。代表作のひとつになっている1954年の“シンフォニア・タプカーラ”。タイトルに使用された〈タプカーラ〉とは、酒席で興がのった人々が誰彼ともなく立って踊る様や、熱狂的な歌が延々と繰り広げられる、それらの総称としての言葉であるという。
「終戦直後は、日本の伝統的なものすべてが駄目、(中略) 何でも新しいものがいいというように、価値判断の尺度がぐらついておりました。日本の伝統的なものが完全に否定された時代でした。(中略)しかし私なんか、そう言うことになる前から生きておりましたから、そうはいっても違うんだ、という感じは残っておりました。」
(「伊福部昭の音楽史」 木部与巴仁 著 春秋社 より引用)
1954年に生まれたゴジラという生物は、地球古来の生物の頂点であった恐竜の生き残りが、度重なる水爆実験によって変則的な進化を遂げ、歩く原子炉へと化身した怪獣だ。放射能火炎を吐きながら街を火の海に変え、人類の科学の結集した兵器によるあらゆる攻撃をはねのけ、人間や文明に敵対することもあるが、地球が宇宙からの脅威に曝されたときは人類の味方にすらなってしまう。何よりも、その存在の誕生を核実験と言う人類の愚行に依拠しているゴジラは、同時に地球そのものの悲痛な叫びを具象化した生物のようですらある。