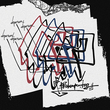Homecomingsが、2018年12月25日、東京・渋谷CLUB QUATTROにてワンマン・ライヴ〈LETTER FROM WHALE LIVING〉を開催した。最新作『WHALE LIVING』のツアー・ファイナルでもあった同公演で、バンドは新旧の名曲を約2時間にわたって演奏。そのパフォーマンスは、日本語詞へと舵を切った『WHALE LIVING』で描いたさりげない優しさに体温を与える一方で、それ以前の楽曲が持つ固有の魅力も際立たせていた。
そのライヴを観ていた1人が、アニメーションの配給会社〈ニューディア―〉の代表であり、著書「21世紀のアニメーションがわかる本」などで知られる評論家、土居伸彰。詳細は後述されるが、Homecomingsのギタリスト、福富優樹が土居の配給したアニメ「大人のためのグリム童話 手をなくした少女」に推薦コメントを寄せるなど以前よりバンドと親交のあった土居は、終演後、昂揚気味に「ホムカミ論を書きたいんすよ~」と周囲に漏らしていたのだ。
この記事は、そんな土居の熱意が晴れて形になったもの。2019年に入って以降も映画「愛がなんだ」への主題歌の提供や、初の展示イヴェント〈COLORING BOOK〉の開催、さらに春にはナイト・フラワーズとのUKツアーの実施がアナウンスされるなど、ホットなニュースに事欠かないHomecomingsだが、土居は彼らのどんなところに魅力を感じているのか? アニメーション畑ならではの〈遠近〉という視点から、つぶさに解析してくれた。 *Mikiki編集部

〈近さ〉にくるまれた〈遠さ〉に触れる体験
Homecomingsの音には〈遠さ〉がある。音を楽しむのは本来〈近さ〉の体験であるはずで、イヤホンで聴けば耳が、ライヴで演奏を聴けば全身がその音の波を受け取る。そこに距離はない。Homecomingsの音にももちろん、音が触れることで染み渡り震わせるような〈近さ〉はある。しかし同時に、遠い何かもある。確かな存在感とともに。
僕は普段、ニューディアーという会社で海外のインディペンデント・アニメーションを日本に紹介している。毎年11月上旬に北海道・新千歳空港で開催される〈新千歳空港国際アニメーション映画祭〉のフェスティヴァル・ディレクターの仕事もしている。この映画祭、昨年の第5回は、Homecomingsと多数の作品でアートワークを担当してきたイラストレーター、サヌキナオヤが共催する音楽と映画のイヴェント〈New Neighbors〉を招聘し、ウェス・アンダーソンの名作「犬ヶ島」(2018年)の爆音上映のあと、Homecomingsのアコースティック・セットによるライヴを披露してもらった。ちなみに、そのプログラムの前には、「リズと青い鳥」(2018年)の爆音上映が、山田尚子監督のゲスト・トーク付きで行われた。言うまでもなく、Homecomingsが主題歌“Songbirds”を提供した映画である。
Mikikiを訪れる人がアニメーションに対してどういうイメージを抱くのかわからないが、僕が扱っているインディペンデント・アニメーションは、たとえば人が〈アニメ〉や〈ハリウッドのアニメーション〉という言葉である程度共通したイメージを持ててしまうのとは異なり、ある特定の絵柄のイメージにおさまりきらない。個人や小規模の集団を中心に制作されるそれらのアニメーションは、作家・作品ごとに異なる世界観を持ち、ヴィジュアルもそれぞれ違い、手法も異なるし、ストーリーテリングの仕方もまちまちだ。作家がいればその数だけ絵柄や世界観がある。
そういったアニメーションと対峙するときには、〈近さ〉と〈遠さ〉が共存する感覚がある。アニメーションは本質的には親しみやすい。複雑で広大なはずの世界が絵になり単純化されるので、観客とのあいだにノイズのないコミュケーションが成立しやすい。一方、インディペンデント作品の場合、そこに内包される世界観は作家に由来した奇妙奇天烈なものであり、簡単に飲み込むことができない。そこには、理解の及ばぬ〈遠さ〉が、確かな質感とともに存在するのだ。〈近さ〉にくるまれた〈遠さ〉に触れる体験――インディペンデント・アニメーションの魅力は、そこにあると僕は考えている。見慣れた、親しんだもののなかにしっかりと感じ取れる違和感が、ときに自分が当たり前としている価値観を揺さぶることがある。いままでとは違った距離感で世界を眺めたり、自分自身の人生について再考させてくれたりする。
Homecomingsの英語の歌詞は、それらがもたらす〈遠さ〉のためにある
しかし、ここで言っておきたいのは、この僕のアニメーション観自体が、インディーの音楽によって育まれてきたということだ。かつて僕はこういうテキストを書いたことがある。その概要を伝えれば、想像もしなかったような音の鳴り方に直面することによって、いままで観たことのなかった景色を観る経験を、音楽がもたらしてくれたということである。それもまた、〈近さ〉と〈遠さ〉の共存である。とりわけ僕はSSW的な音が好きで(エリオット・スミスやニック・ドレイク、スパークルホース……)、それらのミュージシャンの音楽は直接的に琴線に触れてくるが、同時に、自閉的な異質さをも感じ取らせる。
その音を紡ぐ人たちの存在の愛らしさ・チャーミングさと、どこか謎めいたものの共存。それらの音は、当人たちにとっては圧倒的とも言っていいくらいに整合性も一貫性もあるにちがいない。でも、それを必ずしも共有しきれない感じもつきまとう。自分だけがわかる言葉で、自分に向けた独り言のようにして、届けられない手紙のようにして、紡がれるそんな音。
さらにいえば、日本人として彼らの音を聴くとき、言語の問題ゆえにその〈遠さ〉はさらに増す。対して、英語詞が持つ〈遠さ〉が、SSW/インディーの持つ自閉性・異質さを日本人リスナーにとって増幅させる。言葉の意味が(直接的に)入ってこないことにより、彼らの歌う声は、抽象的な音として受け止められる。ときおり脳に入り込んでくる断片的な言葉が、漠然としたなにかをイメージさせる。
僕がHomecomingsの音楽に親しみを感じるのは、海外のインディー表現に触れるときに内包される二重の距離感が、その音に落とし込まれているように思えるからだ。Homecomingsの英語の歌詞も、それらの音楽がもたらす〈遠さ〉のために必要とされているように思える。〈遠さ〉ゆえの仕掛けもある。彼らの英語詞は、彼ら自身も何度か語っているように、歌詞の内容を一歩読み込ませるための仕掛けを内包しているし、さまざまなMVやブックレットにおいて、その英語詞が日本語に文字として翻訳されたときの〈詩的〉とも言っていいような変容は、英語詞の〈遠さ〉だからこそありえる発明のようなやり方である。英語詞の入ってこなさが、声が音として抽象性に響かせて、だからこそありえる、大きな変容をもたらす。

惰性で聴くと何かを逃した気にさせる音楽
Homecomingsが奏でるのは〈距離〉の音楽である。変わらない4人のメンバーが鳴らす音は、どの時代の音源を聴いてもこの人の音である。しかし同時に、ファースト、セカンド、サード(さらにはそのあいだに挟まれるEPや平賀さち枝とのコラボなど)、どの2枚のあいだの距離を測っても、驚くほどにそれぞれが〈遠い〉ようにも思える。あるアルバムがこの形容でこのジャンルにおさまるものだとすれば、次の新譜はその想定を裏切ってくる。
僕自身はセカンド以降の比較的新しいファンだが、そこからEP『SYMPHONY』(2017年)の“PLAY YARD SYMPHONY”を初めて聴いたとき、さらにそこから「リズと青い鳥」の主題歌“Songbirds”を聴いたとき、さらに『WHALE LIVING』(2018年)のリード・シングル“Blue Hour”を聴いたとき、少し戸惑ったことを覚えている。音がものすごく変わったわけではない。あのいつものHomecomingsの音である。しかし、何かが圧倒的に変わっているような感じがする。まるで、すべてが組み立て直されたかのような。次のフェーズに入るとき、Homecomingsは、自分たちの輪郭は変えないままで、音の価値観を毎度作り直しているような気がするのだ。その作業によって、次第にスケール感が上がっていくような。
おもしろいのは、最初に聴いたときの戸惑いは、数回聴いたあとには、これ以上なくしっくりときて、いままで以上にえぐられる音として、リスナーとしての僕の身体に刻み込まれることである。よく考えればよく考えるほど、よく聴き込めば聴き込むほどに、この音の鳴らし方しかありえないことが次第にわかってくるのだ。おそらくそれは、Homecomingsが新たに見つけ出した必然性を、理解したということなのだ。いままでとは違った角度から組み立て直して、そして常にHomecomingsの音という変わらないコアが作り上げられたことに。だからHomecomingsを惰性で聴くと何かを逃した気がしてくる。そこには常にイメージを裏切る揺らぎがあり、しかし、その揺らぎのなかに硬い必然性がある。