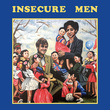昨年は音楽メディアでファット・ホワイト・ファミリー(以下FWF)の名前を目にする機会がとても多かった。そして彼らの名前と共に記されていたのが、〈サウス・ロンドン〉という現在のUKロックにおける一大発信拠点だ。FWFの名はそのシーンを語る際の枕詞のひとつとしてたびたび登場してきたが、記事の主役はシェイムやゴート・ガールなど同じサウス・ロンドン出身の若手バンドだったりする場合がほとんど。シーンが表立って盛り上がりはじめたタイミングでは、当時の彼らの最新作だったセカンド・アルバム『Songs For Our Mothers』(2016年)はリリースから2年ほど経過しており、2011年より活動しているというキャリアも含めてフレッシュな存在とは言えなかったから、それも仕方がないのか。しかし2019年春、ようやくこのサウス・ロンドンのボスにスポットライトが当たろうとしている。所属レーベルをドミノに移したFWFが、3年ぶりとなる3枚目のニュー・アルバム『Serfs Up!』を携えて帰ってきたのだ。
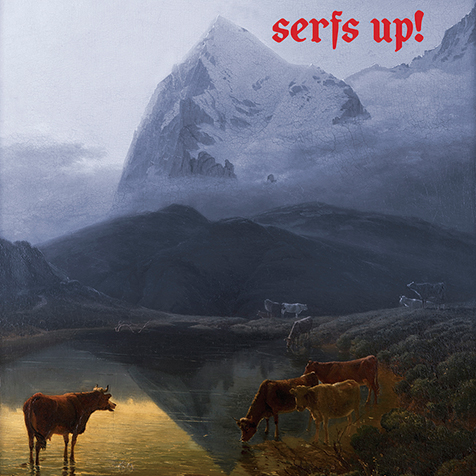
「俺たちが活動をスタートさせた頃は、まだあまりサウス・ロンドンにDIYシーンがなかったと思う。音楽はイースト・ロンドンのほうが盛んだったしな。周りの連中とはちょっと違っていた俺たちは、みんなに阻害されながらも自分たちのやりたいことをやり続けたんだ」。
そう語るのは、フロントマンのリアス・サウディ(以下同)。続けて「気付いたらゴート・ガールとかシェイムとかそういったバンドが俺たちに続いて出てきた。俺たちにとって弟や妹みたいな存在だね」と話してくれた。
結成当初のFWFはジェントリフィケーション(再開発などによる地価の高騰化)が進む前の不穏なサウス・ロンドンでスクワット(不法占拠)しながら共同生活し、いまやムーヴメントの中心地となっているブリクストンのライヴハウス、ウィンドミルを根城に音楽活動を繰り広げていた。ライヴ会場を次々と破壊とするほど凶暴なパフォーマンス、過激なリリックと言動、そして混沌としたサイケデリック・サウンドは、リアスが言う〈阻害された〉ものではなく、名誉ある孤立だったと筆者は考えている。それだけFWFには独自性があり、聴く者に強烈な印象を植えつけるが、今作はさまざまな音楽性が交差し、混沌としている点では変わらないものの、ずいぶんと音が整理されて聴きやすくなった印象だ。
「俺たちの楽曲は常にポップであり続けてきたと思うんだけどな(笑)。そのうえで、リスナーや音楽業界に対して攻撃的かつ反抗的なものじゃなく、人を惹きつけ、自分自身をもっと素直に表現したものが少しずつ作れるようになっていき、今回のアルバムまで辿り着けた。よりコミュニケーションが取れる音楽を作れるようになったと思うね」。
『Serfs Up!』も大まかに〈サイケ・ロック〉とカテゴライズできる。しかしながら、いわゆるサイケな音というわけではない。60年代のポップスからグラム・ロック、レゲエ/ダブ、フュージョン、ファンクなど形を変えながら詰め込まれたカオスな演奏が、ドラッギーなムードを醸し出していると言っていい。
「俺たちはさまざまなタイプのレコードを聴くからな。このアルバムには聴いてきたレコードの影響がすべて落とし込まれている。ファンクもあるし、テクノもあるし、フォークもあるし、カニエ・ウェストっぽいものもあるし、インスピレーション源は計り知れないよ。なかでもよく聴いていたのはワム!の“Blue(Armed With Love)”。あの曲は俺たちが聴いていたなかでもっとも重要な作品だと言えるね。凄く刺激を受けたんだ。ぜひ聴いてみてくれ。あと、ジャー・ウォブルもたくさん聴いていたな」。
時代もジャンルもマーケティングもへったくれもない。大事なのは己が本能的に正しいと感じるものだけ――そんなプリミティヴな感覚を貫くFWFがいま、テムズ川を北に渡り、英国全土を、そして世界中を席巻しようとしている。
ファット・ホワイト・ファミリー
リアス・サウディ(ヴォーカル)、ソウル・アダムチェイスキー(ギター)、ネイサン・サウディ(キーボード)から成る3人組。2011年にサウス・ロンドンで結成。共同生活を送りながら精力的なライヴ活動を展開し、2013年にトラッシュマウスからファースト・アルバム『Champagne Holocaust』を、2016年にウィズアウト・コンセントから2作目『Songs For Our Mothers』を発表する。同年末にドミノへ移籍し、2017年に映画「T2 トレインスポッティング」のサントラに参加して知名度を上げる。元テンプルズのサミュエル・トムズ(ドラムス)がサポート・メンバーとして加入したことも話題を呼ぶなか、このたびニュー・アルバム『Serfs Up!』(Domino/BEAT)をリリースしたばかり。