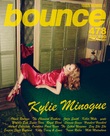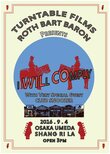揺れ動く世界のなかで、憎しみを超えて響く〈歓喜の歌〉——実験的な試みを重ねながら豊かな創造性を磨き続けてきたシカゴの雄が壮大なニュー・アルバムを完成!
そうか、約3年ぶりになるのか。ここ1年ぐらいを振り返ると、オリジナル・アルバムということでは初作となる『Warm』に加えて、そのスピンオフ的な『Warmer』というジェフ・トゥイーディーの美しいソロ作が世に放たれて。それからノラ・ジョーンズの最新作『Begin Again』では、これぞオルタナ・カントリー!といった共作曲“A Song With No Name”も聴かせるなど、彼の充実した活動ぶりに幾度となく心が躍らされたもの。それからネルス・クラインはというと、新プロジェクトのネルス・クライン4で初アルバム『The Brother's Sister's Daughter』を出したかと思えば、最近は妻の本田ゆかと新たに組んだデュオ、CUPの音源を届けてくれたり。次はどのメンバーからどんなお知らせが届くのか、とワクワクし通しだったもので、あまりブランクを感じていないのが正直なところなのだけど、やっぱり格別なものがあるな。偉大なるマザーシップ、ウィルコの新作を受け取ることで得られるこの胸の高鳴りは。
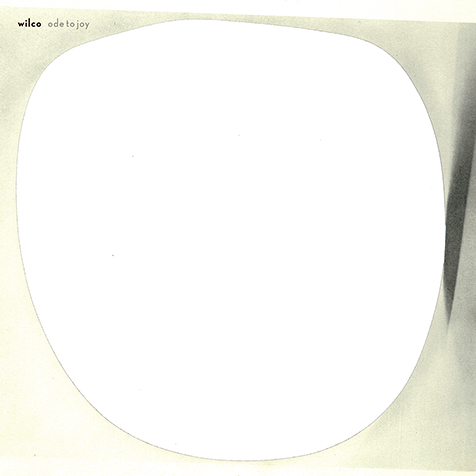
ウィルコの通算11作目『Ode To Joy』。〈歓喜の歌〉という意味を持つこの新作を聴きはじめたところ、反射的に前作『Schimilco』の内容が鮮明に甦ってきた。そこには伝統的なフォーク・ソングやカントリーのフォーマットを持つアコースティックな楽曲が集められており、彼ららしいオブスキュアな音作りも施されて一風変わった作品に仕上がっていたが、全体的に地味かも、という評価が一般的だったように思う。なんだか気怠いムードが全体を包んでいたっけ、って印象がいま強く感じられるのだが、思わずそんなことを思い出したのは、この新作の入り口あたりにもまた同様の雰囲気が漂っていたから。ただし、曲が進んでいくと、違った感触が芽生えてくる。とにかく今回は骨太なのである。ひねくれたセンスも存分に塗してあるが、シンプルに曲の骨格を考えたアレンジが随所で成されていて、ガツンとくる聴き応えがあるのだ。
レコーディング及びミックスダウンが行われたのは、彼らのホームグラウンドであるザ・ロフト。古い友と語らうような親密な空気は、オープニングを飾るメロウなミディアム・ナンバー“Bright Leaves”から濃厚だ。まずグッとくるのは、じっくりと語りかけるようなグレン・コッチェのドラム・プレイで、無条件に〈これこれ!〉という感慨をもたらしてくれる。それにしても、なんと雄弁なビートであることよ。どこまでも荒々しく乾いていて、歪みの角度が鋭い。
そんなドラムの響きはゆったりとした曲調がメインとなった本作の基調音と言えるもので、鋭くも滑らかな刺激を与えてくれる。一方ジェフの歌声といえば、やけにビターなフォーク・チューン“Before Us”や独特な浮遊感を醸し出す“Quiet Amplifier”など、オーガニックなビートのなかを縫うようにして泳いでいるのだが、パーソナルな手触りのソロ作で得られたものとは確実に異なる複雑な模様を生み出していて、とにかく魅力的。
ネルス・クラインのフリーキーでノイジーなギターがのたうつヘヴィーな“We Are Lucky”や先行シングル曲となった牧歌的な“Love Is Everywhere(Beware)”など、穏やかな流れと激しい風が緩やかに交錯しながら何とも言えない心地良い揺らぎを生み出している。
そんなアルバムの内容についてジェフ・トゥイーディーは「一枚岩のようにがっしりと固まった構成にデリケートな感情がぶら下がった、本当に壮大なフォーク・ソングから成り立っている」のだと語っているが、柔靭という表現がもっとも適当なバンド・サウンドといい、ここにきてさらなる表現力を携えたウィルコのすごさを如実に物語る作品となっている。これらの新曲がステージ上でどうやって再現されるのか。次なる来日公演への期待も思いっきり高まるというものだろう。
ウィルコの近作を紹介。
関連盤を紹介。