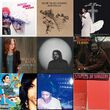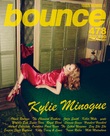KNOCK ON THE DOOR
[ 特集 ]理想の〈アメリカ〉を求めて
アメリカがどこへ向かおうとも、アメリカーナはいつだってここにある。先行きの見えない時代だからこそ、ルーツに根差した音楽と旅に出ないかい?
★Pt.1 FLEET FOXES『Crack-Up』
★Pt.3 DAN AUERBACH『Waiting On A Song』
★Pt.4 SUFJAN STEVENS/BRYCE DESSNER/NICO MUHLY/JAMES McALISTER 『Planetarium』
★Pt.5 「American Epic」と巡る1920年代の米国/ジョン・フェイヒーに愛を込めて
★Pt.6 ディスクガイド

JEFF TWEEDY
かつてボブ・マーリーは、自身の曲を再録音することについて、「時間が経つことで理解が深まる。最初はインスピレーション、次が理解だ」と語り、「曲は進化する」とも言った。ジェフ・トゥイーディも同じような思いに駆られ、形にしたくなったのだろうか?
ウィルコのバンドとしての在り方は、理想的ではないだろうか。メンバー各人が高いスキルを持ち、実家(ウィルコ)以外にもそのスキルを活かして心地良く過ごせる場所があり、そこで過ごす自由が保証されている。彼らが長きに渡って〈最強のラインナップ〉を維持できている理由のひとつは、これだ。昨年、英The Independent紙の取材でジェフは以下のように話している。
「ウィルコはどんどん良くなっているよ。僕たちのミュージシャンとしての関係は、より良くなっていて、僕の創作に対する熱意とエネルギーは強まっているんだ」。

実家が安泰であれば、課外活動もしやすい。近年のジェフは、メイヴィス・ステイプルズやリチャード・トンプソンなどのプロデュースを手掛ける一方、息子のスペンサーらと組んだトゥイーディでアルバム『Sukierae』を作り、ツアーもした。さて、次は何かな? その答えが全編アコースティックのセルフ・カヴァー集『Together At Last』だ。ウィルコの2016年作『Schmilco』が生音を主体にしていたこと、そして先頃リリースされたジェフの最新プロデュース作品であるジョアン・シェリーの『Joan Shelley』もオーガニックなフォーク・ポップ盤であったことを考えると、何となくいまはそういう流れなのかもと思えたりして。
90年代半ばより、折に触れソロ・ライヴを行なってきたジェフだが、ソロ名義で作品を出すのはこれが初めて。ジム・オルークやグレン・コッチェ(ウィルコ)と組んだルース・ファーの“Laminated Cat”と、ゲイリー・ルーリス(ジェイホークス)やダン・マーフィー(元ソウル・アサイラム)らと集ったゴールデン・スモッグの“Lost Love”を除いた9曲は、ウィルコの既発曲を取り上げている。その中には、昨年のトゥイーディによる来日公演でジェフが弾き語りを披露した“Via Chicago”“I'm Trying To Break Your Heart”“Hummingbird”も含む。
オリジナルは麗しいピアノとノイズを絡めた風変わりなバラードなのに、近年の本隊のライヴでは過剰なまでの静と動のコントラストで壮絶なカオスを生み出し、観客を熱狂させてきた“Via Chicago”を筆頭に、曲のすっぴんを見ている思いだ。各々味のあるすっぴんを。
目の前にジェフが座っているような、親密な空気に包まれながら本作を聴き進める。少々声が上ずろうが掠れようが、ポップな曲も、メロウな曲も、チャーミングな曲も、やるせない曲も、すべてのナンバーで洗練味や素朴さ、エキセントリシティーを自在に操るメロディーメイカー、ジェフのセンスが控えめに光っている。一旦ジェフの手を離れ、ウィルコに育てられた曲たちが、ふたたび彼の手に戻った時、こんなにも無防備で素朴な表情を見せるのか……と愛おしさを感じずにはいられない。そんなアルバムだ。
『Together At Last』でカヴァーした曲のオリジナルが聴けるアルバム。