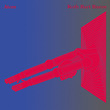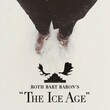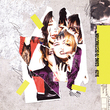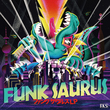光の粒が散らばっているような、緩やかなコミュニティー
――優河さんをフィーチャーした9曲目の“ウォーデンクリフのささやき”は、ピアノと電子音による冒頭から歌へ入っていく流れがとても美しい。以前、〈自分を癒すため個人的にアンビエントばかり作っている〉と言ってましたが、そういう要素もバンドの音楽へ流れ込んでいるんでしょうか?
「ここ最近ジワジワ侵食され始めている感覚はありますね。この曲は、来年5月に僕らが生まれ育った地元にある〈めぐろパーシモホール〉でツアー・ファイナル公演をやることを想定して作ったものなんです。そういう広がりを持った空間に相応しい曲が足りないんじゃないか、と中原(鉄也/ドラマー)と話しているなかで、自宅スタジオでピアノを触りながら作り始めたらススっと5分くらいで出来たんです。アルバムが求めていたパーツはこれだ!って感じで」
――アレンジもはじめから見えていた?
「生ドラムも試したんですけど、どうもしっくりこなくて。ピアノはクリックに合わせずリッチに鳴っているけど、ドラムはマシーン的な反復を繰り返すみたいなところに終着しました。その他の楽器もそういった構造に呼応するようにカットアップされているんだけど、全体としては有機的なものを作りたかったんです」
――たしかに、バウンシーなリズムも、これまでのROTH BART BARONにはあまりなかったような新鮮さを感じました。
「目立つか目立たないギリギリのところでリズムが跳ねていて、クラーベとかも駆使しながらけっこう複雑に構築されているんです。これは優河ちゃんの声がすごく合うだろうなあと思っていたんですが、やっぱり絶妙にハマりましたね」
――普段の彼女の作品にはあまりなさそうな曲調だからこそ、かえって新鮮なおもしろさがありました。
「うんうん」
――そして、ラスト曲“iki”では他の曲に参加していた女声コーラスもみな勢揃いして、まさにアルバムの大団円感があります。
「この曲は元々クリスマス企画として2018年にアップしていた曲だったんですが、それをファンの皆さんにすごく気に入ってもらえて。〈なんでライヴでやらないんだ?〉とか、〈アルバムに入れるべきだ!〉とか怒られて(笑)」
――歌詞の面でもアルバムの他曲の世界観と少し違っているように聴こえますね。でも、こうした曲がラストに入っていることで救いのようなものも見えてくる。
「10年代が終わりを迎え新たな10年を迎えるという空気感を、あくまで希望のある形で提示したかったんです。1人の人間が見つける希望や、もっと大きく、時代が未来へ向かっていくなかでの希望……その一方で絶望感も入っているような……。そういう複層的な感情が現れている曲だから、このアルバムを締めくくるのに相応しいんじゃないかと思ったんです」
――みんなで歌っていることによるクワイア的な感じも、今バンドがいろいろな人たちと繋がりながら活動を行っているということの象徴のようにも聴こえました。
「声を張り上げて〈がんばっていこう!〉とかじゃなくて、ちょっと不安感も漂っている。サポート・メンバーの誰かが〈ノアの箱舟みたいな感じもするよね〉って言っていて……(笑)。嵐を経て、舟がバラバラになる不穏な予感を抱きながらも、緩やかな集合として豊かに歌っているという。なんだろう、それこそプラネタリウムのように、光の粒がそこここにポツ、ポツ、とあるみたいなイメージ」
――多様性というものがノンストレスな形でそこに存在しうるということが、ひとつの音楽として提示されている感じ。だからこそ仄かな希望を感じるんだと思いました。
「そう聴こえれば嬉しいですね」

人間のことを歌いたくない
――アルバムのテーマとして、なんというか……全編を通して人間同士のやりとりだったり、社会的な現実から離れたいという欲求が反映されているのかなと思ったんですが。
「それはあると思う。とにかく今回は人間のことを歌いたくない、って思ったんです。日々のニュースとか、ネット上で話題になっていることとかって、当たり前ではあるんですけど、人間についての話しかないな、と思って。例えば大規模な山火事とか、こないだの大きな台風とかで少しそれ以外の視野へ連れられるけど、やっぱり人間についての話に戻っていく。
例えば、こないだグレタ・トゥーンベリによる国連気候行動サミットでの演説があったときも、地球環境が深刻な状況に陥っているという事実をもとにした建設的な議論が発展していくわけじゃなくて、彼女の属性をあげつらうような、〈人間についての話〉にスライドしていってしまう…。いや、それはおかしいだろう、と。地球がマズいことになっているということは大前提としてあるわけだし、別に誰が訴えたかとかは本質には関係ない話であって」
――誰と誰が対立して、どういう人間がどういう意見かを持っているかが、加速度的にクローズ・アップされてしまう……。
「そう。当初SNSに期待されていた対話の可能性とそれによって繋がった人たちもいると思うんですが、むしろ実際に起こったことといったら、そこでの関係性が過剰に可視化されて、小さい島がたくさん出来てしまったということだと思うんです。すべてのイシューについて〈イエス or ノー〉で区分けされていって、グレーの部分がないっていうか。それを断絶というなら、まさにそうだな、と。でも、そこを見て見ぬふりをするわけじゃなくて、人間以外へ目を向けてみることで、緩衝地帯を見つける、というか」