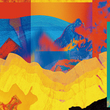前作『極彩色の祝祭』(2020年)を発表して以降、厳しい状況のなかで、精力的にライブやイベント、それらの配信など様々な活動を展開してきたROTH BART BARON。彼らはこの困難な時代を、音楽を通じてサバイブしてきた。そんななかでリリースされた新作『無限のHAKU』は、パンデミックで大きく変わった社会に目を向けた再生のアルバムだ。極彩色から白(HAKU)へ。イメージもサウンドも対照的だが、兄弟のような結びつきも感じさせる新作について三船雅也に話を訊いた。

枯山水の世界をポップミュージックで描く
――ROTH BART BARONは緊急事態宣言下で様々な活動を行なってきましたが、新作にも取り掛かっていたというのが驚きです。
「去年の12月の(めぐろ)パーシモンホールでのライブが終わった頃から、ぼんやりと新作のことを考えていたんです。曲は常に作っていて、あぶくみたいにポツポツ出てくるもののなかから綺麗な石を見つけるようにして、引っかかったアイデアをひとまず引き出しのなかにしまっておく。そして、アルバムを作るときにそれを取り出して仕上げていくんです」
――アルバムの方向が見えてから曲を仕上げていく?
「今の自分の気分とか、自分のまわりの人たちの気持ちとか、普段生活してる町のムードみたいなのを感じながら、〈次の世界ではどんな音が鳴ってるのかな?〉とか〈俺は何を鳴らしたいのかな?〉みたいなことをいつも考えていて。〈次はこうなんじゃないか?〉みたいなものが見えてきてから、メンバーを集めてセッションを始めるんです」
――今回のアルバムに取り掛かるときに見えてきたのは、どんなものだったのでしょう。
「枯山水の世界でした。前作は極彩色でしたが、今回は白のレイヤーを重ねていく感じ。そこにはいろんな白が、感情が渦巻いている。それに白って一見綺麗だけど、どこか緊張感があるじゃないですか。死装束は白だし、白は汚れを一切排除するような強い意思も感じさせる」
――白=〈HAKU〉、ということ?
「それもあります。でも、〈HAKU(はく)〉は〈吐く〉でもあり、〈迫〉とか〈拍〉とか、いろんな意味に取れる。たった2文字の言葉なのに、そこにはいろんな意味があって、綺麗な言葉にも汚い言葉にもなるんです。それが白のレイヤーを作りたい、という感覚になっていったんですよね。今の世の中って白と黒だけで、グレイな領域がなくなってしまった。みんな絶対的な正義みたいな純白を信じていて、その白さにがんじがらめになっている気がするんです。白のなかにも複雑なレイヤーがあるはずなのに」
――白の複雑なレイヤーをサウンドで表現するのは難しそうですね。
「最初は極めてシンプルにして、音の素材の美しさを際立たせたものにしようと思っていました。もっと地味でシンプルなアルバムになるはずだったんです」
――前作がエネルギーに溢れていたのに対して。
『極彩色の祝祭』は生命の危機本能が作らせたアルバムで、未知なるウイルスとの闘いに向けたものだったんです」
――「もののけ姫」じゃないけれど〈生きろ!〉っていう(笑)。
「あるいは、〈死んでしまえばいいのに〉とは言えない感じというか(笑)」
――パンデミックな状況のなかで「エヴァンゲリオン」的な気分にはなれなかったわけですね。
「90年代って、大人たちは〈死ぬ〉ってことばかり言ってきた気がするんです。僕はそんななかで幼少期を過ごしてきたんですけど、『シン・エヴァンゲリオン』を観ると、庵野さんなりに〈生きろ〉って言ってる気がしました」
――確かに。やっぱり現実に死が迫ってくると、そう簡単に〈死ぬ〉とは言えない。生存本能が起動するんでしょうね。
「そう。前作が闘いに向けたアルバムだったとしたら。新作は人間がコロナという転換期を迎えたなかで、ゆっくりと生まれ変わる準備をしている感じというか。シンプルで小さな空間のなかで、お茶を飲んで何かを感じているような作品にしようと思いました。その空間をしっかりとデザインしたい。ゆるやかでありながら緊張感もある空間にしたかったんです。そういう、ある意味アンビエントな空間を、ポップミュージックというフォーマットで作りたいと思っていました」
――それはとてもデリケートな作業ですね。
「すごく難しい作業でした。曲自体はシンプルで力強いけど、音は繊細に作り込んでいく。『極彩色の祝祭』はメンバーみんなで大きな筆を一緒に持って、荒々しい書体で一筆描きしたような肉体的なアルバムだったんです。今回は指先に神経を集中させて、和紙を一枚一枚貼っていくように音を重ねていきました。でも、作り込みすぎて聴き手に息苦しさを感じさせてしまうとダメで。曲を聴いた人が、この部屋なら入ってみたいな、と思えるような空間を目指しました」