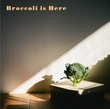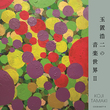満足いくまでやるのがスタジオ派
冨田「Orangeadeの制作はどうやって進めていったんですか?」
Orangeadeスタッフ「ドラムなどはレコーディング・スタジオで録って、それ以外のウワモノはリハーサル・スタジオなどでひとつひとつ録っていく感じでした」
冨田「でも、そうは聴こえませんね。普通にレコーディングした音に聴こえる。リハスタでマイクを立てて録ったとしても、エンジニアリングの心得がある人が録ってミックスしていれば、大丈夫なことは多いんですよね」
岡村「さきほど冨田さんがおっしゃったのは、記録として録音作品を作っている人と、スタジオに主眼を置いて作っている人たちの差が絶対的に大きい、っていうことですか?」
冨田「もちろん良し悪しではないけど、はっきりとちがいますね。バンドでのパフォームやアンサンブルが起点になってそれを整理したり、そこに何かを加えて完成させたりしていくアプローチの人たちと、最初から、スピーカーから出て来る最終形を目指して録音を始めるような人たちとでは、ちがう質のものになりますよね」
岡村「Orangeadeのようにスタジオ派だと感じる人たちはいますか?」
冨田「うーん、あまり思い浮かばないですね。音楽的におもしろいと思う作品はありますが、スタジオ派と言われるとわからない。ライヴとそれほど乖離しているバンドが少ないからかな。録音優先に感じる人は、バンドではないことが多いですね。工夫を感じるものはR&Bやヒップホップのほうが多いんです」
岡村「例えば、ceroはいかがでしょう?」
冨田「ここ数年の彼らしかわからないけど、スタジオ派っていう感じはしないですね。さっきの説明と重複するけど、根本的なアイデアや作曲は別にして、実際のバンド演奏やアンサンブルをやるうちに膨らませていった部分も多い感じがする。レコーディングを見たことはないので、想像ですけど(笑)。
あと、ceroとOrangeadeは音楽構造が全然ちがいますよね。Orangeadeはアレンジャーが(楽譜に)書いた分量が多い音楽に聴こえる」
岡村「たしかに、ライヴで再現できないアレンジだからこそおもしろいんだっていう発想になると、スタジオでの作業に走ると思います。バンドにアレンジャー的感覚を持っている人がいるかいないかっていうのは大きいかもしれないですね」
冨田「Orangeadeはアレンジャーが複数いるバンドなわけですよね。編成とかライヴのことなどまったく頭にないというか、モニター・スピーカーで聴いて満足いくまでなんでもやるのがスタジオ派なんでしょう(笑)」
岡村「Orangeadeのメンバーには、〈ソングライター〉というよりも〈コンポーザー〉的な感覚があると思うんです。再現できるかできないかは措いて、書いた曲の面倒を最後まで見る、と言いますか。だから、誰かから意見を言われて修正するとか、そういう柔軟さをを持っている人がどれだけいるのかが気になります(笑)」
冨田「特に若い頃はね(笑)。僕も柔軟だったとはまったく言えないです(笑)」
岡村「そういうエゴ、私は全然嫌いじゃないです(笑)。バンドの民主的なあり方はそのエゴをうまく調整して、ハッピーなサプライズを起こせるどうかにかかっていますよね。でも、スタジオ派ミュージシャンはある程度計算して、最終的な青写真を描いて、どうやってそこへ近づけていくのかを考える。そして、サプライズがあったときにどう対応するか……ですよね」
冨田「僕がいいなって思う音楽は、その両面がある音楽なんです。だから、書かれすぎている音楽って好きじゃない。僕はリズム隊を全部自分で演奏するじゃないですか。あれは、ウワモノはアレンジャーが書いて、リズム隊は好きなプレイヤーがコード譜を見ながらプレイしたような音楽が、僕の好みだからなんです。そしてそのリズム隊にも音符的、ニュアンス的に明確な嗜好がある。そうすると、音符を書いて人にやらせるのじゃダメなんですよ。
大沢さんはベースも弾くけど、鍵盤も弾きますよね。詳しくはわからないけど、コントロール・フリーク気味なところはあると思う。僕もそれ気味だけど(笑)。なので、マルチ・プレイヤーの作品っていう印象も受けました。
Orangeadeには、そういう人が複数いるって言うことですからね。昔は適度に役割分担できている集団はバンドになって、一人でいろいろやりたい個人は宅録だったんですけどね」