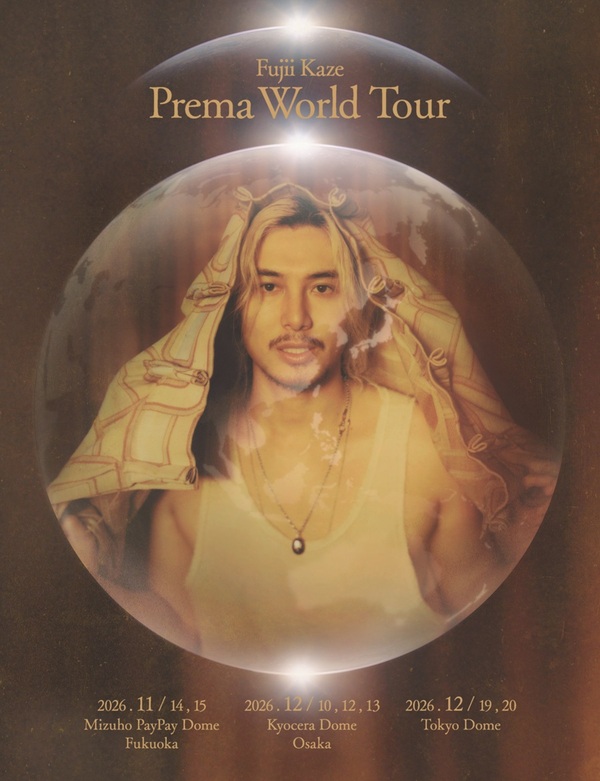ハワイと沖縄を結んだ『ハワイ・チャンプルー』
――そういうOZに流れていたムードをアルバムに反映させようとしたわけですね。その時代にプレイしたり、聴いていたりした音楽のエッセンスの集大成的な『サンセット・ギャング』を経て、次作の『ハワイ・チャンプルー』(75年)になると、かなり明確な夕焼け楽団サウンドが打ち出されてきますね。

「『サンセット・ギャング』を出したあと、久しぶりにアメリカに行ったんだ。昔は原盤が完成すると、リリースまで3、4か月ほどの期間があってさ、6月にミックスが終わり、もらったギャラを持って7、8、9と3か月ぐらい行ってた。で、帰ってきてからプロモーション活動をしたんだけど、その帰りにハワイに初めて行ったんだ。その体験があまりに強烈でね。
で、年の暮れには沖縄にも行き、そこでも衝撃を受けて、やがてハワイと沖縄を結ぶ線がつながったんだ。で、新しいアルバムはそのまま『ハワイ・チャンプルー』となったわけ。旅先ではしっかりネタを仕込んできたんだけど、帰ってきてから話しても誰も相手にしてくれなかった。そんななか唯一喜んでくれたのが細野さん」
――西表島を旅している途中、バスのなかで偶然耳にした喜納昌吉&チャンプルーズの“ハイサイおじさん”についてのエピソードですね。お土産に買ってきたシングルにいちばん反応したのが細野さんで、彼が提唱した〈チャンキー・ミュージック〉の方向性にも多大な影響を与えたという。新作は麻琴さんの頭の中に渦巻いていたものを形にしよう、というテーマがあったんですか。
「まぁ、そういったとこかな」

――スティール・ギターのコマコさん(駒沢裕城)の活躍ぶりもさることながら、共同プロデューサーでもある細野さんのドラム・プレイが素晴らしく、作品の軸となっていることは間違いない。
「いやぁ、あの人はリズムマンだよな。ベースでもドラムでも楽器はなんだっていいんだよ。歌い手としても実際に歌いやすいんですよ、細野さんのドラムって。リハ始めたときから、すごいよ、バッチリじゃん!ってなってね。
あの感じに似ているのは、伊藤大地くん。歌と共存したビートを叩き出せるということでは細野さん以来のドラマー。楽器を叩いているというんじゃなくて、心の中で歌をうたってるんですよ。シンギング・ドラム。大地くんって口笛吹きながら叩いたりするんだけど、それって頭のなかでメロディーが鳴っているってことなんだよね。細野さんも同様で、ポール・マッカートニーみたいに歌いながらベースを弾いているみたいでしょ?」
――ハイライトとも言っていい“ハイサイおじさん”のカヴァーですが、イントロにフィーチャーされた沖縄民謡“てぃんさぐぬ花”の演奏がアンビエントを先取りしていたって事実にも驚かされましたし。
「何にも考えずにやってたよ。ビックリしたのは、ジャマイカでミックスし直したときに、私のヴォーカル・トラックにメンバーの演奏が入っていたこと。つまり歌も演奏も同時にやっていたってことに気づいたんです。だからスタジオ・ライブなの、アレも」
――イントロだけあとで付けたわけじゃないんですね?
「違う違う。ちゃんとあのスティール・ギターの演奏から曲を始めているから。それは今回の3枚とも9割方そうなんだよ。それにしてはずいぶん綺麗に録れているなって思う」
――間違いなくその制作方法があのアルバムにおけるマジックの源泉となっていますよね。
「残念なのはマスタリングをアメリカでやれば良かったのに、そういう知恵が当時はなかったんだよね。昨日のオンエアでも、音が良い、コレなに!?って声がたくさんあがってたけど、オリジナルのアナログ・レコードを持っている人がそう言っているわけじゃない? そういうことなんですよ。だから40何年の時を経て、やっと完成した、っていうとヘンだけど、ようやく画龍点睛できたんだね(笑)」
ライ・クーダーやデヴィッド・リンドレーとの思い出
――スペシャル・サンクスの欄にライ・クーダー※の名前がありますね。
「ハワイへ行く前、私とケンちゃん(井上憲一)がロサンゼルスに寄ったんですよ。そこでふたりがギターを買うんだけど、ライがすべて手配してくれたわけ。1日楽器屋につき合ってくれて」
――もともとライとの出会いって?
「あんまりおぼえてないんだよな。初めて会ったのがそのときなのか、その前に一回会ってたのか。『ハワイ・チャンプルー』のレイアウトを担当してくれた田中汪臣さんは、クイックフォックスって出版社をやっていて細野さんや高田渡の古くからの友達でね、彼がどっかでライに紹介してくれた。その後『ハワイ・チャンプルー』のレコードは彼に送ったよ。そのときはもうギャビー・パヒヌイのレコード※が出ていた。だからハワイにかなり詳しいわけですよ。
スラック・キー・ギターにも詳しくて、楽器屋で実演してくれた。ハワイはこうやってチューニングするんだよ、って。でも企業秘密のチューニングだから、こちらにわからないようにすぐに弦を緩めてしまっていたけどね。で、私もギャビーに会えるかな、でも彼はきっと道路工事に出てるだろう、なんて話してた。
なんか縁があるんだね。夕焼け楽団である野外フェスに出たときに対バンにデヴィッド・リンドレー※がいて、私らが“ハイサイおじさん”をやったら、何なのそれ!?って興奮した彼が楽屋に飛んできたんだ。で、たしかライとリンドレーのツアーのときに、昌吉を楽屋に呼んだこともあった。昌吉はすでにそこでライと知己を得ているわけです」
――『BLOOD LINE』誕生の萌芽がそこにあったわけですね。あれも録音はハワイでしたね。
「楽器3本手持ちで、ライがひとりでホノルルにやってきた。そういったハワイ・コネクションがあったんだよ。で、74年は学園祭やライブハウスなどをまわっていたんだけど、75年になるとエリック・クラプトンの前座で武道館に立っていたからね。それからはホールでもやるようになるし、だんだんキャパがデカくなっていくんだ」