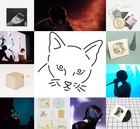現代音楽の流れにありつつ、自然な心地よさを喚起するもの
――今回のアルバムは収録曲の曲調は様々ですが、全体としてはECMが現代音楽を扱った〈ニュー・シリーズ〉を彷彿させる、耽美的なサウンドで統一されているようにも感じました。作品を制作するにあたって、インスピレーションを得た音楽などはありましたか?
「曲ごとになんとなくヒントになるような音楽はありました。たとえば2曲目の“Ditty”は、ピアノの右手と声が完全に同じラインで連動するんですが、ヴァイオリンって顎で固定するので声を出しながら弾くのがとても難しい楽器なんですよね。もちろんチェコのイヴァ・ビトヴァみたいにできる人もいますけど、訓練を積まないとなかなか難しくて。なのでピアノとかコントラバスとか、声を出しながら演奏できる人たちの音楽がヒントにはなっています」
――“Ditty”の声とピアノのユニゾンはブラジル音楽や現代ジャズとも通じる感触もありました。事前にメロディーラインを作曲しないとできない演奏とも言えますが、反対に即興的な演奏を丸ごと収録したトラックもあるのでしょうか?
「実は半分以上が即興で、その場で出てきた演奏を録音でメモして、そのまま曲にしているんです。“Ditty”も譜面に書いたわけではなくて、帰り道に頭の中で考えていたものを家に着いてからすぐにピアノで歌い、その場で丸ごと録音しました。
それと1曲目の“Artegio”は、とある森の中の美術館にピアノが置いてあって、他に誰もいなかったので遊びで触っていたことがあったんですね。そのときにiPhoneで録音していて、それを後から切り貼りするように繋げて曲にしているんです。
ただ、9曲目の“Tide”はクラシカルな構成になっていて、フーガという対位法の技法を使っています。同じフレーズを繰り返して重ねることで壮大になっていくんですけど、それは即興では作れない種類の響きなんです」
――“Tide”は8曲目“Sea”から続いて海にまつわるフィールド・レコーディングが使用されていますよね。
「そうです。曲ごとにぼんやりと思い浮かべている景色があって、森とか、街の中とか、電車の車窓から見える風景とか。“Sea”と“Tide”は曲名にあるように海辺のイメージがありました。アルバム全体を映画のような作りにしたかったんです。景色のなかから聴こえてくる響きを立体感を持って出していくというか」
――先ほどの〈フレーズを繰り返す〉という点では、ミニマル・ミュージックにも近いところがあります。高原さんは現代音楽の作曲家だと誰が好きですか?
「人間的にも惹かれているのはジョン・ケージです。いろんな作風がありますけど、非常に斬新なことをやる一方で、“Dream”とか“In A Landscape”とか、ああいうフランス印象主義のような叙情的なピアノ作品も作っている。すごくシンプルだけどしっかりと美しくて、聴き手の内側に何かを喚起させるところがある。それに肩書きが音楽家でありキノコ研究家であるというのもおもしろいですよね(笑)」
――現役のミュージシャンで共感を覚える人物はいますか?
「姉妹で活動しているココロージーが好きで、ライブ映像もよく観ていて。あと現役ではないですが、エリオット・スミスは宅録の先輩だと思っています。ほかにはフィッシュマンズのループを使った曲なんかもよく聴いていますね。どうしても、有限な生命のきらめき、みたいなものを感じられる音楽に惹かれます」
――“Tide”は、ポーランドが拠点のエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー、アース・トラックスさんによるリミックス・ヴァージョンが公開されていますが、彼についてはどうでしょうか?
「もちろん好きですよ。やっぱりリミックスするのであれば自分にはない要素が欲しくて、生音には生音のよさがありますけど、アース・トラックスさんをはじめ電子音楽には〈無機質だからこそ心地よい〉という部分があると思うんです。それは私にはない部分ですし、無機質であっても音楽のエネルギーを埋めてしまうような、そういうミュージシャンはすごくいいなと思っています。
このアルバムではアース・トラックスさん以外にも、イスラエルのゾーイ・ポランスキーさんやイギリスのディラン・ヘナーさんら世界各国のアーティストさんにリミックスをお願いしていて、あとからリミックス集をリリースする予定です。もともとは部屋で一人で作っていた曲が、海を越えて誰かの手にかかるというのは、とても興奮しますね。
あとは現役のミュージシャンで言うと、アルヴォ・ペルトが好きなんです。実は留学中にペルトの室内楽のプロジェクトに参加したことがあって、ご本人ともお会いしたんですけど、彼の今やっていることはクラシックの延長線上にありつつ、間違いなく現代の響きでもあると思うんです。
私自身、そうした現代音楽の流れの先にはありたいなと思います。けれど、文脈を知っている玄人だけのための音楽ではなくて、そうではないような人にも自然に手にとってもらえるようなものでもありたいなと思っていて。斬新なだけではなくて、自然と心地よさを喚起するような音楽を作っていきたいですね」