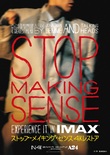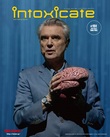さかさまのユートピアに響くデイヴィッド・バーンの爽快で力強い抵抗の音楽「アメリカン・ユートピア」
理想郷としてのユートピアは、理想であるがゆえに、逆説的にそれが到達不可能なものであることを示している。1516年、英国の思想家トマス・モアは、〈どこにもない場所〉という意味を持った架空の国を物語に描き、その理想の国家とされる〈ユートピア〉を通じて、モアの時代の社会を批評した。ユートピアは、理想の社会像を描いたものではあるが、現実の社会が投影されたものであり、それは目指されるべき、より良い社会の希求でもある。しかし、その追い求めるべき理想の国家は、いまはまだ〈どこにもない場所〉だ。ユートピアとは、そうしたいまだ実現しない理想や夢のための場所として描かれてきたし、また、つねに新たな理想を更新し続ける、ゆえにたどり着けない場所でもあるのだろう。
ヨーロッパにとって新大陸としてのアメリカは、そうした理想の社会への夢と憧憬が投影されたユートピアであった。しかし、ユートピアという虚構世界は、たんに夢のような理想郷なのではなく、現実世界を反映した、その延長にある誇張された社会を描くことで、現実の社会に反省的な眼差しを向けるものとなっていく。ユートピアは、理想郷を夢見ることで現実から逃避するのでも、あるいは、回避できない将来に起こり得る変化をただ受け入れるだけのものでもない。それは〈どこにもない場所〉が〈いま、ここ〉で起きている、起こるであろうことを直視するための場所となり、自分たちの世界を、変えることのできる世界であることを認識するための回路となる。

映画「アメリカン・ユートピア」は、2018年に発表されたデイヴィッド・バーンの同名のアルバムをもとに、2019年にブロードウェイのショーとして再構成されたハドソン・シアターでの公演をスパイク・リーが監督し、映画化したものである。しかし、この映画は、たんなるコンサートのドキュメントという性質のものではまったくない。そもそもこの公演自体がたんなるコンサートではないのだから、それがなにかこれまでになかった舞台芸術の領域を開示することになったとしても、なんの不思議もないだろう。コンサートの映画化ということでは、よく知られるように、バーンがリーダーをつとめたトーキング・ヘッズにおいて、84年に「ストップ・メイキング・センス」が、ジョナサン・デミの監督によって制作され、コンサート映画というジャンルに新しいスタイルを作り出した。それは、映画のために周到にデザインされたセットや演出を駆使した(バーンのトレードマークともなった、あの異様に大きなスーツ)、それまでの一般的なコンサートの演出とは異なる、洗練された舞台作品といえるものでもあった。また、バーンがブライアン・イーノと27年ぶりに共作をリリースした直後の2009年のコンサート(イーノはいなかったが)でも、その考え抜かれた舞台は、同様にポピュラー音楽のコンサートの類型にしたがわない、いままでに類を見ない独創的なものだった。
バーンは、「ストップ・メイキング・センス」以降、コンサートを録音作品の副次的な演奏行為という以上の、総合的なパフォーミング・アートとしてとらえ、自身の表現手段の完成形のひとつとみなしてきた。「アメリカン・ユートピア」は、その(あくまでも現在における)到達点にちがいない。なによりも白眉は、舞台上に固定された楽器やアンプなど、機材の類がまったくないということだ。それは、ロックであれ何であれ、コンサートのセッティングとして、半ば前提とされていたものであっただろう。チェーンのカーテンで囲まれた舞台には、それがいっさいない、からっぽの空間なのである。また、コンサートにありがちな映像や派手な演出もまったくない。ステージ自体はグレーを基調にしたもので、床も、統一されたパフォーマーのスーツもグレーである。そのニュートラルなモノトーンに照明がアクセントを与えている。音楽と同期する照明と振り付けは、視覚化された音楽を見るかのようであり、綿密に計算されたようなフォーメーションは、整然としたディシプリンを感じさせるようなものではなく、もっと自由なものだ。その舞台演出を、さらに複数のカメラの視点によって切り出し、明確にし、再構成する映画の演出。そこでは、音楽、舞台、映画、それぞれの創造性があますところなく発揮され、融合している。
パーカッションとキーボード奏者は、オリジナルの装具によって楽器を自身の体に固定して演奏する(あんなふうにキーボードが演奏できるということを初めて知った!)。広々とした舞台を、バーンを含む総勢12人の、性別、人種、国籍もさまざまな、パフォーマーが、楽器の呪縛から解放され、自由を謳歌するかのように、生き生きと動き回り、歌うのである。楽器からはケーブルすら伸びていない、モニターはイヤフォン、マイクもワイヤレス、パフォーマーは何にも縛られず、裸足で舞台を駆け巡る。必然、ドラムセットのような大掛かりなものはなく、パーカッションが複数人で演奏する。そうした編成によって音楽それ自体もまた独特のものに変わっていくだろう。不思議なことだが、この映画を観ていると、間接的に映像でコンサートを観ている、という感覚をつい忘れてしまう。このパフォーマンスの前に多くの観客がいるということも、つい忘れてコンサートに没入している。やがて、カメラが舞台後方からのショットに切り替わると、そこには客席を埋め尽くす観客がいる。