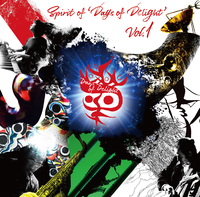日本のジャズが覚醒した70年代をリスペクトすると共に、新しいジャズの在り方を追求するレーベル。それが〈Days of Delight〉だ。2018年の設立以来、計20点の作品をリリースし、来たる2021年9月22日(水)には3周年記念のコンピレーション・アルバム『Spirit of ‘Days of Delight’ vol.1』も登場する。「このレーベルを新しい日本のジャズのプラットフォームにしたい」と意気込む平野暁臣ファウンダー/プロデューサーへのインタビューは、猛烈なガッツとパッションに溢れたものとなった。
70年代の〈歓喜の日々〉をもう一度
――3周年おめでとうございます。計20作品、大変なラインナップです。コロナ禍をものともせず、2020年には8作品もリリースされました。
「あっという間でした。なにしろ物事を決めたり動かしたりしているのは僕ひとりなので、休む間もなく走り続けていましたから。手掛けるアーティストも、土岐英史さんや峰厚介さんのように僕がジャズに出会った70年代から活躍している世代もいれば、現在30歳前後の世代もいる。ミュージシャンと音楽のバリエーションがどんどん広がっているので、たえず新鮮な発見があるんです。しかも日本ジャズの最高水準の演奏が次々にアーカイヴされ、それが作品として目に見える形で積み上がっていくわけですからね。それを目の当たりにするのはとても幸せなことだし、エキサイティングです。もっともっとやりたいですね」

――Days of Delight設立の動機について、改めて教えていただけますか?
「まもなく還暦を迎えるという時に、〈もう1度、未知の世界で自分を試してみたい〉と思ったんです。僕の本業はイベントやディスプレイなどのメディア空間のプロデュースで、主に日本文化を世界に伝えたり、地域振興のお手伝いをしてきました。仕事は面白いし、誇りも持っています。だけど、30年も40年もやっていると、さすがに新鮮な感動はなくなります。20代で初めて現場にぶち込まれた時の不安や恐怖を感じることはもうないし、逆に作品が出来上がった時の喜びや達成感も当時とは違います。場数を踏んで経験値が上がった分、うまく作れるようにはなったけれど、それと引き換えに感動や刺激が失われていく。まあ、仕方がないことですよね。で、還暦を迎える時に、未知の世界に今放り込まれたら何ができるか、どこまでできるのか、自分自身を試してみたくなったんです。
ただし未知の世界といっても〈蕎麦打ち〉ではなく、仕事でなければならないと考えました。本当の意味での歓喜や達成感は、社会と関わりリスクを背負う〈仕事〉にしかないからです。そう考えるうちにテーマは音楽だと思った。小学校6年で洋楽と出会って以来、音楽が僕の人生を支え、彩ってくれたからです。最大の恩人である音楽にわずかでも恩返しをしたいと」
――小学校6年での洋楽との出会いから、音楽とはどんな風に付き合ってきたんですか?
「レコードは高くてあまり買えないから、レコード店を回って聞き耳を立てたり、FMをエア・チェックしてテープ作りに励んだり。なかでも一番ワクワクしたのがライブでした。もっとも、当時熱中した海外のロックを生で観る機会は年に1回あるかないか。今と違って海外アーティストの公演は極めてレアな〈非日常〉でしたからね。なので、僕はロックにどハマりしたけど、その付き合い方は〈音源を聴く〉だけだった。
ところが、日本のジャズだけは日常的に生で観ることができた。ピットイン、タロー、ミンゴス・ムジコ、ロブロイ……たくさんあったジャズ・クラブに行けば、ジャズマンたちの肉体からほとばしり出る生身の音を浴びることができたんです。チープなステレオで〈音源〉を聴くのとは次元の違う体験ですよ。それこそ土岐さんや峰さんを朝顔管(サックスのベルの部分)から数十センチの距離で聴くことができたわけですからね。喩えて言うなら、F1サーキットで聞くエンジン音と同じです。あの音圧と音の質感は言葉で説明しても絶対にわからない。現場で体験する以外にないんです」

――現場での体験が、プロデュースに反映されているわけですね。
「僕が初めてジャズと触れ合った70年代の日本のシーンは、現在とは熱量が全く違っていました。スリー・ブラインド・マイスやイースト・ウィンドのような日本ジャズ専門のレーベルが次々に立ち上がり、若いプレイヤーがどんどん出てきて、新譜がバンバン売れていた。
時を同じくして、日本のジャズがそれまでの〈コピーの時代〉から〈オリジナリティーの時代〉へと大きく変質しました。たとえば渡辺貞夫さんのアフリカン・フレイヴァーのサウンド(72年作『Sadao Watanabe』など)は世界を見渡しても例のないものだったし、日野皓正さんのアンサンブル(75年作『スピーク・トゥ・ロンリンネス』など)もそう。ジャズ喫茶やジャズ・クラブがいっぱいあって、そこにファンがつめかけて客席は満席だったし、プレイヤーたちも自分のオリジナル曲を遠慮なく堂々と演奏し、客もそれを支持した。プレイヤーも、リスナーも、業界も、とにかくものすごい熱があったわけです。
ところが今の状況は、残念ながらあの時代の活況とは比べるべくもない。そういうなかにあって僕にできることは何か。今からサックスを習っても手遅れでしょ(笑)。できるとしたら、今もジャズという音楽を真摯に守り伝えようとしているミュージシャンたちを社会に送り出すお手伝い、もうそれしかないと思ったんです。レーベルを〈Days of Delight〉と名付けたのも、あの時代のジャズ・シーンが持っていた情熱と気概、その結果として獲得した〈歓喜の日々〉を取り戻したいとの思いからです。もっともその時点でジャズ界の知り合いはゼロでした」