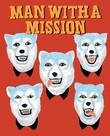タワーレコードのフリーマガジン「bounce」から、〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに、音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴っていただきます。今回のライターは青野賢一さんです。 *Mikiki編集部
★連載〈LIFE MUSIC.~音は世につれ~〉の記事一覧はこちら
今宵のお月さまも一筋縄ではいかない
道を歩いていると、思いがけないところから月の姿が見えて驚かされることが少なくない。わたしは方向感覚に乏しく、家以外の場所だと基本的に東西南北がよくわからないのでこうしたことが起こるのだが、この「あれ、こんなところから月が」というのはなかなかに楽しいものである。そして、さっきまで見えていたかと思えば、いつのまにか位置を変えて――我々が思っている以上に月の動きは速いのだ――何かの影に隠れてしまったりすることにも感心してしまう。そんなところから、私にとっての月のイメージは神出鬼没であり、するりとこの手から逃げてしまう捉えようのない存在というものである。
月をバンド名に含むムーンライダーズにもどこかそうしたムードを感じるのは、わたしの思い込みだけではないだろう。メンバーがそのときどきで影響を受けている事物が有機的に結びつき、ムーンライダーズの音楽として表現されるとき、ジャンルやカテゴリーはそれらに追いついてはゆかない。ようは一筋縄ではいかないのである。ムーンライダーズに対してわたしがそう思うようになったのは、アルバム『マニア・マニエラ』と『青空百景』のリリースについて話題になっていたとき。1982年のことである。『マニア・マニエラ』の内容があまりにも時代の先を行きすぎているとレコード会社が難色を示したのを受けて、急遽『青空百景』を制作し9月にレコード・リリース、『マニア・マニエラ』は当時まったく普及していなかったCDフォーマットで12月に発売されたというのは有名な話だ。当時、『マニア・マニエラ』収録曲はFMでオンエアされる機会があって、それを耳にしてそのかっこよさにぶっ飛んだと同時に『青空百景』の質感との振れ幅に驚いたのだった。
『マニア・マニエラ』はその後、1984年にカセット・ブックとして冬樹社より発売され、わたしは迷うことなくそれを書店で買い求めた。荒俣宏が寄稿していたり稲垣足穂が引用されていたりして、本としての内容もすこぶるよかったが、何よりこれで『マニア・マニエラ』をいつでも聴くことができる嬉しさがあったのを覚えている。これ以降のムーンライダーズの作品においても、過去作と違うアプローチ、それによる新しいアウトプットを積み重ねてきたのはご存じのとおり。季節や時刻によって表情が変わる月さながら――ときには皆既月蝕のように姿が見えないことも何度かあった――、聴く者に新たな感情をもたらしてきた。2022年4月にリリースされた11年ぶりのアルバム『It’s the moooonriders』ではモノローグを多用し、パンデミック以降の社会の不均衡、違和感、後戻りできない時間とそれにともなう老いや死といったモチーフをポスト・クラシカルからインプロヴィゼーションまでを含むサウンド・アプローチで表現し、バンドとしての今を見事に更新している。この変幻自在ぶり、月を名前に冠したバンドの本領発揮といわずして何といおう――。
ところで、稲垣足穂は「一千一秒物語」で喧嘩する月や石に当たって欠けてしまった月など、さまざまな月を描き出しているが、これらを読むにつけ、ムーンライダーズだったらどんな月を作り出すだろうかと考えてしまう。すなわち、素材は港湾に関連するものだろうか、最終的には手作業で組み立てていそうだな、などと他愛もない想像を巡らすわけだが、おそらくしばらくはスーパームーンよろしく大きく輝いているだろうことは間違いなさそうだ。
PROFILE: 青野賢一
1968年東京生まれ。ビームスにてPR、クリエイティブディレクター、音楽部門〈ビームス レコーズ〉のディレクターなどを務め、2021年10月に退社、独立。現在は、ファッション、音楽、映画、文学、美術などを横断的に論じる文筆家としてさまざまな媒体に寄稿している。2022年7月には書籍「音楽とファッション 6つの現代的視点」(リットーミュージック)を上梓した。
〈LIFE MUSIC.~音は世につれ~〉は「bounce」にて連載中。次回は2022年10月25日(火)から全国のタワーレコードで配布開始される「bounce vol.467」に掲載。