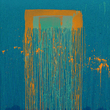演奏は基本的にマニュエル・ウィルキンス (サックス)、ビル・フリゼール(ギター)、グレゴリー・リース (ペダル・スティール)、ケヴィン・ヘイズ (ピアノ)、ラリー・ゴールディングス (ハモンド・オルガン)、スコット・コリー (ベース)、ネイト・スミス (ドラム)が行なっている。透明感のある美しい演奏ぞろいだ。ミュージシャン選びではどんなところに気を配ったのだろう。
「ジャズの素養のあるミュージシャンたちだ。ジャズではふだん一定の範囲内で演奏する必要があるけど、このアルバムでは、言葉が最も重要なので、それがわかっている特別なミュージシャンを選んだ。スタジオではまず歌詞をプリントしてミュージシャンに渡して、レナードのヴァージョンを聴いて、レナードの歌に対するぼくの解釈を話した。誰もが詩を異なる方法で聴いていると思うけど、レナードは詩に託した意味をきちんと説明することはなく、作品がそれぞれちがったふうに解釈されることを望んでいたから、それでいいんだ。歌や言葉に耳を傾けてから、音楽的な方向性を少し話して、スタジオに入った。演奏の腕前を証明するんじゃなく、詩を強調してアンダーラインを引くように演奏してほしいと。やりすぎないように気を配った。そしたらすぐに何かしら魔法が起こったんだ」
編曲は基本的にヘッド・アレンジだったのだろうか。レナードの作品はリズム面ではとても簡潔なので、工夫が必要だったという気がするのだが。
「そうだ。きっちりアレンジされたものじゃなくて、印象主義的なものが欲しかった。言葉の周りに演奏が自然に生まれてくるようなオーガニックな音楽をね。レナードは自分の歌の音楽的な限界について、他のミュージシャンはいろいろ切り札を持っているけど、ぼくはひとつしか持ってないって、よく冗談を言ってた (笑)。もちろんそれが彼にふさわしく、素晴らしいものだったんだけど。だから、このアルバムでは、演奏を複雑にしようとか、より濃くしようとは考えなかった。さっきも言ったけど、言葉が前に出てきて、人々に強く訴えるものにしたかった。レナードはよくぼやいていたんだ。レコードの中でも演奏がしばしば歌に割り込んできて、詩の自然性を損なうんだと。出来上がったヴァージョンは、原曲の言葉を新しいやり方で聞く感じかな。文脈を変えることで歌に新しい生命を吹き込みたかったんだ」
ラリーはハービー・ハンコックが中心になってジョニ・ミッチェルの作品に取り組んだ『リヴァー~ジョニ・ミッチェルへのオマージュ』をプロデュースして、グラミーの最優秀アルバム賞を受賞したことがあるが、今回のアルバムとそのときとのちがいはあったのだろうか。
「基本的なアイデアやコンセプトは同じ。どちらも原曲がファンタスティック。でも細目がちがうんだ」
レナードの音楽がいまの時代に持っている意味についてはこんな意見だった。
「彼の音楽はタイムレスなんだ。いつもていねいに曲を作っていた。ときには1曲に何年も時間をかけて。音楽的にはカントリー、たとえばハンク・ウィリアムスの影響を強く受けていた。同時にゴスペルの影響も受けていた。祈りの音楽というか、讃美歌のようなところがあった。でもストレートではなく、ゴスペルの要素の周りで戯れて、裏返して、皮肉なユーモアも感じさせるんだ。見逃されがちだけど、レナードの暗めのユーモアのセンスは抜群だった。官能性と精神性の葛藤についての歌も多い。そんなところも味わってもらえたらうれしいね」
Larry Klein(ラリー・クライン)
グラミー賞10度ノミネートされ、ハービー・ハンコックのジョニ・カヴァー集など4度受賞。ジョニ・ミッチェルの『Turbulent Indigo』(邦題:『風のインディゴ』)やトレイシー・チャップマンの『Our Bright Future』(邦題:『アワー・ブライト・フューチャー』)などのアルバムをプロデュースし、フレディ・ハバードやウェイン・ショーター、ドン・ヘンリーなどの偉大なアーティストと一緒にベースを演奏し、ウォーレン・ゼボンやボニー・レイットなどと共作などの経歴を持つ名プロデューサー。