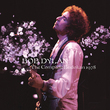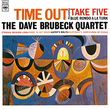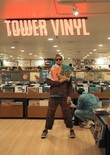第三章 戦後芸能の光と影──クレージーキャッツと美空ひばり

クレイジーキャッツマニアであった大瀧詠一が編集とライナーノーツの執筆を手がけた決定的ベスト盤。日本の戦後ジャズシーンが生んだ国民的コミックバンドの代表曲をひと通り聴くことができる。2枚目には、1986年に行われたクレイジー最後のレコーディングの様子を収録する。「ヒップネスと強靭な大衆性。本来相反するその二つのスタイルを一身で表現してみせたのがクレージーだった」(本書第三章より)。

美空ひばり 『LOVE! MISORA HIBARI JAZZ & STANDARD COMPLETE COLLECTION 1955-1966』 コロムビア(2005)
美空ひばりは、しばしばジャズの歌詞を日本語にして歌った。それが日本の大衆に曲の魅力を伝える最良の方法だと考えたからである。10代から20代後半にかけて彼女が録音したジャズスタンダード集であるこのアルバムで、その〈ひばりのジャズ〉を体感することができる。「ジャズであろうがポップスであろうが民謡であろうが、要するに歌は歌であって、自分の心の奥底を通過し、自分の肉声に乗れば、彼女にとってそれは自分の歌であった」(本書第三章より)。
第四章 ならず者たちの庇護のもとで──ギャングが育てた音楽
アメリカの歴史上最も有名なギャング、アル・カポネが支配した1920年代のシカゴにおいて、ジャズは大衆音楽への第一歩を踏み出した。禁酒法下のシカゴのもぐり酒場で演奏されていたのは、例えばこんな音楽だった。サッチモ(ルイ・アームストロング)が率いたレコーディングバンド〈ホット5〉と〈ホット7〉。ステージでのサッチモの演奏は、これ以上の熱気に溢れていたことだろう。4枚組のコンプリートバージョンもある。
シカゴを支配していたのはギャングだったが、もう一方のジャズの本場カンザスシティを牛耳っていたのは、悪徳政治家トム・ペンダーガストだった。そこで育ったカンザスシティジャズは、演奏者の即興を重視することでのちのビバップへの道筋をつくったのだった。〈史上最もスウィングするバンド〉カウント・ベイシー楽団や、若きチャーリー・パーカーが在籍したジェイ・マクシャン楽団などの全20曲を収める。