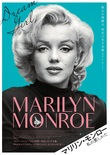ロイは絶対に計画通り動いてくれない人
――アンリ監督は1990年にロイと出会って、長い年月をかけて築いてきた関係性がありますよね。だからこそ映画には、ロイがリラックスしていろいろ話す姿も収められています。その意味では非常に個人的な関係性が刻まれた作品ですが、同時に、ドキュメンタリー映画としての客観的な距離も感じさせる作りになっています。そうした個人的な関係と客観的な距離のバランスはどのように考えて撮影されていましたか?
「この映画が存在しているのは、そもそも、やっぱり私とロイの長い友情があったからこそだと自分でも思います。そのぐらいロイはものすごくプライベートな人だったんですね。あそこまで彼が自分自身を語るようなシーンを撮ることは、普通はあり得なかった。それは私とロイの間に、28年間の交流から生まれた友情と信頼の関係があったからだと思います。
ただ、自分はあくまでもドキュメンタリー制作者として、なるべく客観的に真実を語りたいとも思っていました。映画からどういう結論を導き出すかは観客のみなさんに任せたいという気持ちで作っていたので、その一線は越えないようにしていました。
とはいえ本音を言うと、すごく直感的にやっていたというのが実際のところですね。私は今回、ドキュメンタリー映画としてはこれが初めての監督作品だったので、オン・ザ・ジョブ・トレーニングといいますか、その場で実践し学びながら作っていったんです。ロイのインタビューに関しても、あらかじめ質問事項を考えて訊くことはまったくなくて、その時その場の対話の中から生まれてきた、自分が純粋に知りたいと感じたことを訊いていました。そういうことができたから、ものすごく生々しくリアルで、スポンティニアスな映画になったんじゃないかと思っています。
こちらが計画を立てても、ロイはその通りには絶対に動いてくれない人だったんですよ(笑)。たとえば撮影クルーと6時間ひたすら待ち続けて、ようやく45分の映像が撮れた、みたいなこともありました。ロイはどこに行くかもわからないんです。映画に出てくるショッピングのシーンも、実は彼が突然お店に行き始めちゃったんですね。ちょうど撮影クルーはご飯を食べていたので、〈ロイが出かけるから早く来て!〉ってメールして。その直後に撮れたのが、ロイが街の中で歌いながら歩いているシーン。そんなことがしょっちゅうありました。だからあらかじめ準備して計画通りに撮影するということは、彼に関してはなかなかできませんでした」

俺はレイシストじゃない! マネージャー、ラリーとの軋轢
――今回、アンリ監督自身も映画にたびたび登場しますよね。中でも印象的だったのが、ロイとアンリ監督、それにマネージャーのラリー・“ラグマン”・クロジアーさんの3人で喧嘩のようになるシーンでした。ラリーさんが激昂して出ていったあと、ロイとアンリ監督は「すべて撮れた!」みたいに仰っていましたが、あのシーンはラリーさんの普段の姿をカメラに収めるためにわざと怒らせていたのでしょうか?
「あれはフランスのセットという街で、本当は外でロケをする予定だったんです。それで撮影クルーと一緒にホテルのロビーにいたら、ラリーがものすごい形相でやってきて。〈3人で話をするから来い!〉〈カメラマンも連れて来い!〉って。〈え、カメラもいいの?〉と思いつつ(笑)、言われるがままに部屋に行きました。それで、カメラマンはカメラをセットして部屋を出たので、3人だけになったんですけど、ラリーは最初からあの調子でガンガン怒鳴っていて。
途中からはカメラがあることすら忘れて喋っていましたね。1時間15分ぐらい続いたんですが、映画で使ったのはそのうち7分ぐらい。なので、最初からラリーは怒っていて、なぜかそれを撮らせてくれたんです。だから自分たちで仕組んだわけではなくて、ラリーが自爆したというか(笑)。あのシーンでは私も本当は言いたいことがいっぱいあったけど、ロイから〈俺が話すから君は話さないでくれ〉と言われていたので、グッと堪えてました」
――そうだったんですね。ちなみに、あのシーンでラリーさんは「自分は人種差別主義者ではない」といったことも仰っていましたが、それは映像に映っていない場面で、そうした発言をしてしまっていたということですか?
「いや、あれは突然ラリーが言ったんですよ。それまでその話をしていたわけではありませんでした。ただ、ツアーに行く前の1月に、ロサンゼルスで2日間撮影していたんですけど、そのときにラリーが私に対して少し人種差別的な発言をしたことはありました。
とはいえ、あの3人のシーンでラリーが突然〈俺はレイシストじゃない〉と言ったのがなぜだったのかは、よくわからないですね。なので編集段階でその映像を使うかどうか悩んだんですが、やっぱり私自身、実感としてそういう待遇を受けたと感じたことがあったのも事実だったので、あえて入れることにしました」