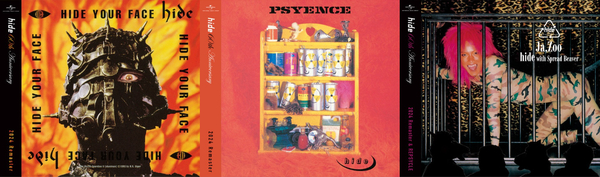クラシックは音楽のほんの一部。もっと血湧き肉躍る音楽を
――バイオリン奏者の場合、クラシックだけで活動することが多いですよね。お2人は言わば対極にあるロックにも積極的に入り込んで活動されてきました。ある種、特異な活動の仕方だと思うんです。
Jill「2人とも幼い頃からクラシック教育を厳しく受けてきまして、私は大学に行くまでクラシックしか聴いちゃいけないという家庭だったんです。J-POPですら、〈何でそんなのを聴いてるの!〉って叱られる状況で。
ただ、大学に入って親元を離れますと、監視の目も緩くなるわけです。そこでハジけて、メタルからEDMまでいろんな音楽を聴きまくったり、ライブハウスに出入りしたり、クラブに行って朝まで踊り明かしたりするようになって(笑)。世の中にはこんなに面白い音楽がいっぱいあるんだ、私が知ってたクラシックって、ほんの一部じゃんって気づくんですね。
その後、大学を卒業するに当たって進路を決めるとき……それまでは親と先生が敷いたレールの上を歩いてきたんですけど、これからは自分で切り開いて生きていかなきゃと。そうなったとき、もっと血湧き肉躍る音楽をやりてぇと思ったんです(笑)。もちろんクラシックにもそういった音楽はあるんですけど、クラシックファンだけでなく一般の方々にもっと直接的に届けられるようなものですね。
クラシックの人がロックをやると、〈クラシックでやっていけないからでしょ?〉って、よく言われるんです。でも、そう言われたくなかったので、コンクールを受けたり、クラシックでも頑張って結果を出すようにして。でも、本当にやりたいのはロックなんだぞって。クラシックもロックも、まだ勉強中ではありますけど、説得力をもってみなさまにお届けできるように、今も頑張っております」
観客が温かい味方になるロックの自由な現場
星野「私は……Jillさんだけのお話にしておいたほうがいいかもしれない(笑)」
――沙織さん、またあえて変わったことを言おうとしていますか(笑)?
星野「いやいや(笑)。私は逆に〈負けた〉人なんですよ。
大学時代はクラシックの世界で仕事をしていくのだろうと思ってはいたものの、ソロでやっていくには圧倒的に能力が足りないし、加えてすごくメンタルが弱いんです。他人と比べられる状況に置かれたとき、恐ろしいぐらいへこんでしまうんですね。だからコンクールで結果が出せなかったんです。そうすると先生が〈どうしたの、いつも弾けてたじゃん〉と落胆するので、さらにへこんで。交響曲を弾くのが好きだったんですけど、オーケストラに入るためには団員試験は受けなくちゃいけない。試験のたびにブルブルしながら受けて、やっぱり結果が出なくて。
そういう経験を繰り返したので、ああ、私は奏者になるのは無理なんだ、講師とか指導者とかになれる可能性はあるかもって思っていました」
――沙織さんの技術力は評価されていたにもかかわらず(星野は国立音楽大学を首席卒業)、そんなことがあったんですね……。
星野「ただ指導者というポストに辿り着くにも、弾いていないと技術は落ちていきますし、でもやっぱり表現をしたい……私にとってバイオリンを弾くことが自分の言葉なので、発信したい気持ちはあって、それで小さいサロンとかで演奏会を組み始めたりしたんです。
当時、お世話になったのが、六本木のソフトウインドというライブハウスでした。ある日、マスターが、〈Sword of the Far EastからAyasaさんが抜けることになって、代打のバイオリニストを入れたいと探してるみたいだけど、提案してみようか〉と言ってくださって。
それまではロックで弾く気はなかったんですけど、何となくお願いしてみたら、〈Sword of the Far Eastではなく、(箏奏者の)吉永真奈さんなどが所属なさってる琴線幻夜というプロジェクトはいかがですか〉とお話をいただいて、参加することになったんです。
そしたらゴツゴツした刺々しい10センチ超えのピンヒールが支給されて(笑)、これで歩きながらパフォーマンスしてエレキを弾いてほしいという話だったんです。要求された全てが、それまでやったことがなかったので、家にダンボールを敷いて、ピンヒールを履いてヨロヨロしながら支給されたエレキを練習しました。私は5弦バイオリンがあることも当時は知らなくて」
――そんな経緯があったんですね。
星野「ただ、初めての本番が楽しかったんですね。知らなかった世界がそこにあって。お客さんのテンションもクラシックと違って、舞台に上がったときに怖く感じた客席が温かいものに感じられて……。同じ楽器を持っているにもかかわらず、場所が変わるだけで、客席が味方になってくれて自分の力になる。その体験が嬉しかったんですね。
元々、弾いているときに体が動いてしまうタイプで、クラシックの先生から注意されていたんですね。それも当時はコンプレックスだったんです」
――オーケストラの場合、ソロは別ですが、演奏中に目立つことはよろしくないわけですよね。
星野「エキストラでオーケストラに行くときも、目立たない格好、音が鳴らない靴を履いて、静かに静かにって感じでした。
でも、自分が自由にしても誰も怒らない場所があることが、音楽を続けるモチベーションになって。そこでこういう音楽をもっとやってみたいと思うようになり、今、ここにいる感じです(笑)」