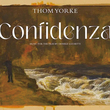今年9月、イギリスで映画「Let Me Go」が公開された。ポリー・スティールが監督を務めたこの映画は、ヘルガ・シュナイダーの体験に基づいたノンフィクション「黙って行かせて」が原作。筆者も以前読んだことがあるが、ナチスの親衛隊員だった母親を娘(ヘルガ)が問い詰めていくという内容は、けっこうハードだったといまも覚えている。
映画については、「シング・ストリート 未来へのうた」(2016年)のラフィーナ役で知られるルーシー・ボイントンが出演していることもあり、公開前から注目を集めていた。カメラマンであるマイケル・ウッドの撮影技術を褒めるレヴューが掲載されるなど、好意的な評価も見られる。日本でも公開してほしいと願うばかりだ。
そして、この映画の大きなトピックの一つが、レディオヘッドのドラマーであるフィリップ・セルウェイがスコアを担当したことだ。過去にはイギリスの有名バレエ団、ランバート・ダンス・カンパニーに音楽を提供しているが、映画は今回が初めて。
フィリップが「Let Me Go」に関わったきっかけは、2015年に映画の台本が送られてきたことだったという。このときの様子については、〈台本を読んで、次にヘルガの体験記を読んだら、完全に引き込まれていた〉と語っており、かなり深く映画にコミットしたうえでスコアを制作したことが窺える。さらに、〈音楽を通して、ヘルガの複雑な感情やストーリーを理解するという自由をあたえてくれた〉とも述べるなど、存分に創造性を発揮できる制作環境だったこともわかる。
こうして作られたのが『Let Me Go OST』で、本作はこれまでフィリップが発表してきたソロ・アルバム『Familial』(2010年)や『Weatherhouse』(2014年)と同じく、ベラ・ユニオンからリリースされた。『Let Me Go OST』を一聴してまず耳を引いたのは、映画のスコアという性質も関係しているが、過去作と比べて歌モノが圧倒的に少ないことだ。歌声が聴こえるのは、フィリップみずから歌う“Wide Open”と“Let Me Go”に加え、映画にも出演しているラムのルー・ローズが参加した“Walk”の3曲だけ。
だが、この3曲が本当に素晴らしい。特に“Wide Open”は、歌とアコースティック・ギターのみというシンプルな楽器編成で、繊細でたおやかなフィリップのヴォーカルを堪能できる。言葉にすることが難しい、複雑な感情が渦巻く映画のムードに寄せるためか、牧歌的な空気が漂うサウンドをバックに、寂しさや絶望感を滲ませた言葉が歌われるのもおもしろい。そういった点で、『Pink Moon』(72年)などの名盤を残して夭逝したシンガー・ソングライター、ニック・ドレイクの音楽を重ねてしまう楽曲だ。
“Let Me Go”は、物悲しいピアノの響きからはじまり、そこに歌、ストリングス、電子音が徐々に絡んでいく展開には、心地よいスリルが醸されている。“Wide Open”と比べて音数は多いが、無駄な音は一切ない。すべての音が適切な場所で鳴っており、長い音楽活動の中で積みあげてきたプロダクション技術が遺憾なく発揮されている。
とはいえ、長年イギリスのポップ・ミュージックを追っている者からするとれば、ラムのルー・ローズが荘厳な歌声を聴かせてくれる“Walk”こそ要注目の楽曲かもしれない。
マンチェスター出身のバンドであるラムは、ヒップ・オプティミスト名義でビッグ・ビートを作っていたアンディー・バーロウが、カメラマンだったルー・ローズを誘って結成された。96年に発表したファースト・アルバム『Lamb』は、当時のイギリスで盛り上がっていたトリップ・ホップやドラムンベースに根ざしたサウンドで注目を集めた。アルバム・デビューはレディオヘッドのほうが早いものの、90年代からイギリスで活動していることはフィリップとルーの共通項と言えるし、そうした2人が交わるのはなかなか感慨深い。だから“Walk”にはドラムンベースの要素も……となっていないのは少々寂しいが、淡々と刻まれるドラムと叙情的なストリングスを前面に出す内容は、マーキュリー・プライズにノミネートされたルーのソロ・アルバム『Beloved One』(2006年)を想起させる。
『Let Me Go OST』には、ストリングス、ピアノ、ギター、ベース、ドラム、エレクトロニックス、ミュージカル・ソー、グロッケンシュピール、ビブラフォンなど、数多くの楽器を用いて作られている。そのなかでもとりわけ印象的なのはストリングスだ。ギターや電子音の比重が高かった『Familial』や『Weatherhouse』と大きく異なり、本作では作品全体を覆い尽くすほど弦楽器が活躍しているが、重厚で迫力たっぷりのオーケストラルな使い方ではなく、あまり音を重ねないミニマルな鳴らし方を志向している点がおもしろい。それはまるで、ナチスに加担した母親を問い詰める娘の悲壮な想いと孤独感を代弁するかのようだ。先に紹介した、音楽を通してヘルガの感情を理解するという本作のコンセプトはその点でも見事に徹底されている。
ストリングスのアレンジはロンドンのチェリスト、ローラ・ムーディーによるもの。彼女はエリシアン・カルテット(The Elysian Quartet)の一員として、ミステリー・ジェッツやホット・チップといったバンドから、デレク・ジャーマンの映画にスコアを提供していたサイモン・フィッシャー・ターナーまで、さまざまな音楽家たちと仕事をしてきた。ソロ活動ではビョークやビーティー・ウルフら先進的な表現で知られるアーティストと共演するなど、まさに手練れのアーティストだ。彼女は『Weatherhouse』にも参加しているため、フィリップとの交流はそれなりに深い。このことが良い方向に出たのか、本作のコンセプトをうまく消化したアレンジに仕上がっている。派手なエフェクトや奇を衒うコード進行はなく、あくまでヘルガの揺れ動く情動に寄り添う慈しみを感じさせる。
ここまで書いたことを総合すれば、ストリングスを中心としたミニマルなサウンドが本作の特徴と言えるだろう。そこには、「ムーンライト」(2017年)や「浮き草たち」(2016年)のスコアを手がけたニコラス・ブリテルのアプローチに通じるものも見いだせる。特に前者のスコアは、ブリテル自身が〈ピアノとヴァイオリンの詩〉と表現しているように、ブリテルのピアノとティム・フェインのヴァイオリンを基調にしたミニマルな音像が特徴で、本作の内容と重なる部分がある。
ただ、そのようなアプローチはフィリップのソロ作品群に通底するものだ。レディオヘッドで嫌になるくらい複雑なことをしている反動か、ソロではシンプルなサウンドを鳴らすことが多い。音と音の隙間をあえて強調することで、無音という音を操っているようにも感じる。言うなれば、少ない音で多くを語るのだ。そう考えると、映画のスコアというフィールドは、フィリップ・セルウェイという音楽家にとって最適な場所なのかもしれない。映画が漂わせる緊張感をふまえつつ、それを伸び伸びと音楽に変換している風通しの良さが映える本作に触れると、そう強く実感してしまうのだ。