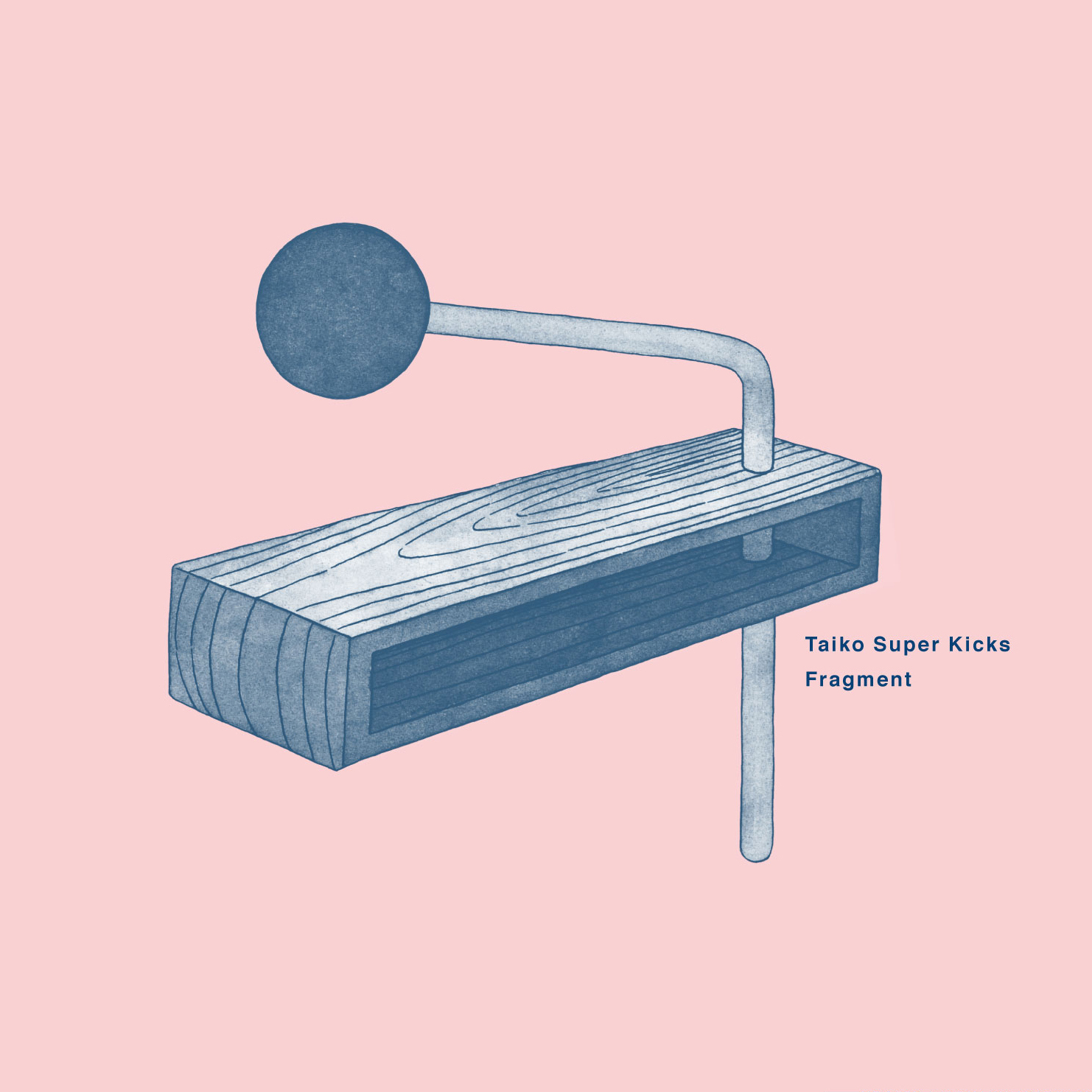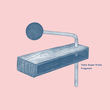長きにわたって協力関係にあるmei eharaと、先達としてリスペクトを捧げ、共感を寄せる仙台のyumboを招いた1月20日の自主企画〈オープニング・ナイト〉でTaiko Super Kicksは、バンドとしてのひとつの区切りを提示するかのような、なにがしかの決意と次のステージへと進む意志が込められた演奏を聴かせてくれた。そのストイックきわまりないプレイとステージングには、凄みを感じさせる瞬間すらあった。〈平熱〉だとか〈淡泊〉だとかいったクリシェな形容を寄せ付けない気迫が、彼/彼女たちの演奏にはあった。
バンドのフロントマンで、ほぼ全曲の作詞曲を担っているヴォーカル/ギターの伊藤暁里は、前作『Many Shapes』から約2年ぶりとなるセカンド・アルバム『Fragment』のリリース前に、次のようなコメントを発表している。〈フラグメント、断片的なこと。今の生きていく態度を表明する言葉〉。そう、だからこそ『Fragment』は、Taiko Super Kicksがみずからのアティテュードを、〈高らかに〉というわけではないが、静かに、だが熱をもって表明している作品なのだろう。
伊藤のコメントを読み、本作のタイトルを知ったとき、社会学者である岸政彦の著書「断片的なものの社会学」(2015年)を思い出した。同書で綴られていたのは〈断片的なもの〉、すなわち〈一般化も全体化もできないような人生の破片〉をめぐる思索だ。たとえば、岸の小説作品「ビニール傘」(2017年)では〈エレベーターの床に捨てられているカップ麺の殻〉や〈海岸に落ちている鍵〉が、特別な意味を持たずに描写される。路上にただ落ちている石塊や木片のような、文脈を剥ぎ取られ、ただそこにあるだけで、何も意味をなさないもの、あるいは出来事――そういったものを愛でるとか、陰謀論のように、それに特別な意味を読み込むというのではない。それは、意味もなくただそこにあるだけなのだ。岸の思想は、どこかで伊藤の歌詞と通底するところがある。
表題曲の“フラグメント”で伊藤は歌う。〈プロレスでも見てみようか/それもありだ/映画でも見よう/何か読もう/何かしよう〉〈やっぱりやめよう/今度にしよう/それもありだ/フラグメントだけど〉。何をするのかはあきらかにされないまま、この曲は、そしてアルバム『Fragment』は幕を閉じる。“フラグメント”で歌われている人物が〈プロレス〉や〈映画〉を観ようが観まいが、それらはつつがなく開催されるし、上映される。なぜなら、彼も〈プロレス〉も〈映画〉も断片にすぎないのだから。
『Fragment』におけるTaiko Super Kicksの演奏、そしてそのサウンドは、『Many Shapes』以上に抑制されていて、ミニマルですらある。バンド・アンサンブルのタイトさが緊張感を強調し、そのぶん、ひとつひとつの音やフレーズ、リリックの切れ端に自然と注意が向いていく。特に、ドラマー・こばやしのぞみの本作における演奏は、一聴して地味ながらも特筆すべきものだろう。リンゴ・スターのようなフィルインや抜き差し加減からは、フレーズや叩き方、あるいは〈どこで叩かないか〉を熟考した形跡が感じられる。そんなドラムの音色を特徴づけている、TAMTAMの高橋アフィによるドラムテックも適切だ。
ゆらゆら帝国の『空洞です』(2007年)、OGRE YOU ASSHOLEの『homely』(2011年)、ミツメの『ささやき』(2014年)、あるいはステレオラブの『Dots And Loops』(97年)やヨ・ラ・テンゴの『And Then Nothing Turned Itself Inside-Out』(2000年)、ペイヴメント、リアル・エステイト、マック・デマルコ……『Fragment』のサウンドや伊藤の繊細なヴォーカリゼーションに耳を傾けていると、ここ20年のインディー・ロックにおけるもっとも重要な作品のいくつかを思い出さずにはいられない。それらが持っていた独特のムードが混交し、波のように押し寄せては引いていくのが感じられる。
細部まで滑らかにトリートメントされたサウンドのなかで、ときおり響くささくれだったファズ・ギターや奇妙なベースライン、そして伊藤の言葉。それらもまた、断片である。点と点はつながることなく、ただそこにある。あきらめているのでもなく、しらけているのでもなく、ただそこにあるものを〈ただそこにあるもの〉として見つめること――それが、Taiko Super Kicksが『Fragment』において表現しようとしていることなのだろう。